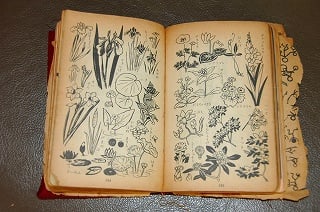ここはどこか不明。ススキと眺望が開ける美しい場所。
座った背中の後ろに、無造作に置き、倒れてしまったたぶんワニ皮のバッグ(これは見覚えがある)。
思わず座って景色を眺めたと思われる。
たぶん、今生きていたら、
「あ~ら、みっともない!年寄りの写真なんて出さないでよ~」
と言うでしょう。
着物を着て、夜行列車に乗ったり、バスに乗ったり、電車を乗り換えたり、山道や海岸を歩いたり・・・
昔の人は、皆が自分なりの着方で、さらりと、毎日、着物を着ていたのだな~と思う。
祖母の旅が盛んだったのは、昭和30年代後半から昭和50年頃までだった。
私はまだ子供だったので、旅について、お酒や地方の料理について、三味線について、興味を持って一緒に話すような歳でなかった。
それが残念。
記憶をたどると、たとえば、京都のハモ、フグのヒレ酒、鴨川をどり、長楽館、円山公園、神護寺など、両親や叔母に話していたように思う。
「如在」
と書かれた書を、5年前に、京都のあるご住職がくださった。
(今はもういらっしゃらないので、教えていただくことが出来ません。ここにあなたが居ると思って、学ばせてもらいます・・・)という意味だと話してくださった。
まさに、そんな気持ちかな~と。