高校生を始めとする若い人たちのスイッチを入れる活動をするNPO法人カタリバ。
カタリバが主催する「カタリバ大学」はすでに今回32講目だが、僕は今回初めて参加した。
今回のテーマは「震災後のニッポン」。
被災地の方々に何かできないものだろうかと思いながら、何一つ行動を起こせない意気地なしの自分。
今回のカタリバ大学へ参加してみたら何かヒントがもらえるかも知れないと云う調子好い期待と、参加費として払ったお金の一部が被災地への寄付に使われると云うことから参加してみようと思った。
カタリバ大学学長の東北芸術工科大学の寺脇研先生をはじめ、首都大学東京の宮台真司先生、北海道大学の中島岳志先生など豪華な顔ぶれの先生方がパネリスト。各先生の専門的な視点から語られる話は、当たり前だが質が高く、興味深くて、真摯である。
特に後半、終了間際の盛り上がりがサイコーに面白くて、この流れが引き継がれるという懇親会への参加は最後の最後まで迷った。
聴講者は思った通り若い人が多くて、誰もがメモを取るか、パソコンのキーボードを叩き、真剣かつ集中してこの会議を見つめている。ボーッとしてる人など一人としていない。
パネリストの先生方の話は本当に面白いのだけれど、聴講者がある程度知識を持っているということが前提になっているようで、最初から高いレベルで話が進行していく。そんな話にしっかり参加している若い人たちを見ると、すごく感心するし、なんだ日本も捨てたもんじゃないな、と少しホッとする。
そんな僕もマイケル・サンデルぐらいは読んでいたので何とかついていけて良かった。
それにしても、こんなに面白いイベントだとは思わなかった。想像をはるかに超えた面白さだった。ありがとう、今村さん。
天ぷら油から自動車の燃料などを作るTOKYO油田という会社の染谷さんという女性もパネリストの一人。そんな会社や技術があるのか、というのがまず驚きだった。
染谷さんの話の中で、現在の日本の自粛についての意見があった。被災地の人たちのことを慮ってイベントや祭りを自粛するその気持ちは分かるけれど、雇用や経済で被災地を支えて行くべき東京が、過剰な自粛で元気を失ってしまっては、その使命を果たせないのではないかと言っていたのに共感する。
僕も、自粛自粛とおとなしくするのだけがいいとは思わない。入学式なのに「おめでとう」という言葉が言えないところもあるらしい。でも、きっと被災された方はそんなことは望んじゃいないと思う。子どもが成長して小学校に入学した事と震災は区別するべきだと思う。
そんなわけで、明日は友人たちとお花見だ。盛り上がるぞ。
カタリバが主催する「カタリバ大学」はすでに今回32講目だが、僕は今回初めて参加した。
今回のテーマは「震災後のニッポン」。
被災地の方々に何かできないものだろうかと思いながら、何一つ行動を起こせない意気地なしの自分。
今回のカタリバ大学へ参加してみたら何かヒントがもらえるかも知れないと云う調子好い期待と、参加費として払ったお金の一部が被災地への寄付に使われると云うことから参加してみようと思った。
カタリバ大学学長の東北芸術工科大学の寺脇研先生をはじめ、首都大学東京の宮台真司先生、北海道大学の中島岳志先生など豪華な顔ぶれの先生方がパネリスト。各先生の専門的な視点から語られる話は、当たり前だが質が高く、興味深くて、真摯である。
特に後半、終了間際の盛り上がりがサイコーに面白くて、この流れが引き継がれるという懇親会への参加は最後の最後まで迷った。
聴講者は思った通り若い人が多くて、誰もがメモを取るか、パソコンのキーボードを叩き、真剣かつ集中してこの会議を見つめている。ボーッとしてる人など一人としていない。
パネリストの先生方の話は本当に面白いのだけれど、聴講者がある程度知識を持っているということが前提になっているようで、最初から高いレベルで話が進行していく。そんな話にしっかり参加している若い人たちを見ると、すごく感心するし、なんだ日本も捨てたもんじゃないな、と少しホッとする。
そんな僕もマイケル・サンデルぐらいは読んでいたので何とかついていけて良かった。
それにしても、こんなに面白いイベントだとは思わなかった。想像をはるかに超えた面白さだった。ありがとう、今村さん。
天ぷら油から自動車の燃料などを作るTOKYO油田という会社の染谷さんという女性もパネリストの一人。そんな会社や技術があるのか、というのがまず驚きだった。
染谷さんの話の中で、現在の日本の自粛についての意見があった。被災地の人たちのことを慮ってイベントや祭りを自粛するその気持ちは分かるけれど、雇用や経済で被災地を支えて行くべき東京が、過剰な自粛で元気を失ってしまっては、その使命を果たせないのではないかと言っていたのに共感する。
僕も、自粛自粛とおとなしくするのだけがいいとは思わない。入学式なのに「おめでとう」という言葉が言えないところもあるらしい。でも、きっと被災された方はそんなことは望んじゃいないと思う。子どもが成長して小学校に入学した事と震災は区別するべきだと思う。
そんなわけで、明日は友人たちとお花見だ。盛り上がるぞ。












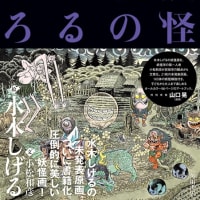
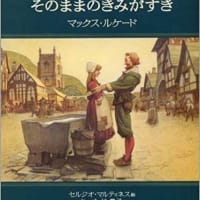


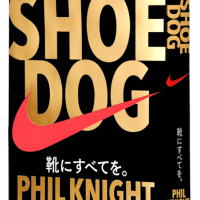



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます