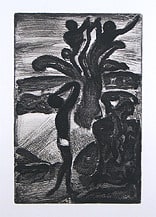昨日、念願のダリを見てきました。寒風吹き荒ぶ中、一時間も待たされた挙句、人、人、人のおしくら饅頭。でも、それだけしても見る価値のある絵でした。
今回ダリの作品を見て受けた衝撃は、不思議なことにローマでミケランジェロを見たときの衝撃に似ていました。形容しがたい圧倒的なパワーが巨大な岩のようにずしんと圧し掛かってくるような感覚。バチカンのシスティーナ礼拝堂で立ち尽くしたように、ダリの絵の前でしばし放心してしまいました。
事実、ダリはミケランジェロを敬愛していたようで、ミケランジェロに関する論文も執筆しています。
今回の展覧会でもミケランジェロの作品を題材にしたものが見られます。一番わかりやすいのは「地質学的循環ラ・ピエタ」。これはバチカンにあるミケランジェロの彫刻をモチーフにしています。ダリの作品ではイエスを抱きかかえるマリアの像に穴が空き、今にも崩れ落ちそう。絵を書いた頃、ダリの最愛の妻ガラが衰弱しつつあったこともあり、自分達の姿をこの絵に移し込んでいるのかも知れません。
また、「世界教会会議」は教皇ヨハネ23世の功績を讃えた作品ですが、ミケランジェロの「最後の審判」に大いに影響を受けているように思われます。主題は違うとは言え、構図は非常に似通っていますし、どちらも非常に巨大な絵であるという共通点があります。また、妻ガラを聖女へレナに見立てて書き込んでいますが、このポーズはミケランジェロのモーゼ像のものですね。
私がダリとミケランジェロに感じるパワーと言うのは、何かとんでもないもの、普通の人間なら想像すらできないようなことを具現化してしまう強い衝動です。
ダリの絵を見れば誰でも一度は困惑するはずです。それはダリの絵がとても現実離れしたもので、一見意味がよくわからないから。当のダリ自身ですら自分の絵を「理解でないことがある」と言っています。普通の人ならそんなものは描こうとも思わないでしょう。ただ、そんな意味不明のイメージを確かな技量で緻密かつリアルに描ききる強い欲求と情熱がダリにはあった。これはバチカンの礼拝堂一面にたった一人で「天地創造」と「最後の審判」を描ききったミケランジェロの情熱に通じるものだと私は思うのです(結果としてミケランジェロは視力を失ってしまいます)。そして何か常識の壁を突き破るような強烈なパワーが今の自分にはないことをとても不甲斐無くも思うのです。
大したブレイクスルーもなくダラダラと過ごしてしまった一年。来年こそは自分の道を切り拓いて行きたいと思います。