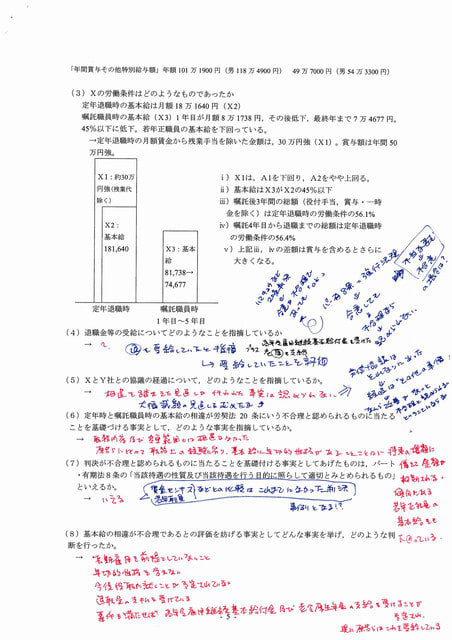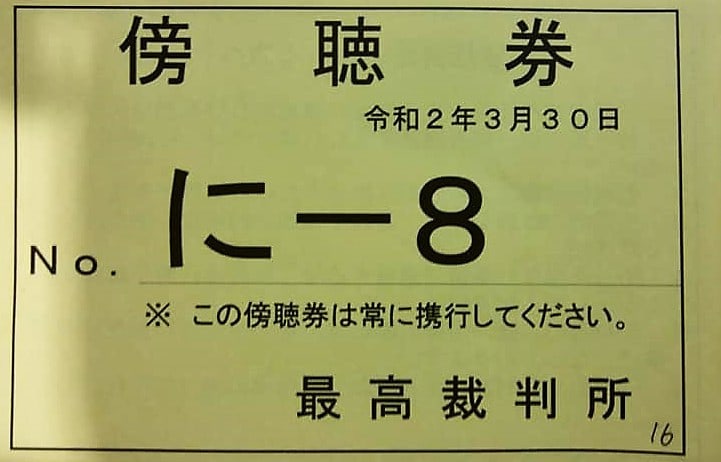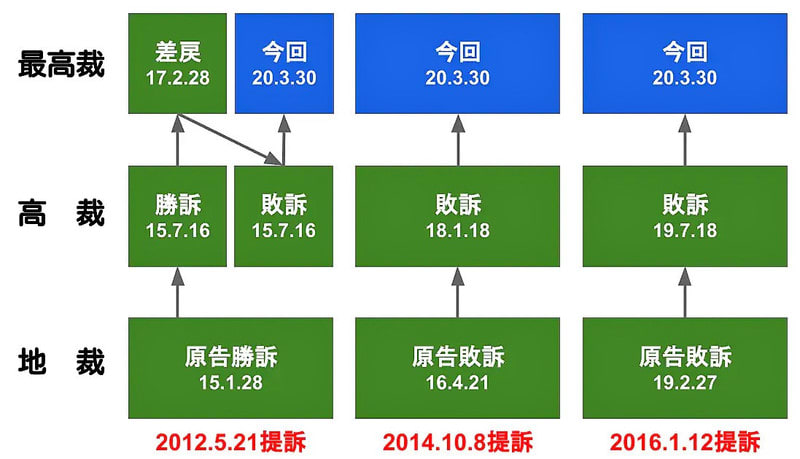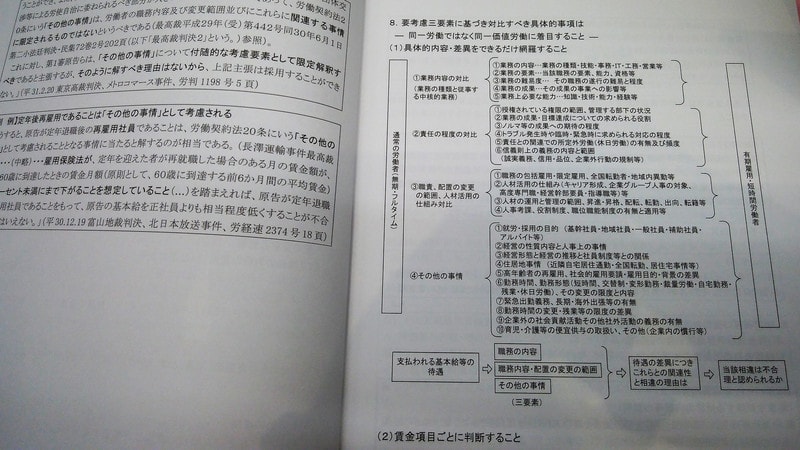5月28日、横浜市開港記念会館にて、神奈川労働弁護団主催「働き方改革法対応セミナー」~上限規制・有休・高プロ等の労働時間分野の法改正の向き合い方~を受講、講師は嶋崎量弁護士。
労働者側の弁護士であり、労働組合への強いメッセージが込められた講演だった、自分の講演のメモをこちらのブログに記載しておく。
国会審議では、有休どうでもいいけど、高プロだけは絶対に通してなるものかとやってきたが、しかし現場では、実は有休が結構大変。
しかしあるものは何でも使うのが労働運動、だから労組は、現実にどううまく使うかが重要。
労基法1条2項、大事な条文なんだが、労働関係の当事者、労働関係を生業にしている人も含めて、実はあまり読んでない。
労働基準法はあくまでも最低基準、なにより向上に努めなければならない、とまで書いてある。
労働組合は労働運動で何がとれるか、刑罰がある最低ライン、法律の最低ラインを守らせるだけでは労働運動ではない。
労働時間の上限規制、労働時間の規制強化だから事業者は早くから慌てていた。
36協定は過半数労働組合があればそこが締結当事者、だから過半数かどうかには意味が大きい、でも労組の組織率は17%しかない。でもだから意味が無いかということではない。
・過半数労働組合⇒非正規雇用増加による36協定締結権喪失⇒注意!締結権持っていると信じていたが、気がついたら過半数割れしている⇒まさに電通!
⇒組織拡大の契機に!⇒過半数労働組合でなくなるのは使用者にとっても死活問題⇒実践している組合が多数ある。
・重要性を増す過半数代表者⇒広範な決定権がある⇒集団的労使関係を意識していない職場でも、一つでも二つでも意見を言えるようになると大きな効果がある。
⇒形骸化して使用者の意のままに操られているのが過半数代表者であるが、使用者の意向に基づき選出された過半数代表者では違法になる。⇒民主的手続き⇒労働組合の価値を職場でわからせることができる。
・改正前 特別条項が「青天井」だと批判された⇒今までも縛りはあった(告示)⇒「45時間360時間」は例外で、特別条項は例外の例外⇒今まで過労死ラインを超える特別条項を結んでいる協定の事例ははたくさんあった。
・改正後 例外が法律でしっかり決まった、その例外の例外の「特別な事情」も上限が決められた。(休日の関係…法律の立て付けは時間外労働と休日労働を分けているからこうなる)
・これが特別かどうか…⇒通常予見される残業…原則+例外、通常予見することが出来ない残業…特別条項
⇒全体にかかる罰則付き上限時間 ①坑内労働…、②100時間、③80時間
原則残業許されないし、許されるのは通常予見される残業⇒3月の年度末が忙しくなるのは「通常予見」できるもの⇒労働組合は「特別な事情」を簡単に受け入れてはならない
でも、労働者はこそこそ働いてしまうから、じゃあどのような人員配置が必要か労使で検討しよう。労働組合の出番でしょ。
通常予見が出来ない業務量の大幅な増加などに伴い臨時的に…⇒1年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に発生する業務⇒職場で業務の再確認が必要…使用者側は躍起になってやっている⇒労働組合もしっかり対応を
⇒(ガイドラインや36協定の届け例を見ても…←事例は緩すぎる(汗))役所は受け付けてしまうけど、労働組合は簡単に受けてはならない。(IT企業なんて仕様の変更なんて日常茶飯事、もっと言えば取引先に文句言えよ(笑))
・上限規制が猶予されている業界がある、最近注目されたのは医者、数においては自動車の運転業務⇒なぜ過労死いっぱい出ている業界が猶予されるのか疑問がある⇒でも猶予されているけど無視されているわけではない。
・「100時間残業合法化?」という声もある⇒間違ってはいないけど、今までも100時間残業は出来たわけで、改めて合法化されたわけではない。⇒だから逆に100時間に近づけるという労使関係はおかしい。⇒残業をさせることが出来る「範囲」の基準を労使で引き下げる必要がある。
・上限規制の経過措置 ⇒2019年4月1に以降の期間を定めたもののみに適用⇒始期が3月31日以前のものは引き続き従前の協定が有効
・法の範囲内だから許されるというのは誤解⇒特例の上限内であってもまず安全配慮義務違反を負う⇒業務と発症の関連性が強いと評価される(労災認定される)⇒労基法の労働時間規制は最低基準である!
・36協定の活用を⇒残業は例外的な場合にしか出来ない⇒しかも労働者側に36協定締結する義務はない(安易に締結しない)⇒使用者に言われるままにサインする時代ではない。⇒締結権を武器に。
・よりよい労働条件・職場環境改善を勝ち取ろう!⇒労働者に労働組合が訴えられる時代(安易に結んでいたら「過労死を容認するのか」)⇒労働組合への責任追及
・できるだけ時間は「短く」⇒業務を細分化して書く、一般的・概括的な記載では許されない。
・求人者により企業選別される(人手不足加速、競争力低下による労働条件低下)⇒大企業だから選ばれるという時代ではなくなっている(例 電通)
・法の建前を貫く取り組みを⇒労働組合における活用を⇒義務的団体交渉事項
・罰則付き上限規制は完璧なのか?⇒実際にどんな形で過労死?⇒従来、青天井だった協定内の時間外労働で過労死した事案は多い。
・労働時間管理の徹底⇒安衛法改正…客観的労働時間把握義務(安衛法に逃げやがって、日和りやがって(笑))
・労基法上に時間管理の法的義務化、時間管理を怠った場合の罰則、企業名の公表
労働時間の適正把握義務
従前 把握する責務あり
改正 管理監督者・裁量労働も含め「医師の面接指導の履行確保」のため客観的な把握義務
⇒一人だろうが多数だろうが、管理監督者であろうが、長時間労働を放置して殺したらだめ。
書面による協定での代替休暇制度⇒お金(60時間超の割増賃金)⇒時間で返す(休暇)⇒これまであまり活用されていないがこれから活用されるのではないか、活用されたらいいな⇒生活残業となっている職場では怒られるかも知れないけれど、建前として賃金を上げていくとすれば、活用すればよい!
年次有給休暇時季指定義務
・年休の取得促進が狙いなだけの制度⇒使用者への義務化⇒労働者は年休をこれまでどおり好きなときにとればよい⇒無理矢理取らされる制度ではない!
「労働組合が出来ること。」
組織化の契機⇒休日数増加・取得率増加⇒生産性や就労意欲向上、離職率減少など使用者側のメリットを、現場の声として経営者に理解させる⇒取得を拒む要因除去策を検討する⇒支障が出ない人員配置、職場のニーズを吸い上げて使用者に要求する。
改正に伴っての年休の先行取得条項導入は?⇒強行されたら就業規則の不利益変更(労契法9条)←こんな話し合いも組合があれば出来る。
勤務間インターバル規制
・努力義務と法律に書かせた⇒使用者には努力義務⇒労働者には使用者に求めることが義務化された(ということ!)⇒厚労省のサイトに掲載された事例を是非参照⇒労働組合がもっと活用すべき⇒社労士が助成金のために出来ているのだから労働組合が出来ないわけがない!⇒企業の手柄になっているのはおかしい。
・労働組合として要求しないと始まらない!⇒前提、職場の労働組合内部で意識を認識すること(共有しなくてはいけない)
・労働者なら誰もが賛成?そうでもない⇒「仕事するのを邪魔するな」(出世・評価、やり甲斐、義務感)、「俺がいないと仕事は回らない!」そんなことはない、絶対に回る(笑)⇒だから労働時間把握がスタート
・通勤時間のカウント⇒過労死防止するには効果的⇒健康確保の意義からすれば当然(労災認定にはカウントされないが健康確保には重要な要素)
・勤務間インターバルは使用者側のメリットは絶大⇒業績が上がる(求人・生産性向上)ことを主張⇒36協定と同時に検討
労使での話し合い⇒労働組合がなければ出来ない⇒労組のないところでは社労士の助成金の提案で導入しているだけ!
有害な労働時間規制の緩和
裁量労働制の拡大⇒撤回⇒労働時間把握義務は課せられた⇒導入の厳格化も行われている
フレックスタイム制
高プロ⇒使わさないことが重要⇒導入するのはかなりハードルも高い⇒しかし広がらせないようにするのも重要⇒経営側は緩和・拡大を狙っている。⇒経営側は小さく産んで大きく育てる⇒自由な働き方ではない、使用者が自由になるだけだ。
・高プロ導入された会社では労働組合が魂を売ったということ!⇒労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議⇒ブラック労働組合認定!⇒叩かれるよ!⇒「こんなの入れちゃったら、ブラック企業認定だよ、やめときなよ、なんのメリットもないし、手続きも面倒くさいし!」と主張すればよい⇒賛成しなければよい。