はじめまして!成安デス。
ブログを開始します。実は他のブログからやってきました。過去ブログも着いて来ましたから良かったら一緒に読んでください。また、以前からの方もそのままお読みください。簡単なおねがいですみません。
「説法日誌」とは、数年来毎日、法華経を1品1品コツコツ解読してみましたら私は法華経の海の中で過ごすことが好きになり、研究を日誌にすることにしました。法華経がこんなに面白いとは私にとって最大な大発見でした。これさえあれば何も必要ない、元来面倒くさがりの私にとってこんなに素晴らしい宝物は他にありません。毎日書けるかどうかはわかりませんが、時々目を通していただけると皆でHAPPYLIFEになれてとても嬉しいです。今後ともよろしくおねがいします!
もし、良かったら5月1日からまぐまぐから有料メルマガ(140円/月々)を発行する予定ですので、是非とも購読をおねがいします! 毎月毎月、法華経全28品の1品ずつの解説説法を毎日1品ずつ28日間お届けします。是非ご愛顧おねがいします。
ご購読はこちらです ⇒ メールマガジン~MailING日月説法~
<月々28日配信分で¥140円/月(税込み)、1日配信当たりは¥5円/日(税込み)程度です!>
人気ブログランキングに参加中です。
もしブログの内容が良いと思ったら、その時は1日1回、下のお好きなバナーをポチってやってくれるととても助かります!
↓
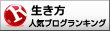
生き方 ブログランキングへ

シニアライフ ブログランキングへ

高齢者介護 ブログランキングへ
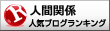
人間関係 ブログランキングへ

まちづくり ブログランキングへ
ブログを開始します。実は他のブログからやってきました。過去ブログも着いて来ましたから良かったら一緒に読んでください。また、以前からの方もそのままお読みください。簡単なおねがいですみません。
「説法日誌」とは、数年来毎日、法華経を1品1品コツコツ解読してみましたら私は法華経の海の中で過ごすことが好きになり、研究を日誌にすることにしました。法華経がこんなに面白いとは私にとって最大な大発見でした。これさえあれば何も必要ない、元来面倒くさがりの私にとってこんなに素晴らしい宝物は他にありません。毎日書けるかどうかはわかりませんが、時々目を通していただけると皆でHAPPYLIFEになれてとても嬉しいです。今後ともよろしくおねがいします!
もし、良かったら5月1日からまぐまぐから有料メルマガ(140円/月々)を発行する予定ですので、是非とも購読をおねがいします! 毎月毎月、法華経全28品の1品ずつの解説説法を毎日1品ずつ28日間お届けします。是非ご愛顧おねがいします。
ご購読はこちらです ⇒ メールマガジン~MailING日月説法~
<月々28日配信分で¥140円/月(税込み)、1日配信当たりは¥5円/日(税込み)程度です!>
人気ブログランキングに参加中です。
もしブログの内容が良いと思ったら、その時は1日1回、下のお好きなバナーをポチってやってくれるととても助かります!
↓
生き方 ブログランキングへ
シニアライフ ブログランキングへ
高齢者介護 ブログランキングへ
人間関係 ブログランキングへ
まちづくり ブログランキングへ










