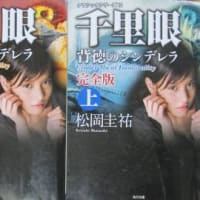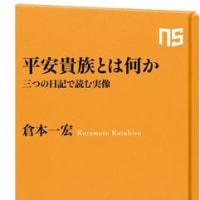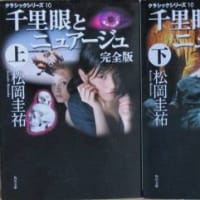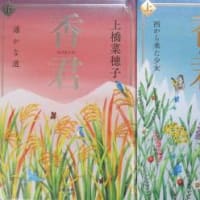「恋愛しない私」という条件設定をして、『源氏物語』は楽しめるかどうかという問いかけをタイトルにしている。地元の図書館の本紹介コーナーに並んでいた。『源氏物語』には関心を抱いているので、このタイトルを見て、興味を持った。『源氏物語』を読み継いでいるが、こんなタイトルの本は初めて!
勿論、本書のような『源氏物語』へのアプローチのしかたの本を読んだのも初めてである。
タイトルの問いかけに対する著者の回答をまず記しておこう。
「異性愛でない人間や、老後を共に暮らすような、あるいは困っている人同士で同居するような結婚の可能性を考えている人にとってこそ、『源氏物語』を今読み直す意義があるのです」(p199-200) と述べ、「あとがき」の中でもこの引用箇所と同趣旨の文の終わりで「『源氏物語』は今読むべき古典なのです」(p240) と結論づけている。
奥書の著者プロフィールは、「もともと専門は平安文学だが、恋愛や生殖に忌避的な女性の感性に注目し、日本近現代文学・文化も対象とする。現在の研究テーマは、動物・植物・人形表象」の研究者と記す。
本書は、2024年8月に単行本として刊行されている。
本書の構成をまずご紹介する。
はじめに セクシュアリティとアイデンティティ
第1章 仕事で恋愛をすること 現代におけるセクシュアリティとアイデンティティ
第2章 心と体で分けられた自己 『源氏物語』のアイデンティティ
第3章 融合する身体 宇治十帖のアイデンティティ①
第4章 浮舟の変身 宇治十帖のアイデンティティ②
第5章 セクシュアリティを自認しない世界 『源氏物語』のセクシュアリティ
第6章 作者と作品を結びつけること 紫式部のセクシュアリティ
おわりに
次に、著者の立ち位置と私が理解した事項を列挙しておきたい。
*現代社会において、アイデンティティやセクシュアリティという近代的な枠組みに疑問を持つ立場にある。
*作品と作者は切り離して研究する。古典作品はできるだけその時代の言葉や文化的文脈に即して読む試みをする。
*『源氏物語』に近代的な枠組み(セクシュアリティとアイデンティティ)は当てはまらない。
*『源氏物語』は必ずしも恋愛だけの物語ではない。
*仕事とオフィシャル(公)、プライヴェート(私)は結構可変的なものである。
この本、第1章は、副題にある通り、現代の事象についての分析から始まる。
第1章の内容は、私にとっては、使われる事例を含めて、初めて知ることばかり。著者は、はるな檸檬『ダルちゃん』、テレビドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』、テレビドラマ『恋せぬ二人』の3つを素材として、著者の問題意識を論じていく。内面・擬態・仕事・恋愛・プライヴェート・自己の領域・感情・好き・家族などが、キーワードとなっている。
この3つの素材については、あらすじが説明されているので、著者の論議をフォローしていくことはできた。ここであと2つ、未知の用語が論議に絡んでいた。おかげでこの用語を学ぶ機会にもなった。この用語がこの後、大きく関わって行く。
アロマンティック:「誰にも恋愛感情を持たない人」。恋愛傾向に関する用語。
アセクシュアル :「性的傾向の一つ」で「通常は、他者に性的に惹かれないこと」
である。(p45)
この二語は違う観点での分類なので、組み合わせのパターンは広がる。「なお、性的指向は白か黒かというような単純な二元論ではなく、範囲のようなものとして捉えられています」(p45) と言う。
本書に著者はこの二つの観点から見た自分自身の距離感、体験をも記述している。
著者は、近代に築かれた枠組みがセクシュアリティ、プライヴェート、オフィシャル、仕事などの相互関係と区分が現代社会において揺らぎつつあることを、この章で明らかにしていく。
そして、古典作品については、「近代とはまた異なった枠組みでものを考えていた時代の物語を読むことは、むしろアクチュアルな意味があると思うのです」(p67)と位置づけている。
つまり、第1章での分析が『源氏物語』への導入になっている。新鮮なアプローチだなぁと感じた。
第2章から第5章で『源氏物語』が分析の対象になる。ここで興味深い点は、近代日本のアイデンティティや価値観のもとに、『源氏物語』が解釈されてきた点を問題視しているところにある。近代的な価値観や構造による『源氏物語』解釈の解体をめざすというスタンスとアプローチである。著者は、『源氏物語』の中で使われ、私たちが現在も使っている言葉に着目して、その言葉を抽出し、『源氏物語』が書かれた時代を背景として、『源氏物語』に記述された文脈で、その言葉の使われ方を分析していくというアプローチが本書での研究手法となっている。
第2章:『源氏物語』の内、光源氏が主人公となる部分を範囲とする。
会話や内心語の文脈から「内面」が語られる箇所を分析
「身」と「心」という語を使用した箇所の分析
近代的な「アイデンティティ」との対比という観点でその相違を論じる。
第3章:『源氏物語』の内、宇治十帖の部分を範囲とする。
「身を分く」「同じ身」という言葉を使用した箇所を分析
この物語における「分身」概念の考察
近代的な「アイデンティティ」との対比という観点でその相違を論じる。
第4章:第3章に続く形で、「かはれる身」という言葉を使用した箇所を分析
第5章:『源氏物語』にセクシュアリティのように見える要素があるかの分析
女三宮、宮の御方、紫の上、源氏の女性的な美しさ、小君と光源氏の関係、
須磨巻のホモソーシャリティなどを分析する。
これらの各章で、どのように分析され論じられていくかは本書をお読みいただきたい。
特に印象に残るのは、第5章の子見出しの一つ、「六条院は異性愛の帝国かーーーーポリアモリーについて」から章末尾までの箇所。著者は「六条院が恋愛関係や性愛関係のみによって構成された空間ではないという点」(p193) に着目していく。六条院には、漠然と光源氏が築いたいわばハーレム的なイメージを根底に持っていたので、本書の分析は実に新鮮であり、頭にガツン! 気づかされた箇所である。
「ポリアモリー」という用語もまた、私には初見だった。”「合意の上で」「同時に複数のパートナーと「誠実」に愛の関係を築く」ことを指す言葉”(p192) だと言う。
最初に著者の立ち位置を述べた。最後の第6章は、その逆を行く。なぜか?
「しかしながら、作者と作品を結びつける発想は、近代的なセクシュアリティとアイデンティティの問題と、実は根深く関わっています。近代においては恋愛や性愛に関わる何らかの『告白』があることが人間の『内面』と見なされ、私小説の構造は、その語り手や主人公と作者を同一視しました」(p204) という背景と、先行研究での言及を踏まえて、「紫式部」の恋愛やセクシュアリティについてこの章で論じている。
『紫式部日記』と『紫式部集』が分析の対象となっている。この章の最初に、「セクシュアリティを読み取ることができないことを示すことによって、セクシュアリティとアイデンティティの結びつきを解体することを試みます」(p204) 著者は記す。
第6章内の大見出しをご紹介しておこう。
1 紫式部は「同性愛者」だったか
2 「紫式部」の恋愛
3 水の上の戯れ
出版物等では、あまり表に出てこない、読むことのない側面だが、研究論文レベルでは結構論議され、研究されてきているようだ。その一端もうかがえておもしろい。
こういう分析のしかたもあるのか・・・・と、その分析、論述を楽しめて視野が広がる一書である。
ご一読ありがとうございます。
追補 2025.2.13 21:00
ブログ記事を投稿した後に、ネット検索していて入手した関連情報を補足します。
KUNILABOブックトーク2025第二弾 西原志保『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』(春秋社) NPO法人国立人文研究所 YouTube
著者も参加したZOOM会議によるディスカッションの動画。
『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』(西原志保)編集後記
あらきさんの編集覚え書き :「no+e」
恋愛ばかりが重要なのですか? 『源氏物語』から仕事とプライヴェートの問題を考える
2024.10.3 記事:春秋社 :「じんぶん堂」
本書の「まえがき」が全文を紹介されています。
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
勿論、本書のような『源氏物語』へのアプローチのしかたの本を読んだのも初めてである。
タイトルの問いかけに対する著者の回答をまず記しておこう。
「異性愛でない人間や、老後を共に暮らすような、あるいは困っている人同士で同居するような結婚の可能性を考えている人にとってこそ、『源氏物語』を今読み直す意義があるのです」(p199-200) と述べ、「あとがき」の中でもこの引用箇所と同趣旨の文の終わりで「『源氏物語』は今読むべき古典なのです」(p240) と結論づけている。
奥書の著者プロフィールは、「もともと専門は平安文学だが、恋愛や生殖に忌避的な女性の感性に注目し、日本近現代文学・文化も対象とする。現在の研究テーマは、動物・植物・人形表象」の研究者と記す。
本書は、2024年8月に単行本として刊行されている。
本書の構成をまずご紹介する。
はじめに セクシュアリティとアイデンティティ
第1章 仕事で恋愛をすること 現代におけるセクシュアリティとアイデンティティ
第2章 心と体で分けられた自己 『源氏物語』のアイデンティティ
第3章 融合する身体 宇治十帖のアイデンティティ①
第4章 浮舟の変身 宇治十帖のアイデンティティ②
第5章 セクシュアリティを自認しない世界 『源氏物語』のセクシュアリティ
第6章 作者と作品を結びつけること 紫式部のセクシュアリティ
おわりに
次に、著者の立ち位置と私が理解した事項を列挙しておきたい。
*現代社会において、アイデンティティやセクシュアリティという近代的な枠組みに疑問を持つ立場にある。
*作品と作者は切り離して研究する。古典作品はできるだけその時代の言葉や文化的文脈に即して読む試みをする。
*『源氏物語』に近代的な枠組み(セクシュアリティとアイデンティティ)は当てはまらない。
*『源氏物語』は必ずしも恋愛だけの物語ではない。
*仕事とオフィシャル(公)、プライヴェート(私)は結構可変的なものである。
この本、第1章は、副題にある通り、現代の事象についての分析から始まる。
第1章の内容は、私にとっては、使われる事例を含めて、初めて知ることばかり。著者は、はるな檸檬『ダルちゃん』、テレビドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』、テレビドラマ『恋せぬ二人』の3つを素材として、著者の問題意識を論じていく。内面・擬態・仕事・恋愛・プライヴェート・自己の領域・感情・好き・家族などが、キーワードとなっている。
この3つの素材については、あらすじが説明されているので、著者の論議をフォローしていくことはできた。ここであと2つ、未知の用語が論議に絡んでいた。おかげでこの用語を学ぶ機会にもなった。この用語がこの後、大きく関わって行く。
アロマンティック:「誰にも恋愛感情を持たない人」。恋愛傾向に関する用語。
アセクシュアル :「性的傾向の一つ」で「通常は、他者に性的に惹かれないこと」
である。(p45)
この二語は違う観点での分類なので、組み合わせのパターンは広がる。「なお、性的指向は白か黒かというような単純な二元論ではなく、範囲のようなものとして捉えられています」(p45) と言う。
本書に著者はこの二つの観点から見た自分自身の距離感、体験をも記述している。
著者は、近代に築かれた枠組みがセクシュアリティ、プライヴェート、オフィシャル、仕事などの相互関係と区分が現代社会において揺らぎつつあることを、この章で明らかにしていく。
そして、古典作品については、「近代とはまた異なった枠組みでものを考えていた時代の物語を読むことは、むしろアクチュアルな意味があると思うのです」(p67)と位置づけている。
つまり、第1章での分析が『源氏物語』への導入になっている。新鮮なアプローチだなぁと感じた。
第2章から第5章で『源氏物語』が分析の対象になる。ここで興味深い点は、近代日本のアイデンティティや価値観のもとに、『源氏物語』が解釈されてきた点を問題視しているところにある。近代的な価値観や構造による『源氏物語』解釈の解体をめざすというスタンスとアプローチである。著者は、『源氏物語』の中で使われ、私たちが現在も使っている言葉に着目して、その言葉を抽出し、『源氏物語』が書かれた時代を背景として、『源氏物語』に記述された文脈で、その言葉の使われ方を分析していくというアプローチが本書での研究手法となっている。
第2章:『源氏物語』の内、光源氏が主人公となる部分を範囲とする。
会話や内心語の文脈から「内面」が語られる箇所を分析
「身」と「心」という語を使用した箇所の分析
近代的な「アイデンティティ」との対比という観点でその相違を論じる。
第3章:『源氏物語』の内、宇治十帖の部分を範囲とする。
「身を分く」「同じ身」という言葉を使用した箇所を分析
この物語における「分身」概念の考察
近代的な「アイデンティティ」との対比という観点でその相違を論じる。
第4章:第3章に続く形で、「かはれる身」という言葉を使用した箇所を分析
第5章:『源氏物語』にセクシュアリティのように見える要素があるかの分析
女三宮、宮の御方、紫の上、源氏の女性的な美しさ、小君と光源氏の関係、
須磨巻のホモソーシャリティなどを分析する。
これらの各章で、どのように分析され論じられていくかは本書をお読みいただきたい。
特に印象に残るのは、第5章の子見出しの一つ、「六条院は異性愛の帝国かーーーーポリアモリーについて」から章末尾までの箇所。著者は「六条院が恋愛関係や性愛関係のみによって構成された空間ではないという点」(p193) に着目していく。六条院には、漠然と光源氏が築いたいわばハーレム的なイメージを根底に持っていたので、本書の分析は実に新鮮であり、頭にガツン! 気づかされた箇所である。
「ポリアモリー」という用語もまた、私には初見だった。”「合意の上で」「同時に複数のパートナーと「誠実」に愛の関係を築く」ことを指す言葉”(p192) だと言う。
最初に著者の立ち位置を述べた。最後の第6章は、その逆を行く。なぜか?
「しかしながら、作者と作品を結びつける発想は、近代的なセクシュアリティとアイデンティティの問題と、実は根深く関わっています。近代においては恋愛や性愛に関わる何らかの『告白』があることが人間の『内面』と見なされ、私小説の構造は、その語り手や主人公と作者を同一視しました」(p204) という背景と、先行研究での言及を踏まえて、「紫式部」の恋愛やセクシュアリティについてこの章で論じている。
『紫式部日記』と『紫式部集』が分析の対象となっている。この章の最初に、「セクシュアリティを読み取ることができないことを示すことによって、セクシュアリティとアイデンティティの結びつきを解体することを試みます」(p204) 著者は記す。
第6章内の大見出しをご紹介しておこう。
1 紫式部は「同性愛者」だったか
2 「紫式部」の恋愛
3 水の上の戯れ
出版物等では、あまり表に出てこない、読むことのない側面だが、研究論文レベルでは結構論議され、研究されてきているようだ。その一端もうかがえておもしろい。
こういう分析のしかたもあるのか・・・・と、その分析、論述を楽しめて視野が広がる一書である。
ご一読ありがとうございます。
追補 2025.2.13 21:00
ブログ記事を投稿した後に、ネット検索していて入手した関連情報を補足します。
KUNILABOブックトーク2025第二弾 西原志保『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』(春秋社) NPO法人国立人文研究所 YouTube
著者も参加したZOOM会議によるディスカッションの動画。
『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』(西原志保)編集後記
あらきさんの編集覚え書き :「no+e」
恋愛ばかりが重要なのですか? 『源氏物語』から仕事とプライヴェートの問題を考える
2024.10.3 記事:春秋社 :「じんぶん堂」
本書の「まえがき」が全文を紹介されています。
ネットに情報を掲載された皆様に感謝!
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)