人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける
あなたのおっしゃることは、さあ、本心なんでしょうか。私には分からないですね。なじみの土地では、昔と同じ花の香りが匂ってくるのものですよ。
人はいさ心も知らず 『古今集』の詞書によると、長谷寺参詣の際に定宿にしていた家の主人が、貫之が疎遠であったことについて文句を言ったとある。このことから「人」は、その主人。「は」は、区別を表す係助詞。「いさ」は下に打消の語をともない、「さあ(~ない)」の意を表す陳述の副詞。「心」は、本心。「も」は、強意の係助詞。「ず」は、打消の助動詞。「あなたは、さあ、本心かどうか、(私は)わからない」の意。二句切れ。
ふるさとは 昔なじみの場所。「は」は、区別を表す係助詞。「人は」に対応する句。
花ぞ昔の香ににほひける 「ぞ」と「ける」は、係り結び。「花」は、一般には桜であるが、この場合は、「香ににほひ」とあり、「梅」の意。「ぞ」は、強意の係助詞。「にほひ」は、「にほふ」の連用形で、嗅覚のかぐわしさのみならず、視覚の美しさも表す。「ける」は、詠嘆の助動詞「けり」の連体形で、「ぞ」の結び。今まで意識していなかった事実に気づいたことを表す。「花ぞ昔の香ににほひける」は、「梅の花は昔と同じ香りを匂わせているなあ」という意。これは、主人の心を「花の香」になぞらえ、「あなたが昔と同様に暖かく迎えてくれるのはお見通しですよ」ということを暗に示している。
※ 全く異なる解釈として、「花の香は今も昔も同じであるが、人の心変わりやすく、あなたの心も私の知ったことではない」という内容であるとする説もある。この歌は、主人の不満に対する即興の返答であり、親しさゆえの皮肉まじりの会話なのか、身も蓋もない険悪な反論なのかで見解が分かれている。
きのつらゆき (866?~945?)
平安前期を代表する歌人。三十六歌仙の一人。『古今集』の撰者の一人にして仮名序の執筆者。最初のかな日記である『土佐日記』を著す。
あなたのおっしゃることは、さあ、本心なんでしょうか。私には分からないですね。なじみの土地では、昔と同じ花の香りが匂ってくるのものですよ。
人はいさ心も知らず 『古今集』の詞書によると、長谷寺参詣の際に定宿にしていた家の主人が、貫之が疎遠であったことについて文句を言ったとある。このことから「人」は、その主人。「は」は、区別を表す係助詞。「いさ」は下に打消の語をともない、「さあ(~ない)」の意を表す陳述の副詞。「心」は、本心。「も」は、強意の係助詞。「ず」は、打消の助動詞。「あなたは、さあ、本心かどうか、(私は)わからない」の意。二句切れ。
ふるさとは 昔なじみの場所。「は」は、区別を表す係助詞。「人は」に対応する句。
花ぞ昔の香ににほひける 「ぞ」と「ける」は、係り結び。「花」は、一般には桜であるが、この場合は、「香ににほひ」とあり、「梅」の意。「ぞ」は、強意の係助詞。「にほひ」は、「にほふ」の連用形で、嗅覚のかぐわしさのみならず、視覚の美しさも表す。「ける」は、詠嘆の助動詞「けり」の連体形で、「ぞ」の結び。今まで意識していなかった事実に気づいたことを表す。「花ぞ昔の香ににほひける」は、「梅の花は昔と同じ香りを匂わせているなあ」という意。これは、主人の心を「花の香」になぞらえ、「あなたが昔と同様に暖かく迎えてくれるのはお見通しですよ」ということを暗に示している。
※ 全く異なる解釈として、「花の香は今も昔も同じであるが、人の心変わりやすく、あなたの心も私の知ったことではない」という内容であるとする説もある。この歌は、主人の不満に対する即興の返答であり、親しさゆえの皮肉まじりの会話なのか、身も蓋もない険悪な反論なのかで見解が分かれている。
きのつらゆき (866?~945?)
平安前期を代表する歌人。三十六歌仙の一人。『古今集』の撰者の一人にして仮名序の執筆者。最初のかな日記である『土佐日記』を著す。











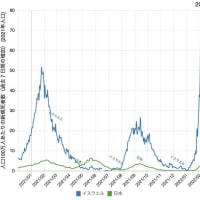
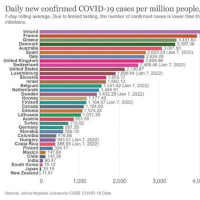
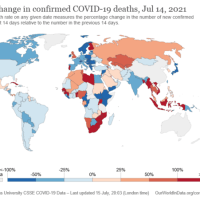
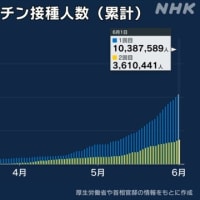
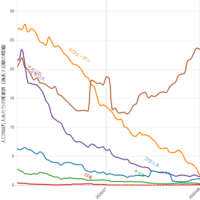
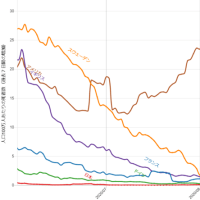
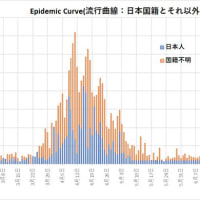
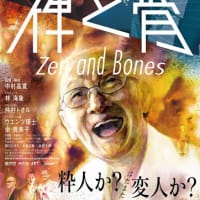







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます