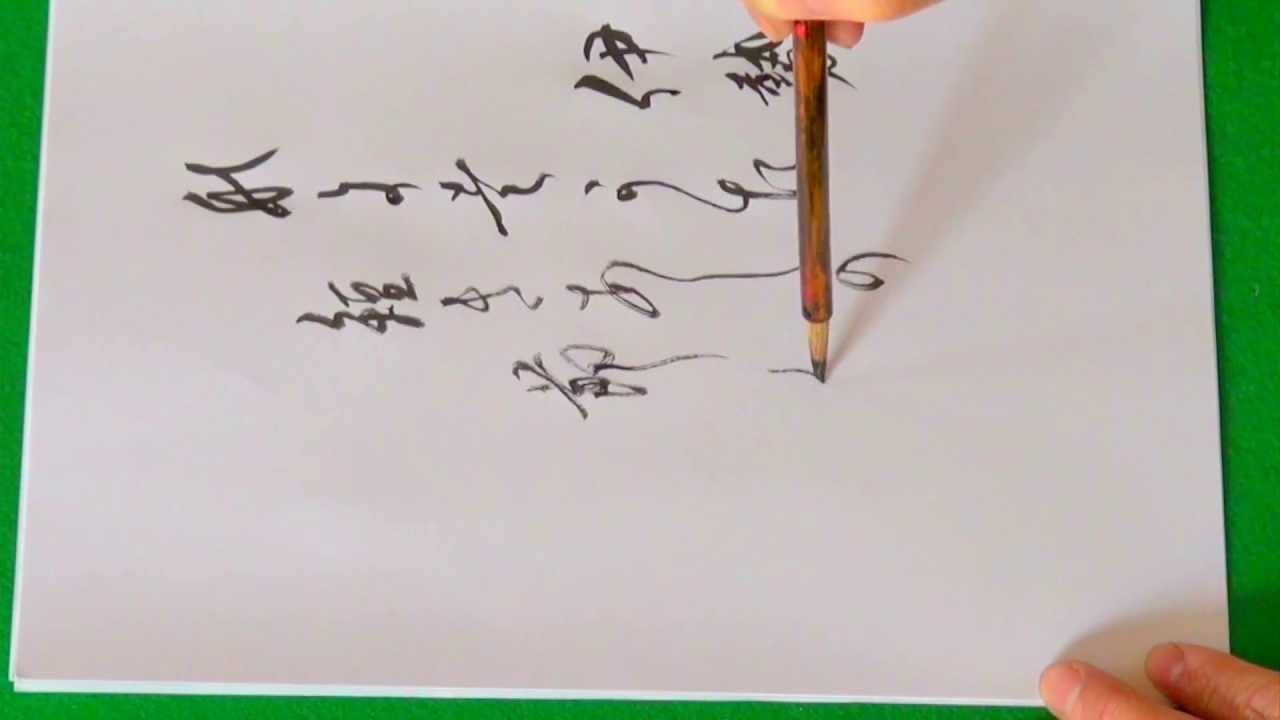恨みわび 干さぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ
恨みに恨みぬいて、ついには恨む気力すら失って、涙に濡れた袖が乾く暇もありません。そんな涙で朽ちそうな袖さえ惜しいのに、恋の浮名で朽ちてしまうであろう私の評判がなおさら惜しいのです。
恨みわび 「わび」は、バ行上二段活用の動詞「わぶ」の連用形で、~する気がなくなるの意。
ほさぬ袖だにあるものを 「ほさぬ」は、“ほさ+ぬ”で干さない、即ち、(涙で)濡れたままにしているの意。「だに」は、軽いものをあげて重いものを類推させる副助詞で、~でさえもの意。「ものを」は、逆接の接続助詞で、~のにの意。「ほさぬ袖だにあるものを」で、涙で濡れて朽ちそうな袖さえ惜しいのにの意。ただし、“涙で濡れた袖さえ朽ちずにあるのに”と解釈する説もある。
恋に朽ちなむ 「に」は、原因・理由を表す格助詞。「な」は、完了の助動詞で強意を表す。「む」は、推量の助動詞の連体形。恋のせいで朽ちてしまうであろう。
名こそ惜しけれ 「こそ」と「惜しけれ」は、係り結び。「名」は、評判。「こそ」は、強意の係助詞。「惜しけれ」は、形容詞の已然形。
後拾遺集の詞書に、「永承六年、内裏歌合に」とあり、具体的な出来事の際に詠まれた歌ではない。しかし、恋多き女性として有名であった相模らしい実感のこもった歌である。
さがみ (生没年不詳)
平安中期の歌人。相模守大江公資(きんより)の妻。公資と離婚後、多数の男性と関係を持って評判となった。
恨みに恨みぬいて、ついには恨む気力すら失って、涙に濡れた袖が乾く暇もありません。そんな涙で朽ちそうな袖さえ惜しいのに、恋の浮名で朽ちてしまうであろう私の評判がなおさら惜しいのです。
恨みわび 「わび」は、バ行上二段活用の動詞「わぶ」の連用形で、~する気がなくなるの意。
ほさぬ袖だにあるものを 「ほさぬ」は、“ほさ+ぬ”で干さない、即ち、(涙で)濡れたままにしているの意。「だに」は、軽いものをあげて重いものを類推させる副助詞で、~でさえもの意。「ものを」は、逆接の接続助詞で、~のにの意。「ほさぬ袖だにあるものを」で、涙で濡れて朽ちそうな袖さえ惜しいのにの意。ただし、“涙で濡れた袖さえ朽ちずにあるのに”と解釈する説もある。
恋に朽ちなむ 「に」は、原因・理由を表す格助詞。「な」は、完了の助動詞で強意を表す。「む」は、推量の助動詞の連体形。恋のせいで朽ちてしまうであろう。
名こそ惜しけれ 「こそ」と「惜しけれ」は、係り結び。「名」は、評判。「こそ」は、強意の係助詞。「惜しけれ」は、形容詞の已然形。
後拾遺集の詞書に、「永承六年、内裏歌合に」とあり、具体的な出来事の際に詠まれた歌ではない。しかし、恋多き女性として有名であった相模らしい実感のこもった歌である。
さがみ (生没年不詳)
平安中期の歌人。相模守大江公資(きんより)の妻。公資と離婚後、多数の男性と関係を持って評判となった。
朝ぼらけ 宇治の川霧 絶えだえに あらはれ渡る 瀬々の網代木
朝がほのぼのと明けるころ、宇治川の川面に立ちこめていた川霧がところどころ晴れていって、その合間から現れてきたあちこちの瀬に打ち込まれた網代木よ。
朝ぼらけ 夜が明けて、ほのぼのと明るくなる時分。暁(あかつき)→曙(あけぼの)・東雲(しののめ)→朝ぼらけの順で明るくなる。
宇治の川霧 「宇治」は、現在の京都府宇治市。瀬田川が、宇治川となり、木津川・桂川と合流して淀川となって、大阪湾に到る。
たえだえに 「川霧」を受けて、川霧が徐々に晴れていくさまを表す主述関係であるとともに、「あらはれわたる」に続いて網代木があちこちに見えるようになってきたさまを表す連用修飾関係となっている。
あらはれわたる瀬々の網代木 「わたる」は、網代木が現れる、即ち、見える状況が時間的・空間的に広がるさまを表す。「瀬々」は、あちこちの瀬、即ち、川の水深が浅い部分。「網代」は、網の代わりに木や竹を編んで作った漁具。それを立てる杭が網代木。
千載集の詞書によると、「宇治にまかりてはべりけるときよめる」とある。宇治川の上流、瀬田川が琵琶湖から発する地、瀬田の対岸は膳所(ぜぜ)であり、実際に宇治からは見えないが、川霧が晴れていく空間的な広がりを象徴する地名として意識したかもしれない。また、宇治と瀬田の中間点は石山であり、紫式部は、石山寺で源氏物語の構想を練ったとされ、その宇治十貼に登場する浮舟は宇治川で入水に失敗した後に尼になるという件がある。宇治川を見た定頼が、これらさまざまな背景をもとに、この歌を詠んだ可能性は高く、単純な叙景詩ではない趣を持った作品であると言える。
ごんちゅうなごんさだより (995~1045)
藤原定頼(ふじわらのさだより) 平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。藤原公任の子。容姿端麗で社交的な反面、小式部内侍をからかった時に即興の歌で言い負かされてそそくさと逃げ帰るなど軽率なところがあった。
朝がほのぼのと明けるころ、宇治川の川面に立ちこめていた川霧がところどころ晴れていって、その合間から現れてきたあちこちの瀬に打ち込まれた網代木よ。
朝ぼらけ 夜が明けて、ほのぼのと明るくなる時分。暁(あかつき)→曙(あけぼの)・東雲(しののめ)→朝ぼらけの順で明るくなる。
宇治の川霧 「宇治」は、現在の京都府宇治市。瀬田川が、宇治川となり、木津川・桂川と合流して淀川となって、大阪湾に到る。
たえだえに 「川霧」を受けて、川霧が徐々に晴れていくさまを表す主述関係であるとともに、「あらはれわたる」に続いて網代木があちこちに見えるようになってきたさまを表す連用修飾関係となっている。
あらはれわたる瀬々の網代木 「わたる」は、網代木が現れる、即ち、見える状況が時間的・空間的に広がるさまを表す。「瀬々」は、あちこちの瀬、即ち、川の水深が浅い部分。「網代」は、網の代わりに木や竹を編んで作った漁具。それを立てる杭が網代木。
千載集の詞書によると、「宇治にまかりてはべりけるときよめる」とある。宇治川の上流、瀬田川が琵琶湖から発する地、瀬田の対岸は膳所(ぜぜ)であり、実際に宇治からは見えないが、川霧が晴れていく空間的な広がりを象徴する地名として意識したかもしれない。また、宇治と瀬田の中間点は石山であり、紫式部は、石山寺で源氏物語の構想を練ったとされ、その宇治十貼に登場する浮舟は宇治川で入水に失敗した後に尼になるという件がある。宇治川を見た定頼が、これらさまざまな背景をもとに、この歌を詠んだ可能性は高く、単純な叙景詩ではない趣を持った作品であると言える。
ごんちゅうなごんさだより (995~1045)
藤原定頼(ふじわらのさだより) 平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。藤原公任の子。容姿端麗で社交的な反面、小式部内侍をからかった時に即興の歌で言い負かされてそそくさと逃げ帰るなど軽率なところがあった。
今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで 言ふよしもがな
今はただ 「今」は、後拾遺集の詞書によると、(伊勢)神宮の斎宮(未婚の皇女。恋愛は厳禁であった)を勤めて帰京された当子内親王のもとに道雅が通っていたことが発覚し、天皇が内親王に監視を付けて逢えないでいる状態。「ただ」は、下に限定の副助詞「ばかり」を伴い、「ただ…だけ」の意。
思ひ絶えなむとばかりを 「思ひ絶ゆ」は、思い切る・あきらめるの意。「な」は、完了の助動詞「ぬ」の未然形で強意を表し、~てしまうの意。「む」は、意志の助動詞。「思ひ絶えなむ」で、思いをあきらめてしまおうの意。「と」は、引用の格助詞。
人づてならで 「で」は、打消の接続助詞で、~ないで・なくての意。「人づてならで」で、人づてではなく、即ち、自ら直接にの意。
言ふよしもがな 「よし」は、方法。「もがな」は、願望の終助詞で、~があればいいなあの意。
さきょうのだいぶみちまさ (993~1054)
藤原道雅 (ふじわらのみちまさ) 平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。藤原伊周の子。関白道隆・儀同三司母の孫。父伊周の失脚に加え、当子内親王との密通事件などの悪行によって、家柄に比べて職位ともに低くとどまった。
今はただ 「今」は、後拾遺集の詞書によると、(伊勢)神宮の斎宮(未婚の皇女。恋愛は厳禁であった)を勤めて帰京された当子内親王のもとに道雅が通っていたことが発覚し、天皇が内親王に監視を付けて逢えないでいる状態。「ただ」は、下に限定の副助詞「ばかり」を伴い、「ただ…だけ」の意。
思ひ絶えなむとばかりを 「思ひ絶ゆ」は、思い切る・あきらめるの意。「な」は、完了の助動詞「ぬ」の未然形で強意を表し、~てしまうの意。「む」は、意志の助動詞。「思ひ絶えなむ」で、思いをあきらめてしまおうの意。「と」は、引用の格助詞。
人づてならで 「で」は、打消の接続助詞で、~ないで・なくての意。「人づてならで」で、人づてではなく、即ち、自ら直接にの意。
言ふよしもがな 「よし」は、方法。「もがな」は、願望の終助詞で、~があればいいなあの意。
さきょうのだいぶみちまさ (993~1054)
藤原道雅 (ふじわらのみちまさ) 平安中期の歌人。中古三十六歌仙の一人。藤原伊周の子。関白道隆・儀同三司母の孫。父伊周の失脚に加え、当子内親王との密通事件などの悪行によって、家柄に比べて職位ともに低くとどまった。
夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも よに逢坂の 関は許さじ
まだ夜の明けないうちに、鶏の鳴き声を真似てだまそうとしても、あの中国の函谷関ならばともかく、あなたと私の間の、男女が逢うという逢坂の関は、絶対に通ることを許しませんよ。
夜をこめて 夜が深いうちに
鳥のそらねははかるとも 「鳥のそらね」は、ニワトリの鳴きまね。「はかる」は、「謀る」で、だます・いつわるの意。斉の孟嘗君が秦から逃げる際、一番鶏が鳴いた後にしか開かない函谷関にさしかかったのが深夜であったため、食客にニワトリの鳴きまねをさせて通過したという故事から。
よに逢坂の関はゆるさじ 「よに」は、決して・絶対にの意を表す呼応の副詞で、下に否定の語を伴う。「逢坂の関」の「あふ」は、「逢ふ」、即ち、逢瀬と「逢(坂)」の掛詞。「逢坂の関」は、山城(京都府)と近江(滋賀県)の境にあった関所。逢坂の関の通過は許さないということと逢うこと、即ち、あなた(藤原行成)と男女の関係を持つことは許さないということを重ねている。
後拾遺集の詞書及び枕草子(第136段『頭の弁の、職にまゐり給ひて…』)によると、清少納言と深夜まで語り合った藤原行成が、翌日に行われる宮中の物忌みを理由に、男女の関係を持つことなく帰ってしまった。翌朝、行成は「鳥の声にもよほされて(せかされて帰った)」と言ってきたので、清少納言は、「鳥とは、函谷関の鶏、即ち、嘘の言い訳でしょうと言い返した。これに対し、行成は、函谷関ではなく、逢坂の関、即ち、あなたとは男と女の関係ですよと反論した。そこで、清少納言は、この歌によって、自分に逢うことは決して許さないという意思を表し、行成をやりこめた。ところが、その後に、行成は、逢坂の関は、誰でも簡単に通れる関ではないか、つまり、清少納言は、どんな男でも相手にしているではないかという内容の歌を詠んだ。
せいしょうなごん (本名・生没年不詳)
平安中期の作家・歌人。清原元輔の娘。深養父の曾孫。中宮定子に仕えた。『枕草子』の作者。和漢の学に通じ、平安時代を代表する女流文学者となった。
まだ夜の明けないうちに、鶏の鳴き声を真似てだまそうとしても、あの中国の函谷関ならばともかく、あなたと私の間の、男女が逢うという逢坂の関は、絶対に通ることを許しませんよ。
夜をこめて 夜が深いうちに
鳥のそらねははかるとも 「鳥のそらね」は、ニワトリの鳴きまね。「はかる」は、「謀る」で、だます・いつわるの意。斉の孟嘗君が秦から逃げる際、一番鶏が鳴いた後にしか開かない函谷関にさしかかったのが深夜であったため、食客にニワトリの鳴きまねをさせて通過したという故事から。
よに逢坂の関はゆるさじ 「よに」は、決して・絶対にの意を表す呼応の副詞で、下に否定の語を伴う。「逢坂の関」の「あふ」は、「逢ふ」、即ち、逢瀬と「逢(坂)」の掛詞。「逢坂の関」は、山城(京都府)と近江(滋賀県)の境にあった関所。逢坂の関の通過は許さないということと逢うこと、即ち、あなた(藤原行成)と男女の関係を持つことは許さないということを重ねている。
後拾遺集の詞書及び枕草子(第136段『頭の弁の、職にまゐり給ひて…』)によると、清少納言と深夜まで語り合った藤原行成が、翌日に行われる宮中の物忌みを理由に、男女の関係を持つことなく帰ってしまった。翌朝、行成は「鳥の声にもよほされて(せかされて帰った)」と言ってきたので、清少納言は、「鳥とは、函谷関の鶏、即ち、嘘の言い訳でしょうと言い返した。これに対し、行成は、函谷関ではなく、逢坂の関、即ち、あなたとは男と女の関係ですよと反論した。そこで、清少納言は、この歌によって、自分に逢うことは決して許さないという意思を表し、行成をやりこめた。ところが、その後に、行成は、逢坂の関は、誰でも簡単に通れる関ではないか、つまり、清少納言は、どんな男でも相手にしているではないかという内容の歌を詠んだ。
せいしょうなごん (本名・生没年不詳)
平安中期の作家・歌人。清原元輔の娘。深養父の曾孫。中宮定子に仕えた。『枕草子』の作者。和漢の学に通じ、平安時代を代表する女流文学者となった。
いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな
昔の奈良の都の八重桜が(献上されてきて)、今日、京都の宮中に一層美しく咲きほこっていることですよ。
いにしへの奈良の都の八重桜 「奈良」は、元明天皇による和銅3年(710)の遷都から約70年間にわたって帝都であった平城京。伊勢大輔は平安中期の歌人であり、当時の人々にとって、既に古都という印象を持たれていた。「八重桜」は、八重咲きの桜で、ソメイヨシノより開花時期が遅い。
けふ九重に 「けふ」は、今日。「いにしへ」との対照。「九重」は、宮中。「八重」との対照。数が多い分、奈良よりも京都で“さらに”美しく咲きほこるさまを強調している。
にほひぬるかな 「にほひ」は、ハ行四段の動詞「にほふ」の連用形で、「美しく咲く」という視覚的な美を表している。「ぬる」は、完了の助動詞「ぬ」の連体形。「かな」は、詠嘆の終助詞。
いせのたいふ (生没年不詳)
平安中期の歌人。伊勢の祭主大中臣輔親(おおなかとみのすけちか)の娘。能宣の孫。高階成順の妻。中宮彰子に仕えた。
昔の奈良の都の八重桜が(献上されてきて)、今日、京都の宮中に一層美しく咲きほこっていることですよ。
いにしへの奈良の都の八重桜 「奈良」は、元明天皇による和銅3年(710)の遷都から約70年間にわたって帝都であった平城京。伊勢大輔は平安中期の歌人であり、当時の人々にとって、既に古都という印象を持たれていた。「八重桜」は、八重咲きの桜で、ソメイヨシノより開花時期が遅い。
けふ九重に 「けふ」は、今日。「いにしへ」との対照。「九重」は、宮中。「八重」との対照。数が多い分、奈良よりも京都で“さらに”美しく咲きほこるさまを強調している。
にほひぬるかな 「にほひ」は、ハ行四段の動詞「にほふ」の連用形で、「美しく咲く」という視覚的な美を表している。「ぬる」は、完了の助動詞「ぬ」の連体形。「かな」は、詠嘆の終助詞。
いせのたいふ (生没年不詳)
平安中期の歌人。伊勢の祭主大中臣輔親(おおなかとみのすけちか)の娘。能宣の孫。高階成順の妻。中宮彰子に仕えた。
41 恋すてふわが名はまだき立ちにけり 人知れずこそ思ひそめしか 壬生忠見
42 契りきなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山波越さじとは 清原元輔
43 逢ひ見てののちの心にくらぶれば 昔はものを思はざりけり 権中納言敦忠
44 逢ふことの絶えてしなくはなかなかに 人をも身をも恨みざらまし 中納言朝忠
45 あはれともいふべき人は思ほえで 身のいたずらになりぬべきかな 謙徳公
46 由良の門を渡る舟人かぢを絶え ゆくへも知らぬ恋のみちかな 曾禰好忠
47 八重むぐら茂れる宿の寂しきに 人こそ見えね秋は来にけり 恵慶法師
48 風をいたみ岩打つ波のおのれのみ くだけてものを思ふころかな 源重之
49 御垣守衛士のたく火の夜は燃え 昼は消えつつものをこそ思へ 大中臣能宣朝臣
50 君がため惜しからざりし命さへ 長くもがなと思ひけるかな 藤原義孝
51 かくとだにえやは伊吹のさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを 藤原実方朝臣
52 明けぬれば暮るるものとは知りながら なほ恨めしき朝ぼらけかな 藤原道信朝臣
53 嘆きつつひとり寝る夜の明くる間は いかに久しきものとかは知る 右大将道綱母
54 忘れじのゆく末まではかたければ 今日を限りの命ともがな 儀同三司母
55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ 大納言公任
56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に いまひとたびの逢ふこともがな 和泉式部
57 めぐり逢ひて見しやそれとも分かぬ間に 雲隠れにし夜半の月かな 紫式部
58 有馬山猪名の篠原風吹けば いでそよ人を忘れやはする 大弐三位
59 やすらはで寝なましものをさ夜更けて かたぶくまでの月を見しかな 赤染衛門
60 大江山いく野の道の遠ければ まだふみも見ず天の橋立 小式部内侍
42 契りきなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山波越さじとは 清原元輔
43 逢ひ見てののちの心にくらぶれば 昔はものを思はざりけり 権中納言敦忠
44 逢ふことの絶えてしなくはなかなかに 人をも身をも恨みざらまし 中納言朝忠
45 あはれともいふべき人は思ほえで 身のいたずらになりぬべきかな 謙徳公
46 由良の門を渡る舟人かぢを絶え ゆくへも知らぬ恋のみちかな 曾禰好忠
47 八重むぐら茂れる宿の寂しきに 人こそ見えね秋は来にけり 恵慶法師
48 風をいたみ岩打つ波のおのれのみ くだけてものを思ふころかな 源重之
49 御垣守衛士のたく火の夜は燃え 昼は消えつつものをこそ思へ 大中臣能宣朝臣
50 君がため惜しからざりし命さへ 長くもがなと思ひけるかな 藤原義孝
51 かくとだにえやは伊吹のさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを 藤原実方朝臣
52 明けぬれば暮るるものとは知りながら なほ恨めしき朝ぼらけかな 藤原道信朝臣
53 嘆きつつひとり寝る夜の明くる間は いかに久しきものとかは知る 右大将道綱母
54 忘れじのゆく末まではかたければ 今日を限りの命ともがな 儀同三司母
55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ 大納言公任
56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に いまひとたびの逢ふこともがな 和泉式部
57 めぐり逢ひて見しやそれとも分かぬ間に 雲隠れにし夜半の月かな 紫式部
58 有馬山猪名の篠原風吹けば いでそよ人を忘れやはする 大弐三位
59 やすらはで寝なましものをさ夜更けて かたぶくまでの月を見しかな 赤染衛門
60 大江山いく野の道の遠ければ まだふみも見ず天の橋立 小式部内侍
大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天の橋立
大江山を越え、生野を通っていく道は、都から遠いので、まだ天の橋立の地は踏んでみたこともありません。それに、そこで暮らす母からの文も見ていません。
大江山 源頼光の鬼退治で有名な大江山は、丹後(京都府北部)の山であるが、この歌に詠まれた大江山は、道順から考察して、丹波(京都府南部)の大枝山を指していると思われる。
いく野 「生野」は、丹波(京都府福知山市)にある地名で、「行く」との掛詞。
道の 「道」は、大江山を越え、いく野を通って行く道。「の」は、主格の格助詞。
遠ければ 「動詞の已然形+接続助詞“ば”」で、順接の確定条件。
まだふみもみず 「ふみ」は、「文」と「踏み」の掛詞。母からの手紙が来ていないことと母のいる天の橋立へは行ったことがないことを表している。すなわち、作品が代作ではないことを主張している。
天の橋立 丹後(京都府宮津市)にある名勝。日本三景の一。「ふみ」と「橋」は縁語。
※ 当時、10代半であった小式部内侍の歌が優れていたため、それらの作品は丹後に赴いていた母の和泉式部による代作ではないかとの噂があった。『金葉集』の詞書に、この歌は、歌合の前に藤原定頼が、「代作を頼むために丹後へ人を遣わされましたか」と小式部内侍をからかったことに対する返答として即興で詠まれたものであると記されている。
こしきぶのないし (?~1025)
平安中期の歌人。橘道貞と和泉式部の娘。年少の頃から歌の才能を現したが、20代で早世。
大江山を越え、生野を通っていく道は、都から遠いので、まだ天の橋立の地は踏んでみたこともありません。それに、そこで暮らす母からの文も見ていません。
大江山 源頼光の鬼退治で有名な大江山は、丹後(京都府北部)の山であるが、この歌に詠まれた大江山は、道順から考察して、丹波(京都府南部)の大枝山を指していると思われる。
いく野 「生野」は、丹波(京都府福知山市)にある地名で、「行く」との掛詞。
道の 「道」は、大江山を越え、いく野を通って行く道。「の」は、主格の格助詞。
遠ければ 「動詞の已然形+接続助詞“ば”」で、順接の確定条件。
まだふみもみず 「ふみ」は、「文」と「踏み」の掛詞。母からの手紙が来ていないことと母のいる天の橋立へは行ったことがないことを表している。すなわち、作品が代作ではないことを主張している。
天の橋立 丹後(京都府宮津市)にある名勝。日本三景の一。「ふみ」と「橋」は縁語。
※ 当時、10代半であった小式部内侍の歌が優れていたため、それらの作品は丹後に赴いていた母の和泉式部による代作ではないかとの噂があった。『金葉集』の詞書に、この歌は、歌合の前に藤原定頼が、「代作を頼むために丹後へ人を遣わされましたか」と小式部内侍をからかったことに対する返答として即興で詠まれたものであると記されている。
こしきぶのないし (?~1025)
平安中期の歌人。橘道貞と和泉式部の娘。年少の頃から歌の才能を現したが、20代で早世。
名作として名高いSFである。
これは映画化すべきだと感じた。
現在の映像技術なら表現できるだろう。
善悪を超越したステージの物語である。
久々に満足できる作品を読んだ。

これは映画化すべきだと感じた。
現在の映像技術なら表現できるだろう。
善悪を超越したステージの物語である。
久々に満足できる作品を読んだ。

やすらはで 寝なましものを さ夜更けて かたぶくまでの 月を見しかな
いらっしゃらないことがはじめからわかっていたなら、ためらわずに寝てしまったでしょうに。今か今かとお待ちするうちに夜も更けてしまい、西に傾くまでの月を見たことですよ。
やすらはで 「やすらは」は、ハ行四段の動詞「やすらふ」の未然形で、ためらう・ぐずぐずするの意。「で」は、打消の接続助詞で、~ないでの意。
寝なましものを 「な」は、完了の助動詞「ぬ」の未然形。「ものを」は、逆接の接続助詞。「寝なましものを」で、もし~であれば、寝てしまったであろうにの意。
さ夜更けて 「さ」は、接頭語。
かたぶくまでの月を見しかな 「かたぶく」は、月が西に傾くことで、夜明けが近付いたさまを表す。「まで」は、限定を表す副助詞。「かな」は、詠嘆の終助詞。
あかぞめえもん (生没年不詳)
平安中期の歌人。赤染時用(ときもち)の娘。実父は、母の前夫平兼盛か。大江匡衡(まさひら)の妻。匡房の曾祖母。中宮彰子に仕えた。『栄花物語』の作者という説も。
いらっしゃらないことがはじめからわかっていたなら、ためらわずに寝てしまったでしょうに。今か今かとお待ちするうちに夜も更けてしまい、西に傾くまでの月を見たことですよ。
やすらはで 「やすらは」は、ハ行四段の動詞「やすらふ」の未然形で、ためらう・ぐずぐずするの意。「で」は、打消の接続助詞で、~ないでの意。
寝なましものを 「な」は、完了の助動詞「ぬ」の未然形。「ものを」は、逆接の接続助詞。「寝なましものを」で、もし~であれば、寝てしまったであろうにの意。
さ夜更けて 「さ」は、接頭語。
かたぶくまでの月を見しかな 「かたぶく」は、月が西に傾くことで、夜明けが近付いたさまを表す。「まで」は、限定を表す副助詞。「かな」は、詠嘆の終助詞。
あかぞめえもん (生没年不詳)
平安中期の歌人。赤染時用(ときもち)の娘。実父は、母の前夫平兼盛か。大江匡衡(まさひら)の妻。匡房の曾祖母。中宮彰子に仕えた。『栄花物語』の作者という説も。