
秋風に たなびく雲の 絶え間より 漏れ出づる月の 影のさやけさ
秋風に吹かれて、たなびいている雲の切れ間から、月の光が漏れ出ている。その光の、なんと明るく、澄み切っていることだろう。
秋風に 「に」は、原因・理由を表す格助詞。
たなびく雲の絶え間より 「たなびく」は、横に長く伸びる。「絶え間」は、切れ間。「より」は、起点を表す格助詞。
もれ出づる月の 字余り。「もれ出づる」は、雲の隙間から、月光がこぼれ出るさまを描写している。「の」は、連体修飾格の格助詞。
影のさやけさ 「影」は、光。この場合は、月光。「の」は連体修飾格の格助詞。「さやけさ」は、ク活用の形容詞「さやけし」+接尾語「さ」で、名詞化したもの。はっきりしていることの意。体言止め。
さきょうのだいぶあきすけ (1090~1155)
藤原顕輔 平安後期の歌人。清輔の父。崇徳院の院宣による勅撰集『詞花和歌集』の撰者。
秋風に吹かれて、たなびいている雲の切れ間から、月の光が漏れ出ている。その光の、なんと明るく、澄み切っていることだろう。
秋風に 「に」は、原因・理由を表す格助詞。
たなびく雲の絶え間より 「たなびく」は、横に長く伸びる。「絶え間」は、切れ間。「より」は、起点を表す格助詞。
もれ出づる月の 字余り。「もれ出づる」は、雲の隙間から、月光がこぼれ出るさまを描写している。「の」は、連体修飾格の格助詞。
影のさやけさ 「影」は、光。この場合は、月光。「の」は連体修飾格の格助詞。「さやけさ」は、ク活用の形容詞「さやけし」+接尾語「さ」で、名詞化したもの。はっきりしていることの意。体言止め。
さきょうのだいぶあきすけ (1090~1155)
藤原顕輔 平安後期の歌人。清輔の父。崇徳院の院宣による勅撰集『詞花和歌集』の撰者。











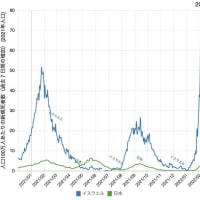
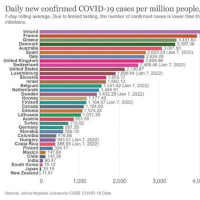
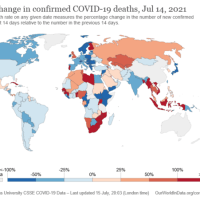
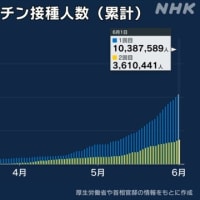
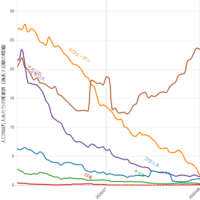
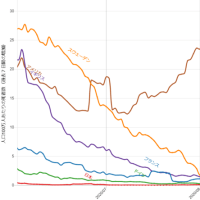
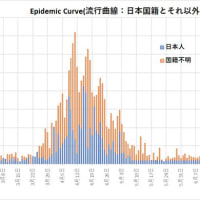
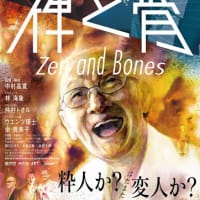







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます