
突如、目の前に現れたジャンボきじ車は、下の道路を走る軽自動車よりも大きいのです。

ジャンボきじ車が設置されている台地は平成21年3月にも「きじ車の里公園」として整備
されていたようです。きじ車の周りと階段の下草もちゃんと刈られて管理されています。

木を組み合わせて作られたきじ車は圧巻です!

きじ車だけだと、大きさが分かりにくいので広報部鳥(身長161.8㎝)を入れて撮影。
その巨大さがお分かりいただけるのでは…。
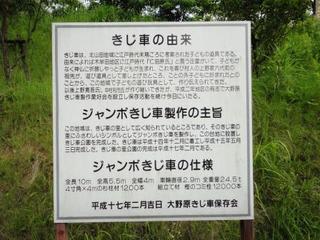
きじ車の近くに掲げられていた看板にはきじ車の由来、ジャンボきじ車製作の趣旨
ジャンボきじ車の仕様について書かれていました。
(きじ車の由来)
きじ車は、北山田地域に江戸時代末期ごろに考案された子どもの道具である。
由来によれば木牟田地区に江戸時代「仁田原氏」と言う庄屋がいて、子どもが
なく神仏に祈願しやっと子どもが生まれ、これを喜び村人の上野家六代前の
祖先が、遊び道具として差し上げたところ、この外子どもに好まれたとの
ことから、この地域で子どもの遊び道具として、作り伝えられてきた。
以後上野寛吾氏、中村利市氏が作り継いできたが、平成二年地区の有志で大野原
きじ車製作愛好会を設立し保存活動を続け今日にいたる。
(ジャンボきじ車製作の主旨)
この地域は、きじ車の里として広く知られているところであり、そのきじ車の
里にふさわしいシンボルとしてジャンボきじ車を製作し、この台地に設置し
きじ車公園を完成した。きじ車は平成十四年十二月に着工し平成十五年五月
三日完成した。きじ車の里公園の完成は平成十七年二月である。
(ジャンボきじ車の仕様)
全長10m 全高5.5m 車輪直径2.9m 全重量24.5t
4寸角×4mの杉柱材 1200本
組立て材 樫のコミ栓 12000本
平成17年2月吉日 大野原きじ車保存会

ジャンボきじ車に遭遇するまで、集落を抜けてきた一本道。
周囲は青々とした田んぼが広がり、公園下の左側にきじ車の加工所がありました。
つづく…































