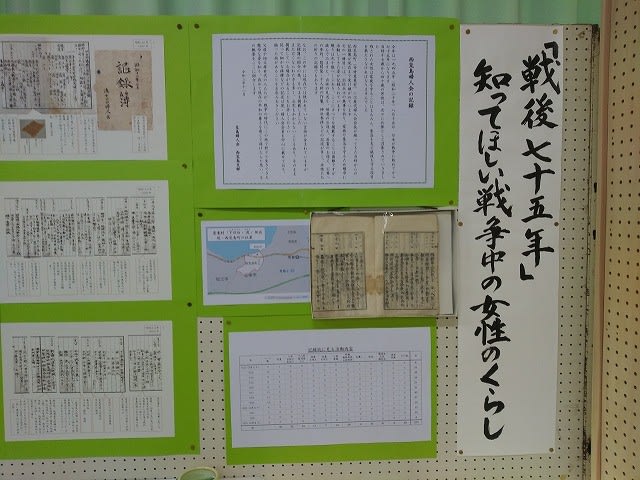夫は「お前が戦争中に生きていたら、皆さんこうしなければなりません、
などとドラマに出てくる戦争中の割烹前掛けのおばさんになっていただろう」と言います。
私は夫に言います。「じゃーあなたは、召集令状が来たら、
自分は戦争反対だから、召集には応じられません、と拒否できるの」
高校の倫理社会で独裁政権は「軍隊・教育・マスコミ」で成立する、と習いました。
今はインターネットが発展してきたから、マスコミは「情報」と表すのでしょうか。
戦争のドラマになると、決まって割烹前掛けのおばさんが出てきて、
陰でそれを非難している人が、いかにも正義のように扱われますが、
それは今の時代だから正義のように見えるだけであって、
当時は違っていたのではないか、と思う今日この頃です。
などとドラマに出てくる戦争中の割烹前掛けのおばさんになっていただろう」と言います。
私は夫に言います。「じゃーあなたは、召集令状が来たら、
自分は戦争反対だから、召集には応じられません、と拒否できるの」
高校の倫理社会で独裁政権は「軍隊・教育・マスコミ」で成立する、と習いました。
今はインターネットが発展してきたから、マスコミは「情報」と表すのでしょうか。
戦争のドラマになると、決まって割烹前掛けのおばさんが出てきて、
陰でそれを非難している人が、いかにも正義のように扱われますが、
それは今の時代だから正義のように見えるだけであって、
当時は違っていたのではないか、と思う今日この頃です。