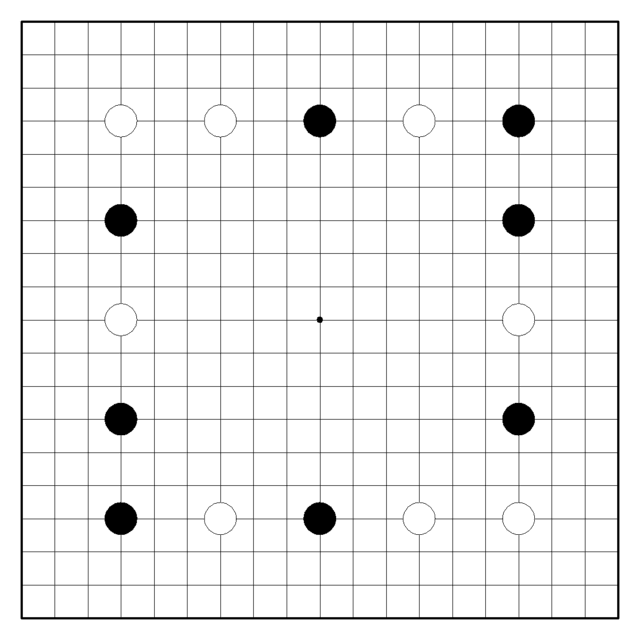≪田中阿里子『源氏物語の舞台』を読んで≫
(2024年4月14日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、紫式部と『源氏物語』について考える上で、次の著作を読んでみたので、紹介してみたい。
〇田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年
「『源氏物語』の舞台になった場所をたずねて、京の町のところどころを歩こうというのが、この本の試みである」と「初刊本まえがき」(5頁)に記してあることからもわかるように、『源氏物語』の舞台となっている場所を訪れて、解説を加えている本である。章立てからも推察できるように、光源氏、薫の生涯にそって、述べている。
『源氏物語』の登場人物の中で、六条御息所、薫について、著者の深い洞察が加えられている点、紫式部の生きた時代の社会的背景などにも考察が及んでいる点など、教えられるところがあった。
【田中阿里子『源氏物語の舞台』(徳間文庫)はこちらから】
田中阿里子『源氏物語の舞台』(徳間文庫)
〇田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年
【目次】
初刊本まえがき
第一章(光源氏の誕生~十七歳)
第二章(光源氏十八歳~二十歳)
第三章(光源氏二十一歳~二十五歳)
第四章(光源氏二十六歳~三十五歳)
第五章(光源氏三十六歳~三十八歳)
第六章(光源氏三十九歳~四十七歳)
第七章(光源氏四十八歳~死)
第八章(薫君十四歳~十九歳)
第九章(薫君二十歳~二十八歳迄、源氏存命ならば七十五歳で終る)
第十章――『紫式部日記』より――
解説 百瀬明治
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
■六条御息所(第三章より)について
■加持祈禱
■貴族間の対立(『源氏物語』のもう一つの側面)~第五章より
■王朝の文化人
■『栄華物語』について
■三千院
■人々の死
■墓所と葬場
■宇治陵
■物語後半の主題(第八章より)
■薫の思想(第九章より)
■宇治十帖の社会的背景
〇第十章―『紫式部日記』より
■紫式部の略歴について
■日記
■邸宅の跡(廬山寺)
六条御息所について
「第三章(光源氏二十一歳~二十五歳)」の冒頭において、「葵」の巻の「物語の梗概」について、百瀬明治氏の文章(『日本古典文学大系』岩波書店刊行)を引用して、次のような梗概を載せている。(なお、百瀬明治氏は本書の解説[215頁~219頁]の執筆者でもある)
【葵】
・源氏の父桐壺帝が退位し、春宮(とうぐう)が即位して朱雀(すざく)帝となった。
これにともない、新たに春宮に選ばれたのは、源氏と藤壺の間の不義の子であった。
源氏は、新春宮の後見役に任じられた。
・しかし、この頃から、源氏の周囲の情勢は、ようやく厳しくなってくる。
朱雀帝の生母弘徽殿(こきでん)皇太后とその実家右大臣の一派が、政治の実権を掌握し、源氏と左大臣系の勢力は退潮の兆をみせはじめる。
・ところで、当時は、天皇が即位するたびに、伊勢の斎宮、賀茂の斎院も新任されるのが習わしであった。選任される資格は、未婚の王女、内親王であることで、このたびは、源氏の最初の愛人六条御息所の娘が斎宮に、弘徽殿の女三宮(おんなさんのみや)が斎院にそれぞれ選ばれた。
・賀茂の斎院の御禊(みそぎ)が行われた日のことである。
葵上は妊娠中で気分がすぐれなかったが、源氏が斎院の御ともにまいることでもあり、母の宮のすすめもあったので、急に外出の仕度をととのえた。折りから一条通りは、御禊行列を一目見んとする人々で雑踏をきわめていた。
遅れてきた葵上一行は、車をとどめる場を見出せず、従者が強引に割りこもうとして、その人と知りながら、六条御息所の網代(あじろ)車を押しのけてしまった。
ほどなくこの事件を知った源氏は、貴女としての条件は十分備えているのに、どうして情味だけが欠けているのだろうと、葵上の行為を苦々しく思う。
しかし、この事件は、思いがけぬ結果を後にひき起こすことになる。
※『源氏物語』において、六条御息所は、強烈な嫉妬心と自恃(じじ)の持主として描かれている。
彼女は大臣家に生れ、故先坊(桐壺帝の弟)の妃でもあった。
出身と経歴に関しては、葵上に少しも遜色ない。しかも、彼女は源氏の最初の愛人なのである。
これまでに積りつもった恨みが、屈辱的な車争いの一件によって爆発したのだろう。彼女の魂は物怪(もののけ)となって、葵上に取り憑いた。
・葵上は、危篤状態に陥る。
左大臣家では、叡山の座主をはじめ高僧を多く招いて、祈禱を行わせた。
そんなある夜、葵上の姿は急に六条御息所に変じて、涙ながらにつれない仕打ちの続いたことを、源氏になじるのであった。夕顔をとり殺した怨霊も彼女であったことがこの時判明した。
・僧達の祈りがきいたのか、やがて物怪は去り、葵上は美しい男児(のちの夕霧)を無事出産した。けれども結局、葵上自身は生きながらえることができなかった。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、47頁~48頁)
・作者の田中阿里子氏は、六条御息所に深い関心をよせている。
次の点に注意している。
・源氏の最初の愛人であること
・年上の既婚女性であること
・高貴な身分で教養の高い女人であること
・そのほかに、深い情念を湛(たた)えていること
※葵上にしても紫上にしても、あるいは夕顔、花散里、朧月夜君にしても、それぞれに特徴のある美しさと可憐さを備え、源氏との出逢い方も色々に工夫があって面白い。
しかし、六条御息所ほどに強い個性を作者からあたえられたものはなく、生霊となってまでも、主人公とその女達の上につきまとう怨念の強さは、作者紫式部が無意識に仮託した、自己の情念そのものである、と田中阿里子氏はみている。
※この時代では、まだ霊の存在が固く信じられ、恨みをのんで死んだ人の魂が、生きている人間に祟って病を起すところから、霊は仏の力によって退散せしめられたり、あるいは神として祀られた。
※神話においる素盞嗚命(すさのおみこと)は天照大神によって追放された荒神だが、牛頭天王(ごずてんのう)といって祇園社をはじめ方々に祀られている。
今宮(いまみや)神社にもこれを祀った宮があるが、もともと今宮神社は、民衆が悪鬼をはらうためにまつった社で、一条天皇の時にも天下に疫病が流行したために、この地で疫神をまつって、大いに御霊会(ごりょうえ)をいとなまれた。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、53頁~54頁)
■加持祈禱について
・密教では、護摩をたいて、怨霊退散の祈り、加持祈禱を行った。
物怪に対しては、これを「よりましの巫女(みこ)」にのりうつらせて、病者から離し、その後呪文によって調伏した。
「葵」の巻にも、
「……いとゞしき御祈りの、数をつくしてせさせ給へれど、例の執念(しゅうね)き御物の怪(け)一つ、さらに動かず、……加持の僧ども、声しづめて法花経をよみたる。いみじう、尊し」
とある。
また、『紫式部日記』の中でも、中宮彰子(しょうし)の土御門殿(つちみかどでん)における御産の時には、
「日ごろ、そこらさぶらひつる殿のうちの僧をばさらにもいはず、山々寺々を尋ねて、験者といふかぎりは残るなくまゐりつどひ、三世の仏も、いかに聞き給ふらむと思ひやらる。陰陽師とて、世にあるかぎり召し集めて、八百万(やおよろず)の神も耳ふりたてぬはあらじと見えきこゆ」
と描写している。
※六条御息所の怨念が、いかに物語の中に効果的に使われていることか。
葵上をとり殺した怨霊は、この後も紫上にとりついて彼女を気絶させ、そして源氏が紫上につきそって看護している暇に、正夫人の女三宮が他の男性と姦通して妊娠するという事件を起すが、それもみな自分を愛さなかった源氏への仕返しだと、御息所の霊が嘲笑する。
この物怪によって、光りかがやく源氏の物語には深い影が添うこととなる。
そこに、田中阿里子氏は文学性が高まっているとみる。
そして一方には、当時の貴族達の一夫多妻生活の中で、愛し、憎み、哀しみ苦しんだ女性達の真実の声を、御息所一人にしぼって、作者が代表させたのではないか、と考えている。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、55頁~56頁)
■貴族間の対立(『源氏物語』のもう一つの側面)~第五章より
・玉鬘が発見されて、源氏に養われ、さらに本当の父親と対面してから結婚にいたるまでの章ほど、華やかでダイナミックな趣きをそえるものはない。
実は『源氏物語』は、光君(ひかるのきみ)の様々な恋愛遍歴の話にみえながら、その底にきびしい政治権力の対立を描き切っているのである。
その筋書を追って行くと、桐壺院の御代では、左大臣系と右大臣系の対立がある上へ、光君という皇子(みこ)が源氏としてあらわれる。
王氏の源氏は左大臣系の方と結ぶが、やがて朱雀帝の御代になって右大臣系の方が台頭し、源氏は左遷される。しかし冷泉帝の御代に及んで再び源氏と左大臣系が復活してくるという順序である。
とは言いながら、左大臣家の長男も、王氏の源氏とは若い時からのよきライバルで、ことごとに競争があった。
たとえば、梅壺と弘徽殿女御のいどみ合い、あるいは夕霧と雲井雁の結婚問題についてのもつれ等だが、夕顔の遺児玉鬘をめぐっても、源氏は相手に優越しようとし、ついに成功するのである。
そして最後に彼が六条院として上皇に準ずる位に上ると、圧倒的な王氏の勝利で、右大臣側の太后(おおきさき)も、左大臣側の長者も今さらに源氏の運命が、他に異っていたことを納得する。
・しかし式部がこういう経過を書き上げたについては、心中に複雑なものがあっただろうと、著者は推測している。
藤原氏というのは同じ一族の間でも栄達の争いが激しかったから、式部は自らも藤原氏の一員でありながら、中心の摂関家に対する不満を抱いていたに違いないし、また摂関家の権力によって圧迫される、王氏の子孫達に対しては同情や、かくあれかしという希望があって、源氏を理想の人物に描いたという。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、102頁~104頁)
■王朝の文化人
・紫式部たちの生きた時代は、中国の文化はずい分日本化されてきている時代だが、貴族の生活も公的には中国風、私的には敷島の大和心を尊ぶ風が強くなっている。
たとえば、村上天皇の御世の天徳4年には、清涼殿に於て女房歌合せが行われ、それは男性の詩合せに対抗して、大流行の先がけをつくった。
だから『源氏物語』の中にも、「絵合」で女性が二派にわかれて争うというような風俗が描かれたのであろう。
・中国風から日本風への、文化の変り目の一つに書道がある。
「梅枝」の巻でも、源氏が書について批評しているが、「近頃の源氏は書道といっても、仮名の方を重んじて、世の中に上手とよばれる人があれば、身分をとわずに書かせている」のであった。
・一条帝の時代には才人が多くて、書道の方にも人があったが、中でも藤原行成(ゆきなり)は漢字、かなともにうまく、小野道風、藤原佐理(すけたか)とともに三蹟とうたわれた。
しかし行成が才人だといっても、この時代には各方面にすぐれた人材がそろっていて、例をあげれば次のようになる。
一、政治
藤原道長、伊周(これちか)、実資(さねすけ)、斉信(ただのぶ)、
公任(きんとう)、行成、源俊賢(としかた)、頼定、相方
二、漢詩文
大江匡衡(まさひら)、以言(よしとき)
三、和歌
藤原実方(さねかた)、和泉式部、赤染衛門
四、管弦
源道方、済政(なりまさ)
五、絵画
巨勢(こせ)弘高
六、儒学
清原善澄、広澄
七、仏教
源信、覚運、院源、寛朝、慶円
八、陰陽道
安倍晴明
九、武士
下野公時(しもつけきんとき)、尾張兼時、源頼光、源満仲、平維衡(これひら)
このように多士済々である。
そして、これらの人々の中心に、道長が居たのであるが、その才略にとんだ道長の様子が、六条院における源氏の描写にモデルとして使用されているらしいという。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、124頁~126頁)
【私の追記メモ】 大河ドラマ「光る君へ」のキャストを参考までに列記しておく。
・藤原道長(柄本佑)
・紫式部(まひろ)(吉高由里子)
・道長の妻の源倫子(黒木華)
・道長の長女の彰子(見上愛)
・道長の子の頼通(渡邊圭祐)
・紫式部の父(岸谷五朗)
・紫式部の弟の惟規(高杉真宙)
・紫式部の夫(佐々木蔵之介)
・藤原兼家(段田安則)
・藤原道隆(井浦新)
・詮子(吉田羊)
・道隆の長女:定子(高畑充希)
・定子の兄:伊周(三浦翔平)
・清少納言(ファーストサマーウイカ)
・一条天皇(塩野瑛久)
・源高明の娘:源明子(瀧内公美)
・藤原実資(秋山竜次)
・藤原斉信(金田哲)
・藤原公任(町田啓太)
・藤原行成(渡辺大知)
・赤染衛門(凰稀かなめ)
・安倍晴明(ユースケ・サンタマリア)
■『栄華物語』 について
・さて『源氏物語』「若菜」からは、源氏夫妻の運命の凋落がはじまる。
まず紫上が、朱雀院の女三宮に、正夫人の地位をおびやかされる立場になって、ついに病気にかかる。源氏の方は、女三宮の姦通によって、コキュの憂目を味わうという、二人の悲運が、表面上は源氏の四十賀と朱雀院の五十賀という華やかな催しの裏側に進行するのである。
この四十賀の儀式のモデルを、『栄華物語』 の中から著者は拾っている。
・『栄華物語』 の巻第三に、摂政兼家の六十の賀が、東三条の院で行われた記述がある。
永祚2年10月のことで、一条天皇の行幸もあった。
また、巻第七には、東三条院詮子の四十の賀をくわしくのべている。
長保3年のことだが、この年は疫病が流行したり、女院(にょういん)が法華八講会を催されたり、石山詣(もうで)があったりして賀宴が遅れ、10月になった。
土御門殿で行われ、この時も行幸があった。
屏風の歌は上手な歌人達が仕ったが、絵の方は八月十五夜に男女の語らう姿であった。
賀宴の舞人は北家の子息達がつとめたが、ことに道長の息、頼通と頼宗の二人の少年の舞が美しかった。
この時、中宮彰子は西の対屋、女院は寝殿なので、一条天皇もその東廂におられ、道長夫人は東の対屋にいて、公卿は渡殿にいた。
・『栄華物語』の筆者については色んな説があり、何人かの複数の筆者の名前もあがっている。
しかし少なくとも巻三十までの正編については、赤染衛門が最も有力な候補とされる。
彼女は道長の妻の倫子(りんし)に仕えていたから、彰子つきの紫式部とは関わりも深く、親交があったらしい。
式部は赤染衛門のことを、「ことにやむごとなきほどならねど、まことにゆゑゆゑしく、歌よみとて、よろづのことにつけてよみちらさねど、聞えたるかぎりは、はかなきをりふしのことも、それこそ恥づかしき口つきに侍れ」と、好感をもって書いている。
・なおこの第六章の明石姫入内の参考として、『栄華物語』の中から、彰子入内の部分をひいている。
「大殿の姫君十二にならせ給へば、年の内に御裳着ありて、やがて内に参らせ給はんと急がせ給ふ。(下略)」
巻第六の、「かゞやく藤壺」から引用したが、明石姫も同じように未来のお后候補として入内し、そして、源氏四十の賀のあとに皇子を出産する。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、128頁~130頁)
■三千院
・大原の里は桜の花にもよし、緑の雨によし、秋の紅葉に、雪景色にと、昔も今も環境のよいところだが、ことに三千院は品格の高い、よい寺である。
はじめ、伝教大師が比叡山に根本中堂を営んだ時、東塔の南谷に建てた寺が起りといわれるが、後に堀河天皇の皇子が入室されてからは、代々の門跡寺院となった。
・なお、三千院の境内東南部にある往生極楽院は、三間四面、単層、入母屋造り、こけら葺のささやかな建物であるが、内部は藤原時代の阿弥陀堂の様式をとどめ、優雅で美しい。
安置した阿弥陀三尊も、来迎の弥陀の姿を表わしたもので、これは王朝の人達が憧れた未来の相だったらしい。
道長も頼通もこれに似た阿弥陀堂をつくっているが、この世で栄華をきわめた人達が、死だけはまぬがれることが出来ず、最後に如来に願ったのである。
光源氏も女三宮に背かれ、紫上に先だたれてからは、浮沈の多い一生を振り返って、念仏三昧に暮した筈である。
だがその子の夕霧はあくまでも落葉宮をもとめて、大原の山荘から奪うようにして、一条の宮へと移した。
結局、親の犯した過失を同じように繰り返していくのが、人間というものなのか。
そして更に女三宮の過失からは薫君が生れ、表向きは夕霧の弟として、宇治十帖の主人公となるのである。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、144頁~146頁)
■人々の死
・第七章(光源氏四十八歳~死)に於ては、三つの大きな死がある。
柏木と紫上、源氏である。
紫上は先の「若菜下」の巻で、六条御息所の物怪につかれ、危く命を落しそうになった。
蘇生してからも病気がちであった。あくまでも執拗な御息所の怨霊は、「中宮の御事を世話して下さるのはありがたく、あの世からみていますが、生を隔てると、子の愛というのを以前ほど深く感じないのか、あなたへの恨みだけが執着するのです。その恨みの中にも、生前にあなたが私を軽んじられたことよりも、紫上との語らいの中で、私を悪くいわれたことが、口惜しく思われます……」と気味の悪いことを言う。
また中宮への伝言として、「他の女性と帝寵をきそい合うというようなことはするな」といましめたりする。
・こんな噂が自然とひとに洩れるところとなって、紫上はいよいよ出家を希望し、秋好中宮さえも母の菩提を弔うために、尼になりたいと洩らすのだが、源氏が許さないうちに、紫上ははかなくなるのだった。
さすがに源氏その人は「神」のような存在であるから、怨霊のつきようもなく、またその死については一言も語っていない。
しかし源氏周辺の人物の不幸を必ず怨霊のたたりとし、いかに善根を積もうとそのたたりからのがれられぬ筋書を作っている処に、作者のみでなく当時の人々の、ぬきがたい宿命観をのぞきみるのである。
革命というものがなく、すでに階級の固定してしまった貴族社会では、より出世するためにはその娘を天皇に奉って、皇子の出生を待つばかりだった、そういうシステムが、宿命観をより深くさせたのであろう、と著者はみる。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、145頁~147頁)
■墓所と葬場
・柏木を何処に葬ったかという記述はなく、ただ夕霧が「右将軍が塚に、草初めて青し」と口ずさむのみである。
しかし右将軍というのは当時、承平6年(936年)7月に死んだ右大将軍藤原保忠(やすただ)のことで、保忠は藤原氏の一族として、木幡(こばた)墓所に葬られた筈だから、柏木の墓も木幡と考えてよいだろう。
・紫上の方は、「はるばると広き野の、……」とあり、それは鳥辺野(とりべの)の中の、愛宕(おたぎ)の火葬場であり、墓地のことは書いていない。
・ここで振り返ってみると、桐壺の更衣も愛宕で火葬にしたとあり、夕顔、葵上の葬送も同じである。
・しかし桐壺院は、「須磨」の巻に、「御墓は、道の草しげくなりてわけ入り給ふ程、いとゞ露けきに、月の雲にかくれて、森の木立こぶかく心すごし」と御陵のことを描写していて、おそらくは作者は北山あたりに御陵の位置を想定していたとする。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、147頁~148頁)
■宇治陵
・藤原氏一門の骨を埋めた宇治陵は、古くは木幡墓所といったが、現在の地名でいうと、宇治市木幡南山畑町、木幡山の南麓にひろがる相当広い地域である。
次々にその上に家が建って、新しい道が出来、どれが誰の墓所ともはっきりわからない。
しかし木幡駅からさらに府道にそって南へいくと、宇治陵総拝所があって、そこにはちゃんと十七陵三墓に納めた方々の名が書いてある。
宇多帝中宮温子(おんし)
醍醐帝中宮穏子(おんし)
村上帝中宮安子
冷泉帝女御懐子(かいし)
冷泉帝女御超子
円融帝皇后遵子(じゅんし)
円融帝中宮媓子(こうし)
円融帝女御詮子(せんし)
一条帝中宮彰子(しょうし)
三条帝中宮妍子(けんし)
三条帝皇后娍子(じょうし)
後一条帝皇后威子(いし)
・文学史にも有名な方々の名前が並んでいて、圧倒される気分である。
そのほか左側の立札には、藤原冬嗣、基経、時平、道長、頼通など、摂関家の人達の錚々たる名も並んでいるが、この方はどの塚が誰のものかはっきりわからないらしい。
さすがに道長といえども、中宮や女御への扱いには劣るというわけであろうか、と著者は記す。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、152頁)
■物語後半の主題(第八章より)
・「匂宮」の巻の冒頭に、いかに作者は次の物語の中心人物たる薫君の個性について、慎重な用意のある文章をかいていることか。
「をさなき心地に、ほの聞き給ひし事の、折々いぶかしう、おぼつかなく、思ひわたれど、問うべき人もなし」と、薫が幼い時から自分の出生について疑問を抱いていることを述べ、
おぼつかな誰に問はましいかにして始めも果ても知らぬわが身ぞ
と独りで愚痴をいうが、答えるべき人もなかったと書いている。
・この、「おぼつかな」の歌は勿論紫式部の作ったものであるが、作者は薫の口をかりて、無意識に物語の後半部の主題を語っている、と著者はみる。
薫はいうまでもなく、女三宮の不義姦通によって生れた子で、人生観は暗いが、それに托して語っている作者の人生観も暗くなっている。
とてもあの、光り輝く生命の象徴であった、前半の主人公を描いた作者と、同じ人物とは思えぬ程である。
しかし式部は、物語を書きはじめてからすでに何年かを経て、女房生活の裏表を体験し、人生の悲惨も味わっているうちに、心境が変化したのであろうという。
文学観も深く沈潜してきた筈である。
そう思うと、「始めも果ても知らぬわが身ぞ」という言葉には、作者の痛切な無常感(ママ)がこめられて、いよいよ身につまされる感じがしてくる。
・とは言いながら作者はこの薫に、源氏とは違った意味でのすぐれた個性をあたえている。
それは美しい香りである。
原文をひくと、
「香のかうばしさぞ、この世の匂ひならず、あやしきまで、うちふるまひ給へるあたり、遠く隔たる程の追風も、まことに、百歩のほかも、薫りぬべき心地しける」とある。
なお、薫について、「これほどの身分の人が風采をかまわずにありのままで人中へ出るわけはなく、すこしでも人よりすぐれた印象を与えたいという用意をするはずであるが、怪しいほど放散する匂いに、忍び歩きをするのも不自由なのをうるさがって、あまり薫物などは用いない。それでもこの人の家にしまわれた香が、異ったよい匂いを放つものになり、庭の花の木もこの人の袖がふれるために、春雨の日の枝のしずくも、身にしむ香を漂わすことになった。秋の野の藤袴は、この人が通ればもとの香が隠れてなつかしい香に変るのだった。……」と語っている。
・ついでに、
「兵部卿の宮は、薫がこんなに不思議な香の持主である点を、羨ましく思って、競争心をおもやしになるのだった。宮のは人工的にすぐれた香を、お召し物へたきしめることを朝夕の仕事に遊ばし、自邸の庭にも春の花は梅を主にして、秋は人の愛する女郎花、萩の花などは顧みられることなく、不老の菊、衰えていく藤袴、見ばえのせぬ吾木香(われもこう)などいう、匂いの立つ植物を、霜枯れのころまでもお愛しになるような風流ぶりであった。……」と、
薫の模倣者までが現われているのである。
・薫がどのような特異体質をもっていたにしても、科学的には一寸納得のいかぬ話で、そのくせ作者の唯美的な文章には、後世の読者を酔わせる何かがあるのである。
あるいはそれが、王朝人独得の文学的感性的な現実認識の仕方だといえるかも知れない。
・それにしても、光君と薫君という、この二つの名前だけを取り上げてみても、ここには如何にも日本的伝統的な美学がある。
古来から、暗いもの、臭いものはけがれとして忌み嫌った日本人の好みに、源氏はよく合っている。そこにこそ『源氏物語』が千年の生命を保ってきた秘密の一端があるとみる。
臭いものを臭いと書いただけでは、言葉の芸術は成り立たないのである。
紫式部の芸術は、この世に浄土の芳香を漂わす男をさえ創ったという。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、163頁~166頁)
■薫の思想(第九章より)
・宇治十帖は、都を離れて素朴な、しかも趣きに富んだ土地に繰りひろげられる、ささやかな人間関係のなりゆきを描いたものである。
それだけに、前編にくらべて、心理の掘り下げが深く、作者の眼も情感も沈潜していて、文学性はより高いといわれる。
・「橋姫」の巻に、薫のことを八宮がひとづてにきいて、次のように話している。
「人生をかりそめのものと悟り、厭世心の起りはじめるのも、その人自身に不幸のあった時とか、社会から冷たくされた時とか、何かの動機によることですが、年が若くて、しかも思うことが何でもかなう身の上で、何の不満もなさそうな人が、そんなに後世のことを頭において仏教を学ぼうとされるのは、珍しいことですね」
・宇治十帖に漂っている仏教的な宿命観やペシミズムは、この時代のものである。
式部の時代からもう少し下ると、世の中は末法思想という暗いものにおおわれてしまうが、それへのはじまりがすでにここでは現われて、薫の出生そのものが、ぬきさしならぬ人間の運命の暗さを象徴しているかにみえる。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、177頁~178頁)
■宇治十帖の社会的背景
・末法思想というのは、釈迦が入滅後の世界を、正法、像法、末法の三つに分け、
末法の世に入ると仏の教えは衰えて、人々の心は悪化し、世の中には悪のみがはびこるという、悲観的な考えである。
その期間については色んな説がある。
当時は正法千年、像法二千年と信じられていた。
また釈迦入滅の年というのも、それを何時に考えるかによって、末法期の始まりが違ってくるが、式部が宇治十帖を書いたのが1010年頃とすると、残る時間はもう五十年にも足りなかった。
だから、人々はまるで、最後の審判の日が近づいたように怖れ、道長でさえもひたすらに後生を祈って、法成寺の造営を急がせたのだった。
・しかし、こうした思想が流布する裏には、必ず社会的な要因がある。
式部が十歳になった980年頃から1010年までの社会を、著者は調べている。
980年7月 暴風雨あり
同年 11月 内裏焼失
982年2月 伊予国海賊あり、京中群盗
同年 11月 内裏焼失
983年 此年京中で武器所有を禁ず
984年8月 円融天皇譲位
986年6月 花山天皇退位
987年夏 旱害あり
989年7月 彗星出現
同年 8月 暴風雨。高潮あり
992年5・6月 京中洪水あり
993年秋 疱瘡流行
997年9月 高麗の賊来る。南蛮人壱岐、対馬に乱入
998年1月 彗星現わる
同年 8月 暴風雨 此年疱瘡流行
999年6月 内裏焼失
1000年2月 疫病流行
1001年11月 内裏焼失、疫病前年に続く
1004年 此頃地方よりの訴えしきりなり
1005年11月 内裏焼失
1006年10月 南院焼失
1007年5月 流星異変により大赦
1008年2月 花山院崩御
同年 12月 宮中で引きはぎあり
1009年2月 中宮若宮呪咀事件発覚
同年 10月 一条院内裏焼失
1011年6月 一条天皇崩御 冷泉院崩御
1012年6月 道長呪咀 怪事多し
1013年1月 東三条院焼失
1014年2月 内裏焼失
・悪い事件ばかりを拾ってみたそうだ。
朝廷で言うと、摂関家の横暴によって、天皇は次々と退位を迫られたり、出家したりしている。
ことに冷泉天皇は神経症だったというが、そんな朝廷に支配されている社会は、表面の華美に反して、実質は病的であり、退廃をはじめていたといえよう。
宮廷生活の豪華さも、実は地方から取り立てた税によって、消費生活がまかなわれていたのであり、その税を有効に活用して地方民のために産業を興すということは全くなかった。
中央及びそれに連なる地方の国司などが、専ら私腹を肥やしていた。
・次に一条朝は、火事が多い。
『源氏物語』では、「橋姫」の巻に八宮が、京の邸宅を火事で焼かれて後に、宇治山荘に移ったとしてあり、これ以外は火事の記述はないのであるが、実際には式部は多くの火事を見聞した筈である。
しかも彼女が宮仕えをはじめた時には、すでに本当の内裏は焼けていて、彼女の経験したのは主に一条院と枇杷殿などの、里内裏での生活なのだ。
これを考えてもやはり、『源氏物語』の前半部は、彼女の体験から出たというより、理想を求めて描いたという方が当たっているだろう。
あるいは醍醐・村上朝あたりへの憧れがあったのかも知れぬ。
しかし、宇治十帖はたとい一行でも火事を書き、あるいは浮舟の養父一家の地方官的な粗雑な人間達、山荘警備の武士や身分の低い者の描写を多く入れているだけでも、作者の眼が広い現実にふれ、成長してきた証拠だと、著者が考えている。
・ともかく内裏の火災は、この時代の社会不安を実によく象徴していた。
平安京が出来てから、内裏が火災で焼亡したのは、976年の、式部7歳の時がはじめてであったが、それ以後、前の表には7回の火災がある。
さぞかし一条天皇も嫌な気分になられたであろう。
宮廷を警護する人間の気持が余程ゆるんでいたか、または放火とすれば、狂気に近い程の恨みを心に持った人間が徘徊していたのであろう。
・次に疫病の流行だが、それがいかにひどかったかは、一条天皇の勅命で今宮神社を祀り、人々が疫病退散の踊りをしたことでもわかる。
疫病流行のたびに賀茂の流れは死骸であふれたというから、まるで戦争中の爆撃をうけた時に似た状態であった。
・身にかかる不幸を払いのける手段としての政治改革や、科学的対策はなかった時代だから、
人々はこれを宿命としておののき、迷信や占いに走った。
前の記録の中にも彗星出現の記事が幾つかあるが、そうした自然現象は恐怖の的になった。
天変地異があったり、病気が流行したりすると、それは天皇の進退にまで影響をあたえた。
・末法思想の徹底はもう少し時代が後だが、式部の頃には極楽浄土への信仰が盛んで、985年には恵心僧都源信の著した、『往生要集』が世に出ている。
『往生要集』とは、一切経の中から極楽往生に関係した文章を選んで体系化したものである。
これ以後に生れた浄土宗や真宗は、みなこの本を縁に起ったのだが、源信は比叡山の横川に住んだ人だから、この宇治十帖にもおそらくその影響をあたえたのであろう。
(ほかにも横川に住んだ僧はあった。元三大師良源や、賀茂氏出身の慶滋保胤(よししげやすたね)などである)
「手習」の巻では、横川の僧都のことを、「貴族からの招きがあってもことわって、山ごもりをしている聖」としているが、恵心僧都などもそういうタイプの僧だったようである。
・式部自身は、天台宗の教養を学んだとかいう話だが、個人の力ではどうにもならぬ権力機構への反発から、かえって積極的に仏教を支持し、宇治十帖の基礎に据えたということは出来るだろう。
・しかも主人公の薫は、解脱を願いながらもなお、現世への執着が絶てない青年貴族なのである。女性への愛着と悟りの間にあって、彼はつねに迷い続けた。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、178頁~183頁)
第十章―『紫式部日記』より
■紫式部の略歴について
・紫式部の作品は、『源氏物語』及び『紫式部日記』、『紫式部歌集』とはっきりしているが、その履歴についてははっきりしない。
色々にいわれているが、学者によってまちまちである。
・しかし、『紫式部日記』のはじめの方に書かれた、寛弘2年(1005年)12月29日の、初出仕の年齢が、夫の没後数年を経ているとみて、(未亡人になったのは30歳位)35、6歳とすれば、その出生は天禄元年(970年)頃となる。著者は今井源衛氏の説により、出仕の年齢を一応、数え年36歳と仮定して、文章を進めている。
・式部の父は藤原為時(ためとき)、母は藤原為信の女(むすめ)で、共に藤(とう)氏。
先祖は冬嗣流だが、摂関家とは大分離れている。
それでも冬嗣から三代目の兼輔(かねすけ)の時には、中納言で公卿の列にあった。
兼輔は堤(つつみ)中納言として知られ、その子清正や孫の為頼は歌人である。
為頼の弟の為時は詩才があり、文章(もんじょう)博士でもあった。
また式部の母方の親戚には、『蜻蛉日記』の作者や、『更級日記』の作者が生れているし、一族が文才に富んでいたらしい。
『源氏物語』の成立は奇蹟とか偶然とかいわれるものでなく、遺伝的にも作者には才能があったのである。
・式部の生涯を辿ると、3歳の時に弟惟規(のぶのり)が生れ、その翌年に母が亡くなった。
父為時には他に妻もあったらしいが、とにかく式部は父の許(もと)で育っている。
7歳の時には惟道(のぶみち)が生れた。
・為時は円融、花山朝では信任を得ていて、娘が17歳の春には、式部大丞になっている。
しかし、花山帝退位と共に、摂関家からにらまれて官を失った。
それ以後は学問文芸に精励したらしい。
そして10年後の長徳2年に越前守に任じ、式部も父に従った。
しかし2年後には、式部ひとりが帰京して、藤原宣孝と結婚している。
・宣孝は式部と同じ北家の出で、式部とは「またいとこ」に当る。
父為輔(ためすけ)は公卿に列したが、宣孝自身及び兄弟はみな受領階級であるし、何人かあった妻の出身もすべて受領層である。
式部が29歳で結婚した時には、宣孝はすでに5人の男子をもち、年齢も45、6歳になっていた。
式部としてはこんな宣孝に不満だったろうが、30歳といえば当時ではもう女の数に入らなかっただろうし、辛抱したに違いない。
式部の嫉妬心をあおるような行為が宣孝にはたびたびあり、不幸な結婚生活だったが、しかし3年後には死別した。
・未亡人生活を続けているうちに『源氏物語』を書きはじめたらしいが、その評判が高くなったのか、道長方から要請されて、中宮彰子の後宮に女官として出仕することになった。
但し内裏はその前日に焼失したので、天皇と中宮は、道長所有の東三条邸におられたのである。
宮仕えの場所は時々変ったが、その間にも式部は物語を書き続けて、だいたいのところ寛弘7年夏には宇治十帖がおわっただろうといわれている。
その後に『紫式部日記』が整理されたらしい。
日記の文章は寛弘5年7月の中宮御産のことから始まっているが、ばらばらに書かれた日記を一つにまとめ、さらに消息文を加えて編集したのであろう。
そして8年には父の為時が越後守に転任し、一緒に行った弟惟規が死んで、式部は孤独となった。
但し、長保元年、30歳の時に生んだ長女の賢子(かたこ、後の大弐三位)はすでに13歳になっていた。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、205頁~207頁)
■日記
さて、『紫式部日記』の最初の文章、
「秋のけはひの立つままに、土御門殿の有様、いはむか
たなくをかし。池のわたりの梢ども、遣水のほとりの草むら、おのがじし色づきわたりつつ、
おほかたの空も艶なるにもてはやされて、不断の御読経の声々、あはれまさりけり。やうやう
涼しき風のけしきにも、例の絶えせぬ水の音なむ、夜もすがら聞きまがはさる」
これは、寛弘五年に里邸へ退下された中宮に従った式部が、御殿の様子を書いたものである。
式部が何処に生れ育ち、何処に生きたか、それを訪ねてみたいという。
・一条朝は火災が多くて内裏も何回か焼け、式部は一度も本当の内裏に生活していなかったと書いた。
出仕の場所は最初が東三条殿。
翌年三月に御所は一条院に移った。
しかし中宮は御産のたびに実家へ戻られる習慣だから、敦成親王と敦良親王誕生の両度に、式部もおつきしていることになる。
そのほか、一条院が焼失した際には、天皇は枇杷殿に移られ、再建成って再び一条院に戻られた時には中宮も御一緒であった。
崩御の後、中宮は東宮に従って枇杷殿にお住まいになったが、里邸が土御門殿なので、上東門院と称した。従って式部も宮仕えを去るまでは、枇杷殿及び土御門殿にあっただろう。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、207頁)
■宮廷生活
・日記の中で式部が、初めて宮仕えに出た日のことを回想して、次のように記す。
「しはすの廿九日にまゐる。はじめてまゐりしもこよひのことぞかし。いみじくも夢路にまど
はれしかなと思ひいづれば、こよなくたち馴れにけるも、うとましの身のほどやとおぼゆ。夜
いたう更けにけり。御物忌におはしましければ、御前にもまゐらず、心ぼそくてうちふしたる
に、前なる人々の、『うちわたりはなほいとけはひことなりけり。里にては、いまは寝なまし
ものを、さもいざとき履のしげさかな』と、いろめかしくいひゐたるを聞きて、
としくれてわが世ふけゆく風の音に心のうちのすさまじきかな
とぞひとりごたれし」
(十二月二十九日に出仕した。はじめて東三条殿に上った日も、十二月二十九日だったのである。ずい分夢中でお仕えした当時を思うと、こんなに宮仕えに馴れてしまった自分というもの
が、うとましいものに思われる。夜もひどく更けた。中宮は御物忌なので、御前に伺候せずに
寝たが、一緒にいる女房達が、「宮中はひどく勝手がちがうのね。里にいればもう寝る頃なのに、
男の人のくつの音がやかましいこと」などと、色めいたことを言っている。私はそれをきいて、
「今年もくれてしまったし何だか年をとるばかり。風の音をきいたって、わびしくてやり切れぬ……」と独言をいった)
・このように書いているが、すでに若い女房のように男の履(くつ)の音を待つこともない式部は、里邸の静寂を想い出しながら、早く宮仕えをやめたいものだと考えていたに違いない。
「すさまじきかな」の言葉は、いよいよ孤独なわが心と共に、宮仕えのすさまじさを痛感して言ったのであろうか。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、208頁~210頁)
■邸宅の跡(廬山寺)
・式部の里邸は、曾祖父の堤中納言兼輔より父為時にまで伝わった、中川の邸宅だと言われている。
・兼輔が堤中納言とよばれるようになったのは、その邸宅が京極中川の東、鴨川の西にあり、庭には川水をひいて、四季の花木を植えたからだそうだ。
兼輔はすぐれた風流人で、醍醐帝に信任され、その邸宅なども立派だったようだ。
この邸(やしき)から土御門殿まではほんの少しの距離だし、また式部が最初に上がった東三条殿なども近かった。
ここには父為時も、また伯父の為頼も住んでいたらしいが、何時の頃に寺となったのか、今では廬山寺の門が西側の寺町通りに向って開き、寺の南側は立命館大学の建物に隣接している。
・廬山寺は、もとは船岡山の南、廬山寺通りにあった。
円浄宗の本山で、元三大師良源の開創とつたえるから、紫式部にはあながち無縁の人とはいえない。
良源は醍醐から一条朝のはじめまで生きた人で、宮中の信任が篤く、叡山中興の祖といわれ、式部の宗教観に深い影響をあたえた筈である。
しかし廬山寺が応仁の乱で焼けた後、天正年間に中川の地へ移ったのだとすると、それまでの邸の伝領はどんな風になっていたのであろうか。
邸宅にも人間と同じように、色んな運命があるのである。
・紫式部は殆どこの邸宅で『源氏物語』を書いたのだといわれているが、この説と『源氏物語』が最初に「帚木(ははきぎ)」の巻から書かれたという説を結びつけてみると面白い。
この巻に出てくる空蟬を、源氏は方違(かたたが)えに行って紀伊守(きのかみ)の中川の邸で見初めるのだが、空蟬は作者の身の上に似ている。
空蟬が夫の死後に紀伊守に言い寄られる話は、式部が夫の宣孝の没後に、継子から失礼な言動に出られたことが、モデルになっているらしい。
・不愉快なこともそれが創造の動機になれば幸せであろう。
すさまじき宮仕えから退出したつれづれの日に、式部は物語の筆をすすめた。
邸の庭にひいた中川の水をじっと見つめ、その眼を上げて、鴨川の向うにそびえる比叡山を眺めながら、虚構の物語に、あるいは真実の仏の教えに、心をひそめた式部の姿を想いみると、廬山寺の庭もそれなりに意味をもってくる、という。
・『源氏物語』を書いた後で式部がどう生きたか、没年がいつであるか、それも正確にはわからない。
しかしわからないということが、かえって彼女に箔をつけている、と著者は記す。
式部はやはり天才か、爛熟した王朝にあらわれた、文学の精霊みたいなものであったのだろうという。
(田中阿里子『源氏物語の舞台』徳間文庫、1988年、210頁~213頁)