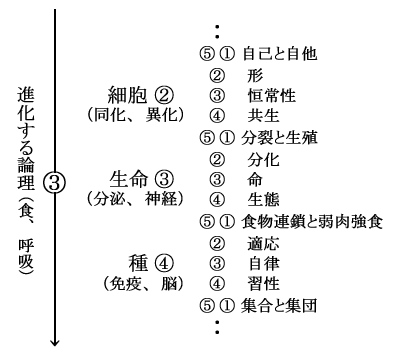有機物には、炭素が含まれているというだけではなく、未だ定義されていない性質があるのではないか。それが「化学反応は反応しているのではなく、反応させられている」というもの。
この働きはイオンとか帯電による電磁気力によるもので、引力と斥力を切り替えることで反応を誘導する。最終的に半導体素子のON.OFFのような切り替えができれば、酵素の働きや、タンパク質合成のような仕事もできるようになるのでは。
これを解明するには、原始の海で何が起こったか、誘導をエネルギーの流れとして捉える必要がある。
微分と積分の関係は、エネルギーの伝わり方そのもののよう。

たとえば、
各項を立体的なエネルギー構造体とし、これを解く。
こういう考え方はできないだろうか?
・周期表の横列は数を表すが、段によって進数が変わるものとする。
・周期表の段が上がるのは、桁または指数が増えるのに相当する。
・こうして表される数は立体的であり、さらに階層構造をもつものとする...みたいな。
ちなみに、微分積分法は地球表面の三次元体系だから有効であって、均一な三次元面でなかったり、四次元の強い影響下ではあまり役に立たない。

※微分と積分で次元が行き来する関係を見ると、三次元にとって二次元(電子)はエネルギーとして捉えるしかないのかもしれない。だとすると四次元にとって三次元もエネルギーでしかないことになる。しかし我々は、三次元では粒子が星を造って実体として振舞っているのを知っている。ならば二次元にも粒子としての振る舞いがあるのではないか。光(半次元)が粒子と波の性質を併せ持つのもこのためでは。