シャドー・バンキングとは何か

石平太郎氏
中国の経済問題を扱った文章を読むと、必ずと言っていいくらいに、「シャドー・バンキング」という言葉を目にします。正直なところ、これまで私は「だいたいの意味は分かる」というくらいのレベルに甘んじてきました。
今回たまたま中国問題評論家の石平氏の『「全身病巣」国家・中国の死に方』(宝島社)を読んでみたら、「シャドー・バンキング」についての言及がありました。それを読むと、シャドー・バンキングのイメージが実に鮮やかになったのです。石平氏が、シャドー・バンキングをどう論じているのかについて、その要点をかいつまんでお伝えしようと思います。
1980年台前半以来の中国の高度経済成長は、「二台の馬車」という特殊な要因によって生み出されてきました。その「二台の馬車」とは、「輸出」と「投資」です。「輸出」の目覚しい伸びは、中国を「世界の工場」と呼ばれる存在に押し上げました。また、「投資」とは国内の固定資産投資を増やすことです。中国は、工場や機械など企業の設備投資、民間の不動産投資、政府のインフラ投資(いわゆる公共事業)を猛烈な勢いで拡大してきたのです。
このことは、中国の貧弱な内需を物語ってもいます。つまり、目覚しい経済成長の陰で、中国は、慢性的な消費不足に悩んできたのです。中国のGDPに占める個人消費の割合は37%に過ぎません。「世界第二位」の経済大国になった国として、普通それはありえないことです。この事態は、共産党員という特権階級に、国民が汗水垂らして生み出した国富が集中する中国経済のいびつさを物語っています。要するに、慢性的な消費不足という中国経済の宿痾を治すには、共産党員という特権階級が消滅しなければならなのです。だがそれは、中共の独裁体制の崩壊を意味するので、到底不可能である、というジレンマにいまの中国は直面しているのです。ちなみに、日本のGDPにおける個人消費率は60%であり、アメリカは70%です。
では、中国はどうやって「投資」を増やしてきたのでしょうか。それは、中央銀行頼みの財政出動と金融緩和によってです。平たくいえば、中国政府は、国民が消費をしないかわりに、企業や政府がお金を使いまくることにした、というわけです。企業や政府が、売上や税収だけを元手に投資することにはおのずと限界があります。その限界を突破するために、中公銀行がどんどんお金を刷って、政府の財源に当て、企業の投資を後押しするわけです。これは、中国のみならず、世界の国々でごく普通に行われていることではあるのですが、中国の場合は、過度の「放漫融資」になっている点が異なります。09年を例にすれば、GDPが日本円換算で536兆円なのに対して、新規融資額は154兆円に及んでいます。新規融資額が、GDPの約29%を占めているのです。その前年の日本の新規融資率が、GDP比で1%にも満たないことと比較すれば、その異常さがお分かりいただけるでしょう。
このようないびつな形においてではありますが、中国では市場経済が発達して、民間企業が中国経済の6割を支えるようになりました。ところが、中国の銀行は、あいかわらず大手国有企業ばかりを優遇し、中小企業にはお金を貸しません。また、いま述べたような異常な貨幣供給状況があるので、中共政府は、悪性インフレの影に怯えています。そこで中共政府は、11年秋から12年春まで金融引き締め政策を実施しました。そのせいで、ただでさえ慢性的な資金不足に悩む中小企業に、当然のことながら倒産の嵐が吹き荒れることになりました。例えば、浙江省温州市では、12年末に約4000社あった中小企業が約1600社にまで激減しています。
では、なんとか生き延びている中小企業は、どうしたらいいのでしょうか。正規の融資の道は絶たれているのですから、ヤミ金融に手を染めるよりほかはありませんね。
金融引き締めを実行しても、中国は基本的に金余りの状態だから、ヤミ金融にお金が流れ込み、中小企業を相手に高い金利でお金を貸すようになっている。11年頃から、いわゆる高利貸し的な商売が流行り、場合によっては年利80%を超える業者まで現れた。(中略)高利貸しが儲かることがわかると、多くの貸し手が高利貸しに参入してくる。しまいには、一部の国有企業までが、高利貸しに参入したいと考えるようになった。
国有企業は、中小企業と異なり、銀行と取引ができるという特権を有するので、安い金利でお金を借りることができます。それを高金利で中小企業に貸し出せば、ボロ儲けができます。本業に精を出さなくても、「濡れ手で粟」状態になれるのですから、それを見逃す手はありません。笑いが止まらないことでしょう。これが、石平氏によれば、「シャドー・バンキング」の前身だそうです。
国有銀行が、指をくわえて、このような国有企業のウハウハ状態を眺めているはずがありませんね。
高利貸しで大儲けをしている業者を見て、最後に腰を上げたのが国有銀行だった。国有企業からすれば、もともとは自分たちのところから出たお金でボロ儲けしている連中がいるということになる。であれば、自分たちで直接、高利貸しをしたほうがいいと考えた。
こうして、国有銀行も高利貸しに参入するようになった。ただし、政府の管轄下にある国有銀行が、法外な高金利でお金を貸すことはできない。法の網をかいくぐるために、国有銀行ダミー会社を作ることにした。具体的には、「融資平台」(ロンズーピンタイ)と呼ばれる投資会社を設立する。国有企業は、この投資会社に出資する形を取るのである。
融資平台は国有銀行からの出資金を元手に、中小企業に対して高い金利でお金を貸し出す。融資平台を通した国有銀行による脱法的な高利貸しこそが、「シャドー・バンキング」 の正体だ。
脱法的な存在なのではありますが、「シャドー・バンキング」は社会的なニーズに深く根ざしているので、どんどん拡大しています。やがて、その豊かな資金源を生かした「理財商品」(高利回りの資産運用商品。主に小口で短期の金銭信託)が開発され、一般の人々も融資平台に投資するようになっていきます。さらに、金融引き締め政策で財政状態が逼迫した地方政府も、融資平台からお金を借りるようになりました。
いかがでしょうか。以上をお読みになったみなさまも、「シャドー・バンキングのイメージが実に鮮やかになった」のではないでしょうか。明快な説明で名高い三橋貴明さん(私自身、そう思います)でも、ことシャドー・バンキングに関しては、なんとなくすっきりしない説明になってしまっているような感じなんですね。
私は、石平氏が描き出した「シャドー・バンキング」の生々しい正体を、正鵠を射たものとして受けとめます。しかし、そこには、中共政府に対する根底的な激しい批判が存するので、日本の大手メディアが、それをきっちりと報道するとは思えません。大手メディアって、中共関連の報道に関して「遠慮深い」ですからね。つまり、石平氏の正鵠を射た議論は、なかなか世間に広まらない。というのは、彼らの主なスポンサーである経団連等の大手グローバル企業団体が中共政府と一蓮托生的な利害を共有する、ゆがんだズブズブの関係にあり、それゆえいかに正しいものであっても、中国批判を好まないという事情に、大手マスコミが取り巻かれているからです。実際、大手マスコミから納得のいく中国報道が私の耳に伝わってきた経験はほとんどありません。産経新聞でさえ、経済面では筆先が鈍っているような印象があります。
それはそれとして、石平氏が描き出した「シャドー・バンキング」の正体にじっと目を凝らしていると、中国の貧弱な実態経済がくっきりと浮びあがってきます。それを無視して、国家がかりでマネーゲームになおも踊り続けているのが、いまの中国の現実なのです。とするならば、「シャドー・バンキング」が融資したお金が、きちんと回収される可能性は絶望的である、という結論が得られそうです。つまり、今後膨大な金額の「不良債権」が浮上するのは必然ということです。それを経験した日本が、長らくのデフレ不況に陥ったことを、私たちは身に沁みて知っています。つまり、そう遠くはない未来に、中国は強烈なデフレ圧力に見舞われ、それに呻吟する時期を迎えることになるのでしょう。
それが、政治的に何を招来することになるのか、私たちは注意深く見守りそれに粛々と対処する必要がありそうです。その点、石平氏の今後の発言は、おおいに参考になりそうな気がします。いっそのこと、彼を対中国外交のブレーンとして招くわけにはいかないものでしょうか。「日中友好バンザイ、お金クレ」というレベルの低い連中ばかりがいつまでも政府を取り巻いていては、まともな対中国政策が浮上して来にくいのではないかと思われます。

石平太郎氏
中国の経済問題を扱った文章を読むと、必ずと言っていいくらいに、「シャドー・バンキング」という言葉を目にします。正直なところ、これまで私は「だいたいの意味は分かる」というくらいのレベルに甘んじてきました。
今回たまたま中国問題評論家の石平氏の『「全身病巣」国家・中国の死に方』(宝島社)を読んでみたら、「シャドー・バンキング」についての言及がありました。それを読むと、シャドー・バンキングのイメージが実に鮮やかになったのです。石平氏が、シャドー・バンキングをどう論じているのかについて、その要点をかいつまんでお伝えしようと思います。
1980年台前半以来の中国の高度経済成長は、「二台の馬車」という特殊な要因によって生み出されてきました。その「二台の馬車」とは、「輸出」と「投資」です。「輸出」の目覚しい伸びは、中国を「世界の工場」と呼ばれる存在に押し上げました。また、「投資」とは国内の固定資産投資を増やすことです。中国は、工場や機械など企業の設備投資、民間の不動産投資、政府のインフラ投資(いわゆる公共事業)を猛烈な勢いで拡大してきたのです。
このことは、中国の貧弱な内需を物語ってもいます。つまり、目覚しい経済成長の陰で、中国は、慢性的な消費不足に悩んできたのです。中国のGDPに占める個人消費の割合は37%に過ぎません。「世界第二位」の経済大国になった国として、普通それはありえないことです。この事態は、共産党員という特権階級に、国民が汗水垂らして生み出した国富が集中する中国経済のいびつさを物語っています。要するに、慢性的な消費不足という中国経済の宿痾を治すには、共産党員という特権階級が消滅しなければならなのです。だがそれは、中共の独裁体制の崩壊を意味するので、到底不可能である、というジレンマにいまの中国は直面しているのです。ちなみに、日本のGDPにおける個人消費率は60%であり、アメリカは70%です。
では、中国はどうやって「投資」を増やしてきたのでしょうか。それは、中央銀行頼みの財政出動と金融緩和によってです。平たくいえば、中国政府は、国民が消費をしないかわりに、企業や政府がお金を使いまくることにした、というわけです。企業や政府が、売上や税収だけを元手に投資することにはおのずと限界があります。その限界を突破するために、中公銀行がどんどんお金を刷って、政府の財源に当て、企業の投資を後押しするわけです。これは、中国のみならず、世界の国々でごく普通に行われていることではあるのですが、中国の場合は、過度の「放漫融資」になっている点が異なります。09年を例にすれば、GDPが日本円換算で536兆円なのに対して、新規融資額は154兆円に及んでいます。新規融資額が、GDPの約29%を占めているのです。その前年の日本の新規融資率が、GDP比で1%にも満たないことと比較すれば、その異常さがお分かりいただけるでしょう。
このようないびつな形においてではありますが、中国では市場経済が発達して、民間企業が中国経済の6割を支えるようになりました。ところが、中国の銀行は、あいかわらず大手国有企業ばかりを優遇し、中小企業にはお金を貸しません。また、いま述べたような異常な貨幣供給状況があるので、中共政府は、悪性インフレの影に怯えています。そこで中共政府は、11年秋から12年春まで金融引き締め政策を実施しました。そのせいで、ただでさえ慢性的な資金不足に悩む中小企業に、当然のことながら倒産の嵐が吹き荒れることになりました。例えば、浙江省温州市では、12年末に約4000社あった中小企業が約1600社にまで激減しています。
では、なんとか生き延びている中小企業は、どうしたらいいのでしょうか。正規の融資の道は絶たれているのですから、ヤミ金融に手を染めるよりほかはありませんね。
金融引き締めを実行しても、中国は基本的に金余りの状態だから、ヤミ金融にお金が流れ込み、中小企業を相手に高い金利でお金を貸すようになっている。11年頃から、いわゆる高利貸し的な商売が流行り、場合によっては年利80%を超える業者まで現れた。(中略)高利貸しが儲かることがわかると、多くの貸し手が高利貸しに参入してくる。しまいには、一部の国有企業までが、高利貸しに参入したいと考えるようになった。
国有企業は、中小企業と異なり、銀行と取引ができるという特権を有するので、安い金利でお金を借りることができます。それを高金利で中小企業に貸し出せば、ボロ儲けができます。本業に精を出さなくても、「濡れ手で粟」状態になれるのですから、それを見逃す手はありません。笑いが止まらないことでしょう。これが、石平氏によれば、「シャドー・バンキング」の前身だそうです。
国有銀行が、指をくわえて、このような国有企業のウハウハ状態を眺めているはずがありませんね。
高利貸しで大儲けをしている業者を見て、最後に腰を上げたのが国有銀行だった。国有企業からすれば、もともとは自分たちのところから出たお金でボロ儲けしている連中がいるということになる。であれば、自分たちで直接、高利貸しをしたほうがいいと考えた。
こうして、国有銀行も高利貸しに参入するようになった。ただし、政府の管轄下にある国有銀行が、法外な高金利でお金を貸すことはできない。法の網をかいくぐるために、国有銀行ダミー会社を作ることにした。具体的には、「融資平台」(ロンズーピンタイ)と呼ばれる投資会社を設立する。国有企業は、この投資会社に出資する形を取るのである。
融資平台は国有銀行からの出資金を元手に、中小企業に対して高い金利でお金を貸し出す。融資平台を通した国有銀行による脱法的な高利貸しこそが、「シャドー・バンキング」 の正体だ。
脱法的な存在なのではありますが、「シャドー・バンキング」は社会的なニーズに深く根ざしているので、どんどん拡大しています。やがて、その豊かな資金源を生かした「理財商品」(高利回りの資産運用商品。主に小口で短期の金銭信託)が開発され、一般の人々も融資平台に投資するようになっていきます。さらに、金融引き締め政策で財政状態が逼迫した地方政府も、融資平台からお金を借りるようになりました。
いかがでしょうか。以上をお読みになったみなさまも、「シャドー・バンキングのイメージが実に鮮やかになった」のではないでしょうか。明快な説明で名高い三橋貴明さん(私自身、そう思います)でも、ことシャドー・バンキングに関しては、なんとなくすっきりしない説明になってしまっているような感じなんですね。
私は、石平氏が描き出した「シャドー・バンキング」の生々しい正体を、正鵠を射たものとして受けとめます。しかし、そこには、中共政府に対する根底的な激しい批判が存するので、日本の大手メディアが、それをきっちりと報道するとは思えません。大手メディアって、中共関連の報道に関して「遠慮深い」ですからね。つまり、石平氏の正鵠を射た議論は、なかなか世間に広まらない。というのは、彼らの主なスポンサーである経団連等の大手グローバル企業団体が中共政府と一蓮托生的な利害を共有する、ゆがんだズブズブの関係にあり、それゆえいかに正しいものであっても、中国批判を好まないという事情に、大手マスコミが取り巻かれているからです。実際、大手マスコミから納得のいく中国報道が私の耳に伝わってきた経験はほとんどありません。産経新聞でさえ、経済面では筆先が鈍っているような印象があります。
それはそれとして、石平氏が描き出した「シャドー・バンキング」の正体にじっと目を凝らしていると、中国の貧弱な実態経済がくっきりと浮びあがってきます。それを無視して、国家がかりでマネーゲームになおも踊り続けているのが、いまの中国の現実なのです。とするならば、「シャドー・バンキング」が融資したお金が、きちんと回収される可能性は絶望的である、という結論が得られそうです。つまり、今後膨大な金額の「不良債権」が浮上するのは必然ということです。それを経験した日本が、長らくのデフレ不況に陥ったことを、私たちは身に沁みて知っています。つまり、そう遠くはない未来に、中国は強烈なデフレ圧力に見舞われ、それに呻吟する時期を迎えることになるのでしょう。
それが、政治的に何を招来することになるのか、私たちは注意深く見守りそれに粛々と対処する必要がありそうです。その点、石平氏の今後の発言は、おおいに参考になりそうな気がします。いっそのこと、彼を対中国外交のブレーンとして招くわけにはいかないものでしょうか。「日中友好バンザイ、お金クレ」というレベルの低い連中ばかりがいつまでも政府を取り巻いていては、まともな対中国政策が浮上して来にくいのではないかと思われます。












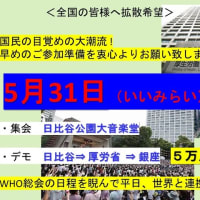















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます