【続タトゥー】近藤先生から
<子供の頃、口のまわりに入れ墨をしたおばあさんを見た記憶があります。
勿論日本人です。それにお歯黒はチョイチョイ見ました。子供ながらに色気を感じた記憶があるのです!
入れ墨は兵庫県または愛知県での記憶だと思います。お歯黒は愛媛でも結構ありました。昭和一桁か、二桁の初めの頃の話です。>
というコメントを頂いた。
昭和10(1935)年のことだと仮定すると、明治4([1871)年の「禁止令」から64年後のことになります。アイヌの場合、女の子は5歳で入れ墨を初め、毎年入れる範囲を広くしたようです。
琉球の入れ墨のことが柳田邦男「海南小記」(角川文庫)所収の「いれずみの南北」という小文に少しだけ書いてありました。
柳田は、入れ墨の風習と女が額に紐を掛けて荷物を運ぶ(頭の上に載せるのではなく)風習とは、相関があり、ハチジという入れ墨の風習とイタダキという額にかけた紐で荷を運ぶ習慣は、沖縄、奄美諸島にはあるが、奄美大島が北限でトカラ諸島南端の宝島には入らなかった、と述べています。
入れ墨を意味する「ハチジ」という音は、「針突き」(ハッツキ)の転音だろうとしています。
柳田の九州・沖縄旅行は1920年のことで、「昔は小学生で入れ墨をした生徒がいたそうだが、今は老女の間にだけ見られる」と書いています。この時、彼は45歳ですから「老女」とは60歳以上の女のことかと思います。
近藤先生が見かけられたのが、それから15年後だとすると、ほぼ話は合うと思います。
なお、柳田は宝島、悪石島で見かけた手背に入れ墨をした女は、いずれも奄美大島か、沖縄糸満出身の女だったと書いています。それにしても、バードの観察と記載に比べると、絵も写真もなく記載に具体性が乏しく、学問的レベルは相当下です。
なお、お歯黒はトカラ七島では、女が13歳になった年の5月に、一回だけ付けるそうで、女になった印だそうです。口の周りに入れ墨をすることは、柳田の文には見あたりません。
バードの本には、「口の上下に幅広く帯状に入れ墨をしているばかりでなく、指関節にも帯状に入れ墨をし、手の裏には精巧な模様をつけている。」(p.296)と書いています。(アイヌの口の入れ墨の写真を探したが見つかりません。添付1 はバードの旅行記に載っているアイヌ女性の手の入れ墨です。)
はバードの旅行記に載っているアイヌ女性の手の入れ墨です。)
小シーボルトはバードより少し先に、やはり北海道流沙郡平取のアイヌ村に調査に入っています。彼の「小シーボルト蝦夷見聞記」(東洋文庫)によると、「アイヌの入れ墨は女だけに行われ、まだ7,8歳の女の子の上唇のすぐ上に、小刀で横に多発性に傷をつけ、そこに煤を刷り込むところから始まる。口ひげみたいになるが、両端が口角部で上に向かう。口の周囲の入れ墨が済むと、手背と前腕の入れ墨が行われる。女が結婚するともう入れ墨はしない」と書いてあります。(p.41-41)
なお本書訳注によると、明治の「入れ墨禁止令」は最初が1871年10月、実効性がないので、1876年9月に摘発と懲罰を科すことに禁令を改めたそうです。
沖縄に口囲に入れ墨する風習がなかったとすれば、先生が見られたお婆さんは1876年に、「入れ墨禁止令」が強化される前に、入れ墨をされたアイヌだったのだと思います。1871年生まれだったとすると、口の周りだけ入れ墨して、手にはできなかったということも起こりえたと思います。
入れ墨はM.モネスティエ「図説奇形全書」(原書房)にも章があり、「人工的奇形」に分類されています。職業的には水夫、兵士に多く、変わったところでは見世物芸人になるために全身に入れ墨をした、という例もあるそうです。添付2 は、「人間シマウマ」と呼ばれたグレート・オミという芸人で、全身に黒帯状の縞を入れ、ロンドンの有名な彫り師が担当し1922年にデビュー、45年に引退したといいます。ここまで徹底した入れ墨は見たことがありません。オミが有名になったのは、「知識人の大ブルジョア」の息子だったからだ、とも書いています。
は、「人間シマウマ」と呼ばれたグレート・オミという芸人で、全身に黒帯状の縞を入れ、ロンドンの有名な彫り師が担当し1922年にデビュー、45年に引退したといいます。ここまで徹底した入れ墨は見たことがありません。オミが有名になったのは、「知識人の大ブルジョア」の息子だったからだ、とも書いています。
今回、「小シーボルト蝦夷見聞記」の原田信男「解説」を読んで、蝦夷のアイヌ語地名に漢字を当て、日本語にしたのが松浦武四郎だと知りました。
また伊波普猷「古琉球」(岩波文庫)を読むと、元来、南九州と沖縄の地名はアイヌ語とほぼ同じだとあります。ところが金田一京助「ユーカラ」(岩波文庫)には、知里幸恵「アイヌ神謡集」(岩波文庫)とちがい、アイヌ語のローマ字表記が載っていない。金田一が勝手に日本語訳をしている。これでは言語学の資料としては使えない。索引もない。
鳥居龍蔵「ある老学徒の手記」(岩波文庫)で、彼は「琉球の土器には、台湾のヤミ族と同じものがある」と述べ、アイヌとのつながりも考えています。医学的には遺伝子とHTLV-1の分布から、沖縄=南九州=紀伊熊野=アイヌとのつながりは、ほぼ実証されています。
そういう点から、アイヌ語、沖縄語と記紀、万葉集以前の古代日本語の関係は再考されるべきだと思いますが、肝腎のアイヌ語ローマ字表記テキストがなくては、素人には手が出ませんね。
「アイヌ神謡集」のようなアイヌ語と日本語の並記がしてあれば、アイヌ語の解読は「ロゼッタストーン解読」より容易です。
例えば、
Menoko=女
Kamui=神
Pito=ヒト
Wakka=水
Pirka=清い
Pirka-wakka=清流
Sake=酒
Pirka-sake=美酒(清酒)
Ainu=人間、アイヌ
Ainu-pito=アイヌ人
Utar=複数を表す語尾(我ら、たち)
Ainu-utari=人間たち(アイヌ民族のこと)
Kotan=村
Ainu-kotan=アイヌの村
Moshir=国、領土
Ainu-moshir=人間の国、アイヌの土地
Tektui=手
Chep=魚
Chep-utar=魚たち
Kamui-chep-utar=神の魚たち(鮭のこと)
ゴチの部分は、日本語と同じ単語です。また造語法は「飛行機」を「天翔るからくり」と大和言葉でいうように、基礎語をそのまま語頭に重ねており、漢字造語のように「抽象化と圧縮」がない点で、古代日本語と同じです。
大野晋「日本語の源流を求めて」(岩波新書, 2007)を読みなおしましたが、大野説では縄文時代に、西日本でポリネシア語族の一つが使われていた。そこにタミール語が到来して「大和言葉」が作られた。それが北東及び西南に広がった。東北、北海道のアイヌ語や南九州、沖縄の隼人語との関係があいまいです。ことに隼人語をポリネシア語(オーストロネシア語)としながら、アイヌ語については、何も述べていない。
これは前3,500年頃に、台湾で外洋航海用のダブル・アウトリッガー・カヌーが発明され、古モンゴロイド系の民族がフィリピン、ボルネオ、インドネシア、マレー半島へ、またハワイ、イースター島、ニュージーランドを含むポリネシア諸島に拡散をはじめ、それに伴いオーストロネシア語が各地に広まったという、最近の比較言語学と考古学の知識が取り入れられていない。
また言語年代学という統計的手法が用いられておらず、定性的手法しかない。
(Cf. J.ダイアモンド「銃・病原体・鉄」, 草思社文庫, 2012)
タミール語はインド南部とスリランカ北部の稲作地帯で話されている言葉で、もしタミール語を話す人々が日本に渡来したのであれば、どうして途中に彼らの遺跡や言語が残っていないのか、説明がつかない。
栽培イネはアフリカにはグラベリマ、インドにはサチバ・インディカ、日本にはサチバ・ジャポニカがあり、別種である。それぞれ独自に栽培種になったものだ。ジャポニカの故郷は南中国だ。
台湾を出たオーストロネシア語が、セイロン島に入り、そこから南インドのタミール地方に広まったということも考えられると思う。
その場合、日本の縄文時代の終わり頃の言語は、オーストロネシア語だったことになる。だからアイヌ語と琉球・隼人語に類似性があるということになるだろう。その後、朝鮮半島から弥生人が九州北部に到達し、そこから東に進み、本州中央部を占めるようになったので、アイヌ語と隼人・琉球語が分離されたと考える方がより矛盾が少ない。これはHLAやHTLV-ウイルスの分布とも一致している。
征服者が少数だった場合、言語学的には原住民の言葉が主流になり、征服者の言葉は部分的にしか残らないことは、12世紀の「ノルマン征服」の結果、古英語が中世英語に変わったが、激変はなかった例をみればわかる。折口信夫「死者の書」に奈良時代、上流階級と庶民の言葉が違っていて、意思疎通が難しかったことが書いてあるが、そういう時代が英国にもあった。
<子供の頃、口のまわりに入れ墨をしたおばあさんを見た記憶があります。
勿論日本人です。それにお歯黒はチョイチョイ見ました。子供ながらに色気を感じた記憶があるのです!
入れ墨は兵庫県または愛知県での記憶だと思います。お歯黒は愛媛でも結構ありました。昭和一桁か、二桁の初めの頃の話です。>
というコメントを頂いた。
昭和10(1935)年のことだと仮定すると、明治4([1871)年の「禁止令」から64年後のことになります。アイヌの場合、女の子は5歳で入れ墨を初め、毎年入れる範囲を広くしたようです。
琉球の入れ墨のことが柳田邦男「海南小記」(角川文庫)所収の「いれずみの南北」という小文に少しだけ書いてありました。
柳田は、入れ墨の風習と女が額に紐を掛けて荷物を運ぶ(頭の上に載せるのではなく)風習とは、相関があり、ハチジという入れ墨の風習とイタダキという額にかけた紐で荷を運ぶ習慣は、沖縄、奄美諸島にはあるが、奄美大島が北限でトカラ諸島南端の宝島には入らなかった、と述べています。
入れ墨を意味する「ハチジ」という音は、「針突き」(ハッツキ)の転音だろうとしています。
柳田の九州・沖縄旅行は1920年のことで、「昔は小学生で入れ墨をした生徒がいたそうだが、今は老女の間にだけ見られる」と書いています。この時、彼は45歳ですから「老女」とは60歳以上の女のことかと思います。
近藤先生が見かけられたのが、それから15年後だとすると、ほぼ話は合うと思います。
なお、柳田は宝島、悪石島で見かけた手背に入れ墨をした女は、いずれも奄美大島か、沖縄糸満出身の女だったと書いています。それにしても、バードの観察と記載に比べると、絵も写真もなく記載に具体性が乏しく、学問的レベルは相当下です。
なお、お歯黒はトカラ七島では、女が13歳になった年の5月に、一回だけ付けるそうで、女になった印だそうです。口の周りに入れ墨をすることは、柳田の文には見あたりません。
バードの本には、「口の上下に幅広く帯状に入れ墨をしているばかりでなく、指関節にも帯状に入れ墨をし、手の裏には精巧な模様をつけている。」(p.296)と書いています。(アイヌの口の入れ墨の写真を探したが見つかりません。添付1
 はバードの旅行記に載っているアイヌ女性の手の入れ墨です。)
はバードの旅行記に載っているアイヌ女性の手の入れ墨です。)小シーボルトはバードより少し先に、やはり北海道流沙郡平取のアイヌ村に調査に入っています。彼の「小シーボルト蝦夷見聞記」(東洋文庫)によると、「アイヌの入れ墨は女だけに行われ、まだ7,8歳の女の子の上唇のすぐ上に、小刀で横に多発性に傷をつけ、そこに煤を刷り込むところから始まる。口ひげみたいになるが、両端が口角部で上に向かう。口の周囲の入れ墨が済むと、手背と前腕の入れ墨が行われる。女が結婚するともう入れ墨はしない」と書いてあります。(p.41-41)
なお本書訳注によると、明治の「入れ墨禁止令」は最初が1871年10月、実効性がないので、1876年9月に摘発と懲罰を科すことに禁令を改めたそうです。
沖縄に口囲に入れ墨する風習がなかったとすれば、先生が見られたお婆さんは1876年に、「入れ墨禁止令」が強化される前に、入れ墨をされたアイヌだったのだと思います。1871年生まれだったとすると、口の周りだけ入れ墨して、手にはできなかったということも起こりえたと思います。
入れ墨はM.モネスティエ「図説奇形全書」(原書房)にも章があり、「人工的奇形」に分類されています。職業的には水夫、兵士に多く、変わったところでは見世物芸人になるために全身に入れ墨をした、という例もあるそうです。添付2
 は、「人間シマウマ」と呼ばれたグレート・オミという芸人で、全身に黒帯状の縞を入れ、ロンドンの有名な彫り師が担当し1922年にデビュー、45年に引退したといいます。ここまで徹底した入れ墨は見たことがありません。オミが有名になったのは、「知識人の大ブルジョア」の息子だったからだ、とも書いています。
は、「人間シマウマ」と呼ばれたグレート・オミという芸人で、全身に黒帯状の縞を入れ、ロンドンの有名な彫り師が担当し1922年にデビュー、45年に引退したといいます。ここまで徹底した入れ墨は見たことがありません。オミが有名になったのは、「知識人の大ブルジョア」の息子だったからだ、とも書いています。今回、「小シーボルト蝦夷見聞記」の原田信男「解説」を読んで、蝦夷のアイヌ語地名に漢字を当て、日本語にしたのが松浦武四郎だと知りました。
また伊波普猷「古琉球」(岩波文庫)を読むと、元来、南九州と沖縄の地名はアイヌ語とほぼ同じだとあります。ところが金田一京助「ユーカラ」(岩波文庫)には、知里幸恵「アイヌ神謡集」(岩波文庫)とちがい、アイヌ語のローマ字表記が載っていない。金田一が勝手に日本語訳をしている。これでは言語学の資料としては使えない。索引もない。
鳥居龍蔵「ある老学徒の手記」(岩波文庫)で、彼は「琉球の土器には、台湾のヤミ族と同じものがある」と述べ、アイヌとのつながりも考えています。医学的には遺伝子とHTLV-1の分布から、沖縄=南九州=紀伊熊野=アイヌとのつながりは、ほぼ実証されています。
そういう点から、アイヌ語、沖縄語と記紀、万葉集以前の古代日本語の関係は再考されるべきだと思いますが、肝腎のアイヌ語ローマ字表記テキストがなくては、素人には手が出ませんね。
「アイヌ神謡集」のようなアイヌ語と日本語の並記がしてあれば、アイヌ語の解読は「ロゼッタストーン解読」より容易です。
例えば、
Menoko=女
Kamui=神
Pito=ヒト
Wakka=水
Pirka=清い
Pirka-wakka=清流
Sake=酒
Pirka-sake=美酒(清酒)
Ainu=人間、アイヌ
Ainu-pito=アイヌ人
Utar=複数を表す語尾(我ら、たち)
Ainu-utari=人間たち(アイヌ民族のこと)
Kotan=村
Ainu-kotan=アイヌの村
Moshir=国、領土
Ainu-moshir=人間の国、アイヌの土地
Tektui=手
Chep=魚
Chep-utar=魚たち
Kamui-chep-utar=神の魚たち(鮭のこと)
ゴチの部分は、日本語と同じ単語です。また造語法は「飛行機」を「天翔るからくり」と大和言葉でいうように、基礎語をそのまま語頭に重ねており、漢字造語のように「抽象化と圧縮」がない点で、古代日本語と同じです。
大野晋「日本語の源流を求めて」(岩波新書, 2007)を読みなおしましたが、大野説では縄文時代に、西日本でポリネシア語族の一つが使われていた。そこにタミール語が到来して「大和言葉」が作られた。それが北東及び西南に広がった。東北、北海道のアイヌ語や南九州、沖縄の隼人語との関係があいまいです。ことに隼人語をポリネシア語(オーストロネシア語)としながら、アイヌ語については、何も述べていない。
これは前3,500年頃に、台湾で外洋航海用のダブル・アウトリッガー・カヌーが発明され、古モンゴロイド系の民族がフィリピン、ボルネオ、インドネシア、マレー半島へ、またハワイ、イースター島、ニュージーランドを含むポリネシア諸島に拡散をはじめ、それに伴いオーストロネシア語が各地に広まったという、最近の比較言語学と考古学の知識が取り入れられていない。
また言語年代学という統計的手法が用いられておらず、定性的手法しかない。
(Cf. J.ダイアモンド「銃・病原体・鉄」, 草思社文庫, 2012)
タミール語はインド南部とスリランカ北部の稲作地帯で話されている言葉で、もしタミール語を話す人々が日本に渡来したのであれば、どうして途中に彼らの遺跡や言語が残っていないのか、説明がつかない。
栽培イネはアフリカにはグラベリマ、インドにはサチバ・インディカ、日本にはサチバ・ジャポニカがあり、別種である。それぞれ独自に栽培種になったものだ。ジャポニカの故郷は南中国だ。
台湾を出たオーストロネシア語が、セイロン島に入り、そこから南インドのタミール地方に広まったということも考えられると思う。
その場合、日本の縄文時代の終わり頃の言語は、オーストロネシア語だったことになる。だからアイヌ語と琉球・隼人語に類似性があるということになるだろう。その後、朝鮮半島から弥生人が九州北部に到達し、そこから東に進み、本州中央部を占めるようになったので、アイヌ語と隼人・琉球語が分離されたと考える方がより矛盾が少ない。これはHLAやHTLV-ウイルスの分布とも一致している。
征服者が少数だった場合、言語学的には原住民の言葉が主流になり、征服者の言葉は部分的にしか残らないことは、12世紀の「ノルマン征服」の結果、古英語が中世英語に変わったが、激変はなかった例をみればわかる。折口信夫「死者の書」に奈良時代、上流階級と庶民の言葉が違っていて、意思疎通が難しかったことが書いてあるが、そういう時代が英国にもあった。












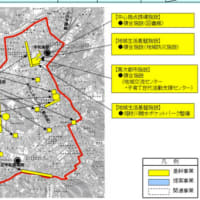
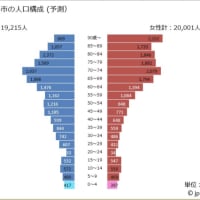



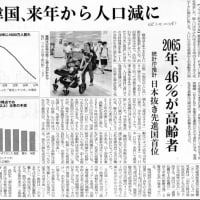










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます