
住職の娘です。
日曜日に、寺の太鼓楼の片づけをしました。
火曜日には、名塩探史会のメンバーの方が、うちの太鼓楼でお預かりしている探史会の収蔵物(昔、村で使っていた品々)を確認しに来られる予定ですので、その前に寺のほうの収蔵物を少し整理しようということになりました。
太鼓楼では、寺の使わなくなった古物も収蔵しており、今まで住職や私が見たことがない珍しいものも出てきました。
主に、江戸・明治時代から戦前あたり祖母の子どもの頃まで使っていた物の一部です。

↓これが何かおわかりでしょうか?


ご覧の通り、ハスの彫り物があるので、蓮台(れんだい)です。
しかも、二つに分離していまして、くっつけるとおよそ真四角の台になります。
一般的に「蓮台」のうえには、仏様がおられるはずなのですが…
これは専用と思われる木箱に台だけが収納してありました。

なんとなく、違和感…
のってた仏様はどこにいったん??( ゚Д゚)となりました。


↓夫や私は、同じ木箱が二つあっても中身がセット物だとは思わなかったくらいなので、上にのせるべきものもわかりませんでした。

↓木箱を開けてみて、初めて「同じものが入ってる!」と驚いたくらいで(笑)
くっつけてみたら「あら不思議…これ二つで一つの蓮台だわ💦」

個人的に寺の収蔵物と思われましたが、確証がなかったので最終兵器である祖母(88歳)を召喚しました(;^_^A
最長老の祖母曰く、「御棺をのせてた台やわ。昔、借物(かりもん)であった」とのこと。
昔は、座棺だったので、これくらいの蓮台に御棺がのったらしいです。
確かに、仏様がのってはったらしいです…
夫&私( ゚д゚)ポカーン
私「カリモン?って何?借り物ってこと?寺の物じゃなくて」
祖母「借物(かりもん)は、お葬式の時に名塩の村の人が、必要な物一式を借りに来てはった物のこと。他にもいろいろあったと思うわ。終わったら返却しにきてはったのを、母親の代わりに受け取ったん覚えてる。お礼に『借物料』ってお金を包んできてくれてはったんよ」
私「葬儀のレンタル用品一式ってこと?借物料はレンタル料?」
祖母「そういうことやね」
夫&私「へぇ~~~~…村内は2カ寺が旦那寺であって、うちは村内のご門徒のお預かりがなかったけど、他のお寺で葬儀があったら一緒に助けてもらえるようになってたんやね」「確かに村で2個も3個も持っていても仕方ない物も多いやろうし、こういうのを預かってたって、確かに『村持ちの寺』って感じですわ」(@_@)(@_@)ありがたや~
50年以上死蔵されていたであろう珍品がでてきたうえ、名塩の村の風習を教えてくれた太鼓楼整理でした。
南無阿弥陀仏











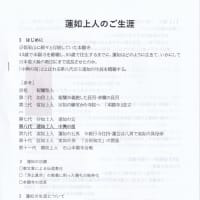



![蓮如上人のご生涯[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/43/65/a9e3f68db595e4ed512643cd418eaa2c.jpg)




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます