
ジョージ・アンタイル
・春 I
・バレエ・メカニック
・ファイティング・ザ・ウェーヴス
・ジャズ・シンフォニー
・リトアニアの夜
・ジャズ・ソナタ
・室内オーケストラのための協奏曲
・ヴァイオリン・ソナタ第1番
・春 II
指揮:HK グルーバー
アンサンブル・モデルン
テノール:マーティン・ヒル
ヴァイオリン:ヤグディシュ・ミストリー
ピアノ:ヘルマン・クレッチュマー
BMG: 09026 68066 2
「音楽界の悪童」とか自称していた1900年生まれのアメリカの作曲家ジョージ・アンタイルの代表作は、何といっても「バレエ・メカニック」でしょう。バレエと言っても実際に舞台でバレエが上演されるわけではなく、機械が踊っているような音楽という意味らしいです。15分くらいの曲で、ピアノ8台、木琴、各種打楽器の他、プロペラ、サイレン、ベルなどの騒音が鳴らされます。後に楽器編成を縮小したバージョンが作られており、このディスクに収録されているのはその改訂版のようです。
聴いてわかるように、騒音です。特に初期版で顕著です。まるでイタリアで興った未来派の音楽のようですが、アンタイル自身は未来派を標榜しているわけではないようです。初演の際には大変なスキャンダルになったようですが、騒音とはいえ現在の耳からすると比較的整った音楽に聴こえます。もっとも、ロマン派大好きリスナーにとってはそうでもないかもしれませんが。私はこういう20世紀前半の音楽、特に前世紀の肥大化したロマン派音楽をぶち壊すような作品が好きなのです。
その他の作品も魅力的なものがそろっています。このディスクのタイトルにもなっている「ファイティング・ザ・ウェーヴス」では、テノールとコーラスが繰り返す長いグリッサンドが異様です。「ジャズ・シンフォニー」と「ジャズ・ソナタ」はタイトル通りジャズっぽいフレーズをコラージュしたような楽しい曲。弦楽四重奏による「リトアニアの夜」は異国情緒とミニマル的な動きが面白い作品。「室内オーケストラのための協奏曲」はまるで新古典主義時代のストラヴィンスキーの作品のようです。これらのように、一つの作風に陥らない所が「悪童」たるゆえんなのかもしれません。
全体的にアメリカ的なインチキくささが楽しめるディスクですが、アンタイルの作品はどれもわざわざインチキくさく作られており、その意味でこのディスクはアンタイル入門には格好の一枚でしょう。交響曲も何曲か作曲しているので、ちょっとひねったインチキくさい曲が好きな方はそちらもぜひ聴いてみてください。
クラシックCD紹介のインデックス










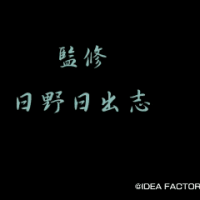
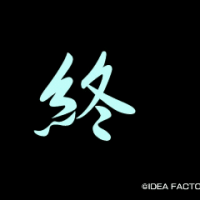
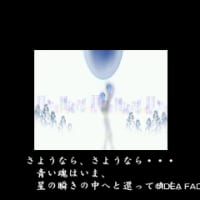


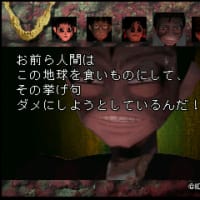

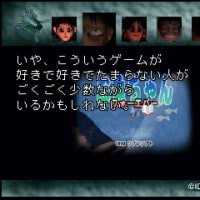

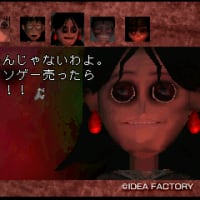
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます