お待たせしました。某日、都内で開かれた忘年会にて発表された、今年のベスト本。
 『赤朽葉家の伝説』 桜庭一樹
『赤朽葉家の伝説』 桜庭一樹
昭和初期から3代にわたる女性の物語。こういう話が好きなので。
桜庭一樹の他の本「七竃となんとか」(題名よく覚えてないけど)も読んだけれど、これはつまらない。この作家よくわからないところがあります。(禁煙好き) 『オリガ・モリソヴナの反語法』 米原万理
『オリガ・モリソヴナの反語法』 米原万理
チェコのソヴィエトスクールのダンス教師オリガ・モリソヴナにまつわる謎をかつての教え子の主人公が解き明かしていく、その経緯はそこらのミステリよりも何倍も面白い。時間を忘れ、読み終わるのがもったいないと感じたのは久しぶりでした。旧ソ連の話というだけで何年も毛嫌いしていた自分を恥じました。 (よぴかり) 『牛乳の作法』 宮沢章夫
『牛乳の作法』 宮沢章夫
この5年で最大のへこみを助けてくれた物のひとつなので。(やませみ) 『The Alexandria Quartet』 Lawrence Durrell
『The Alexandria Quartet』 Lawrence Durrell
新刊ではないのだが(邦訳は新訳が出たのだった、まあそれもひとつの契機となった)。今年の個人的なテーマだった地中海'30sの一環として読んだ。 今回読んでナラティブの断片化の手法がD・リンチの映画に通じるように思え、なんとなく嬉しくなった。
新刊では半年図書館で待った姫野カオルコの「ああ正妻」が、久しぶりに賞取りをもくろんでいない姫野節全開で笑えた。また松山巖の「猫風船」。小説家になっているとは…。改めて旧作「日光」を読みその力量にうならされた。 (Y) 『風が強く吹いている』 三浦しをん
『風が強く吹いている』 三浦しをん
これこそ今年のベスト本、とダントツ、ブッチギリの作品は、今日現在ありません。残り一ヶ月で、そうした本にめぐり合えればと思っています。本書は、心に残った何冊かのうちの一冊。青春群像劇として近頃にない名作だと思います。余談ですが、某青年マンガ雑誌にコミカライズされたものが連載されていますが、これは最悪です。 (天馬トビオ) 『八日目の蝉』 角田光代
『八日目の蝉』 角田光代
他にもいろいろ面白かった本はあったのですが、結構内容を忘れています…。
この本が今でも一番内容を覚えている、インパクトの強い一冊だったので。( キトリ) 『グレート・ギャツビー』 スコット・フィッツジェラルド著 村上春樹訳
『グレート・ギャツビー』 スコット・フィッツジェラルド著 村上春樹訳
読んでよかったと思えたので。いやな女性などが出てきましたが、全体に美しい物語でした。やはり、名作なのですね。昔、読んだはずなのですが、まるで憶えてなかったのです。子供じゃわからない話だったからなのかな。 (舞浜嵐子) 『再起』 ディック・フランシス
『再起』 ディック・フランシス
昨年末、刊行されたシッド・ハレーシリーズですが、図書館で数ヵ月待ちして今年読みました。
いちばん面白かった本というよりも、ここ数年、もう新刊は出ないと思っていたので、80代半ばにして、こういう新しい題材を扱って、一定のレベルを維持して書けるってとこに驚嘆しました。訳者の菊地光さんて、去年お亡くなりになってたのですね。。あとがきで初めて知りました。 (ままりん) 『道元禅師』 立松和平/『デスマスク』『イエスの裔』 柴田錬三郎
『道元禅師』 立松和平/『デスマスク』『イエスの裔』 柴田錬三郎
道元の難解な思想を肉体化し、言語化した労作にこの作者の深化した魂のありようを感じた。今年は半年ほど柴錬の初期の小説や評論、エッセイと取り組んだ。上記の二作は前者が芥川賞の候補に、後者は直木賞の受賞作という純文学と大衆文学との狭間で揺れる作者の心情を象徴する二作である。眠狂四郎を『自虐が示す虚構のてずま』の産物とうそぶいた作者の自虐の背後にあるものと、露悪趣味の原点を示す作品である。その混沌とした中に、純文学作家から大衆文学作家に転向した作者のすさまじい断念が伝わってくる。 (爆酔するおじさん) 『グレート・ギャツビー』 スコット・フィッツジェラルド著 村上春樹訳
『グレート・ギャツビー』 スコット・フィッツジェラルド著 村上春樹訳
ああ今年はほんとに「これがベスト!」といえる本に出会えなかった。読んだ本が少なかったのも一因でしょうか。
その中で強いて選んだ一冊。ずいぶん前に読んだので、細かいことは忘れました。
村上訳でも「ロング・グッドバイ」は世間で言うほど素晴らしいとは思わなかった。
村上訳が、と言うより、「ロング・グッドバイ」自体が私の好みではないのかも。( アビィ) 『赤朽葉家の伝説』 桜庭一樹
『赤朽葉家の伝説』 桜庭一樹
とりあえず。すごく迷った。実は数年前にマイベストに上げ、今年読み返した「村田エフェンディ滞土録」(梨木香歩)が一番面白かったんだけど、またこれをあげたりしたら、「ジェフィーさんたら、ぼけた」と言われるだろうと思ってあげられなかった。
現在読んでいる「凍」(沢木耕太郎)、「mit Tuba」(瀬川深)あたりがベストにおどり出てくれたらうれしいんだけど。 ( ジェフィー23) 『サクリファイス』 近藤史恵
『サクリファイス』 近藤史恵
自転車のロードレースという競技の魅力を伝えながらミステリー展開で引き込み、読後は「ああこれはひとりの青年の成長物語だったのだな」と感じさせたところ。 (垂ッん) 『星新一』 最相葉月
『星新一』 最相葉月
星新一は、僕の世代では女性に人気があったと思う。
僕は何作かは読んだが、エヌ氏などの命名に抵抗があった記憶がある。
作者は非常に丹念な取材で、星新一を描き、かつSF全盛期のエピソードにも触れて、非常に面白かった。
特に、タモリが伊豆の別荘で星新一を接待する場面は印象的であった。(たで63) 『動物園に入った男』 デーヴィット・ガーネット
『動物園に入った男』 デーヴィット・ガーネット
課題本で「狐になった奥様」を読みデーヴィット・ガーネットにはまりました。「狐になった…」より良かったのが「動物園に入った…」。動物園にヒトが展示されていないのはおかしいと自ら檻に入り展示物「ホモ・サピエンス」として生活する青年。どちらも奇抜な設定にもかかわらす、読ませます。うゎーうまい、小説ってほんとうにおもしろいって久しぶりに感じた作品でした。そして挿絵も良かった。 (KK) 『ヒストリー・オブ・ラブ』 ニコール・クラウス著/村松潔訳
『ヒストリー・オブ・ラブ』 ニコール・クラウス著/村松潔訳
「愛の歴史」というタイトルから、恋愛小説かと思われるだろう。
ポーランド生まれの、大量虐殺を逃れたユダヤ人の男、彼が書いた小説が世界を巡り、ある家族、友人、人と人との因縁を紡ぎだす、人間小説である。
「孤独については、それをまともに受け止められる器官はない・・。」
80歳を過ぎ、身寄りなしの男はそれでも生き続ける。それは、人を愛した思いがあるからだ。
人なんて結局は一人・・、そう語る人は淋しい。愛されることにも背を向ける。
ひとりだからこそ、人を愛し愛されて生きたい。それは、感情を持つ人間だけができることなのだから。
まだ若い著者が描く深い愛の物語から、そんな感想を持った。男の孤独さには落涙。
新潮社の装丁がいまいちで残念だ。秀作なのに損していると思う。(はりゆみ) 『秘花』 瀬戸内寂聴
『秘花』 瀬戸内寂聴
感動したというより印象に残ったという意味で。
この著者でこのテーマ、さぞかし幽玄枯淡の境地を極められたかと思いきや、瀬戸内さんまだまだお若い!あるいは俗欲きわまりて悟りとなすところまで行き着かれたか。 (NT) 『雪沼とその周辺』 堀江敏幸
『雪沼とその周辺』 堀江敏幸
雪沼という土地周辺に暮らす、普通の人々の7つの物語です。
地味だけど、とてもいい小説でした。主人公それぞれが、人間的な存在感
をもって描写されて、まるで実在するかのように感じられました。(ぺぺろん7) 『Op.ローズダスト』 福井 晴敏
『Op.ローズダスト』 福井 晴敏
自衛隊、警察、天下り、汚職、色々からんだアクション小説。新聞を賑わしている、材料をうまく使ってあるのが良かった。 (マタタビ)
欠席された方、未提出の方も追加UPしますので、ベスト本をお知らせください



















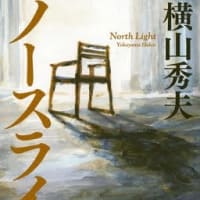






タイトルの文字面から絵文字を決めただけなので、
内容とはズレズレのものがあったら
ごめんなさい、です