何年もアロマをやっているものからすると、精油はブレンドして当たり前・・・という概念でいましたが、初心者の人はまた違ったとらえ方をするものだと思いました。
「精油を混ぜてしまうと効能が減ってしまうことはないんですか?」
と聞かれたので、
「ないとは言い切れません」
と答えたんです。確かにないとは言い切れないので。
「じゃあ、何か効果を期待して使う時は混ぜないで1種類で使った方が効果があるんですね。」
「いえ、そうではないんです。ブレンドした方が効果はあるように思いますよ」
そのあと時間がなくなって上手く説明することができませんでした。
家に帰って関連書を漁り、ネットを漁ってみましたが、これといった答えが得られませんでした。
なんせ、「フレンドする理由」というキーワードで検索してみたら、私のブログが一番上に出てきてしまったくらいなんですから。
確かに精油をブレンドすることによって、ある成分がある成分の効果を消してしまわないという可能性はまったくなくはないと思います。ではそれがどれくらい証明されているのかというと、残念ながら実例が不足しているとしか言いようがありません。研究者は単一の精油の化学的効果効能をマウスや時に人体で実験をしてデータを集めているはずです。ところがブレンドした精油に関してはおそらくデータがないのではないでしょうか。というより単体の精油に対するデータもまだまだ集めきれていない状況にあるのだと思います。
では、アロマの本に書かれているこういう時にはこういうブレンド・・・といったサンプル、あれはおそらくそのセラピストまたは研究者の経験によるものだと思います。ガブリエル・モ―ジェーなどは治療に使う精油は最低5種類、心理的効果を狙うばあいは3種類にとどめる、などと言っています。
なぜブレンドをしなければならないのか?という問い対する答えは主に2つあります。
1つは感覚の麻痺。感覚器のなかでもとりわけ嗅覚というのは環境にすぐに順応してしまう性質を持っています。そのためいつも同じ香りばかりを嗅いでいると、それが刺激にんならないため本来持っていた精油の効果が出づらくなってしまうということ。そのため、例えば他の精油と併せて違う香りを感覚的に変化をつけてあげる必要があるのです。
もうひとつが、症状の多様性。単に頭痛といってもそれが風邪によるものなのか、アレルギーなどの目や鼻の症状からくるものなのか、単なるストレスなのか、歯痛や肩凝りからくるものなのか?ということを見極めてそれに合った精油をあわせなければならないわけです。例えば花粉症からくる頭痛の場合、単に痛みを止めるだけでなく、抗アレルギー作用のあるもの、呼吸器系の働きを強めるもの、アレルギーに抵抗したことでその残骸を排出しるための循環器を促進んする作用や利尿作用などのある精油も併用します。また、クライアントが嫌いな香りを使うと効果が減ってしまう恐れもあるためクライアントの好きな香りを添加するといった意味もあります。
簡単に書いちゃいましたが、これ、結構難しいことです。来週もう一度お話しようと思いますが、どこまでわかっていただけるかちょっと不安です。


↑ポチっとよろしく↑お願いします。
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとことお書きください。コメントのないもの、記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。
「精油を混ぜてしまうと効能が減ってしまうことはないんですか?」
と聞かれたので、
「ないとは言い切れません」
と答えたんです。確かにないとは言い切れないので。
「じゃあ、何か効果を期待して使う時は混ぜないで1種類で使った方が効果があるんですね。」
「いえ、そうではないんです。ブレンドした方が効果はあるように思いますよ」
そのあと時間がなくなって上手く説明することができませんでした。
家に帰って関連書を漁り、ネットを漁ってみましたが、これといった答えが得られませんでした。
なんせ、「フレンドする理由」というキーワードで検索してみたら、私のブログが一番上に出てきてしまったくらいなんですから。
確かに精油をブレンドすることによって、ある成分がある成分の効果を消してしまわないという可能性はまったくなくはないと思います。ではそれがどれくらい証明されているのかというと、残念ながら実例が不足しているとしか言いようがありません。研究者は単一の精油の化学的効果効能をマウスや時に人体で実験をしてデータを集めているはずです。ところがブレンドした精油に関してはおそらくデータがないのではないでしょうか。というより単体の精油に対するデータもまだまだ集めきれていない状況にあるのだと思います。
では、アロマの本に書かれているこういう時にはこういうブレンド・・・といったサンプル、あれはおそらくそのセラピストまたは研究者の経験によるものだと思います。ガブリエル・モ―ジェーなどは治療に使う精油は最低5種類、心理的効果を狙うばあいは3種類にとどめる、などと言っています。
なぜブレンドをしなければならないのか?という問い対する答えは主に2つあります。
1つは感覚の麻痺。感覚器のなかでもとりわけ嗅覚というのは環境にすぐに順応してしまう性質を持っています。そのためいつも同じ香りばかりを嗅いでいると、それが刺激にんならないため本来持っていた精油の効果が出づらくなってしまうということ。そのため、例えば他の精油と併せて違う香りを感覚的に変化をつけてあげる必要があるのです。
もうひとつが、症状の多様性。単に頭痛といってもそれが風邪によるものなのか、アレルギーなどの目や鼻の症状からくるものなのか、単なるストレスなのか、歯痛や肩凝りからくるものなのか?ということを見極めてそれに合った精油をあわせなければならないわけです。例えば花粉症からくる頭痛の場合、単に痛みを止めるだけでなく、抗アレルギー作用のあるもの、呼吸器系の働きを強めるもの、アレルギーに抵抗したことでその残骸を排出しるための循環器を促進んする作用や利尿作用などのある精油も併用します。また、クライアントが嫌いな香りを使うと効果が減ってしまう恐れもあるためクライアントの好きな香りを添加するといった意味もあります。
簡単に書いちゃいましたが、これ、結構難しいことです。来週もう一度お話しようと思いますが、どこまでわかっていただけるかちょっと不安です。

↑ポチっとよろしく↑お願いします。
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとことお書きください。コメントのないもの、記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。











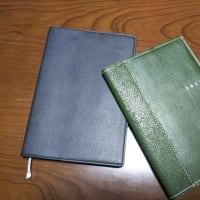















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます