いつも学科を受けてる先生とは別の先生が担当してくださったのですが、こちらの先生はテンションが高い。しかもアイコンタクトを頻繁にとるので目が離せない。自分が教壇に立っているときはどちらかというと視線を合わせない、というか合わせられないほうなのでアイコンタクトの重要性を身をもって感じました。
聞くところによると前回のパレ原宿のインストラクター試験合格率は85%だとか。取り立てて試験対策に力を入れている学校でもないので、いかに先輩達が努力しているかが窺える。学校の方針としては試験よりもその後の実践にむしろ重要視している。
認定校に属していると二次試験が免除されるが、本来インストラクターは不特定多数の人の前で自分の考えを語らなければならない立場なので、二次試験があったほうがいいと先生は言ってました。確かにNARDのインストラクター試験には口答試験といって口頭で試験管の前で説明する制度があるようです。
インストラクターの独自性を考えると、その制度は理にかなっていると思います。AEAJの場合協会ではセラピストとインストラクターはそれぞれ異なる性質の資格だと述べていますが、現状インストラクター資格の上にセラピスト資格が乗っかってる印象をゆがめません。特にパレ原宿の場合はほぼ全員がセラピストを目指しているので、インストラクター試験はセラピスト試験のワンステップと考えている人が主流です。
勉強方法についてのアドバイスでは、問題集がいろんな出版社から発行されているが、あまりそれに惑わされないよう言われました。勉強の仕方がわからない人ほど問題集に頼る、授業の内容と協会発行の印刷物(資格マニュアルや検定問題集)をじっくり読んだほうがいいと言い渡されました。おっしゃってることは理解できるのですが・・・どうしても問題集で何点取れたか・・・というのが気になってします。
それからインストラクター試験には解剖生理学の出題数がそれほどないので、解剖生理学ばかり重点的に勉強してしまうと他が手薄になってしまうので気をつけるよう言われました。むしろ精油学などのアロマ学科や歴史をしっかりやったほうがいいと。
解剖生理学に関しては私も前回最も手を焼いた領域なので、言われてみればそうだなと思う反面、そういわれても・・・という気にもなります。勉強の手順にも問題があるのだと思います。
インストラクター試験に出てくる解剖生理学は皮膚、身体の発生、脳神経系、内分泌系、免疫系、嗅覚。私は今回セラピスト関連の呼吸器、循環器、消化器などを先に勉強したのでそれがよかったのだと感じてます。実はここに上げた中で内分泌や免疫って難しい領域だと思うのです。先に呼吸器や循環器などのからだのしくみを学習したほうが内分泌や免疫は理解しやすいのです。
もう、試験日も迫っているので時間はないのですが、理系が苦手な人ほど試験範囲だけを重点的にやるより、先に『目でみるからだのメカニズム』などでからだのしくみをしっかり把握してから試験問題を解いたほうがいいと思います。急がば回れで。


↑ポチっとよろしく↑お願いします☆
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとこと感想をお書きください。コメントのないもの及び記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。
聞くところによると前回のパレ原宿のインストラクター試験合格率は85%だとか。取り立てて試験対策に力を入れている学校でもないので、いかに先輩達が努力しているかが窺える。学校の方針としては試験よりもその後の実践にむしろ重要視している。
認定校に属していると二次試験が免除されるが、本来インストラクターは不特定多数の人の前で自分の考えを語らなければならない立場なので、二次試験があったほうがいいと先生は言ってました。確かにNARDのインストラクター試験には口答試験といって口頭で試験管の前で説明する制度があるようです。
インストラクターの独自性を考えると、その制度は理にかなっていると思います。AEAJの場合協会ではセラピストとインストラクターはそれぞれ異なる性質の資格だと述べていますが、現状インストラクター資格の上にセラピスト資格が乗っかってる印象をゆがめません。特にパレ原宿の場合はほぼ全員がセラピストを目指しているので、インストラクター試験はセラピスト試験のワンステップと考えている人が主流です。
勉強方法についてのアドバイスでは、問題集がいろんな出版社から発行されているが、あまりそれに惑わされないよう言われました。勉強の仕方がわからない人ほど問題集に頼る、授業の内容と協会発行の印刷物(資格マニュアルや検定問題集)をじっくり読んだほうがいいと言い渡されました。おっしゃってることは理解できるのですが・・・どうしても問題集で何点取れたか・・・というのが気になってします。
それからインストラクター試験には解剖生理学の出題数がそれほどないので、解剖生理学ばかり重点的に勉強してしまうと他が手薄になってしまうので気をつけるよう言われました。むしろ精油学などのアロマ学科や歴史をしっかりやったほうがいいと。
解剖生理学に関しては私も前回最も手を焼いた領域なので、言われてみればそうだなと思う反面、そういわれても・・・という気にもなります。勉強の手順にも問題があるのだと思います。
インストラクター試験に出てくる解剖生理学は皮膚、身体の発生、脳神経系、内分泌系、免疫系、嗅覚。私は今回セラピスト関連の呼吸器、循環器、消化器などを先に勉強したのでそれがよかったのだと感じてます。実はここに上げた中で内分泌や免疫って難しい領域だと思うのです。先に呼吸器や循環器などのからだのしくみを学習したほうが内分泌や免疫は理解しやすいのです。
もう、試験日も迫っているので時間はないのですが、理系が苦手な人ほど試験範囲だけを重点的にやるより、先に『目でみるからだのメカニズム』などでからだのしくみをしっかり把握してから試験問題を解いたほうがいいと思います。急がば回れで。


↑ポチっとよろしく↑お願いします☆
※トラックバックを送られる方は、コメント欄にひとこと感想をお書きください。コメントのないもの及び記事の内容と関連のないものは削除させていただきます。











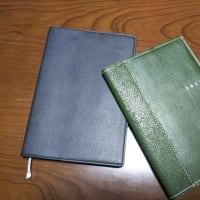
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます