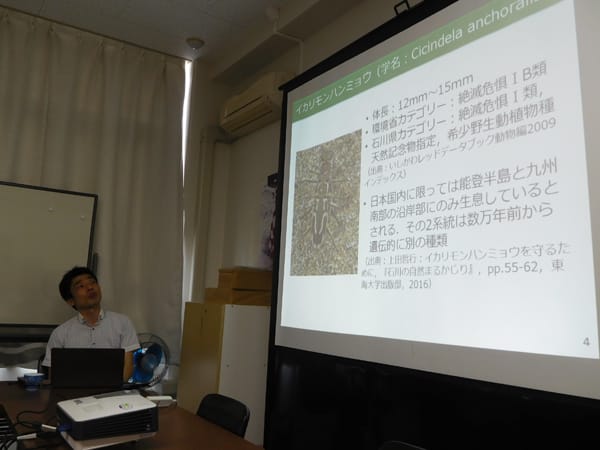里山をテーマに角間里山ゼミ会を
毎月開催しています。
12月の角間里山ゼミ会として、今日は以下を学び合いました。
と き:12月19日(木)15時~17時
ところ:石川県自然史資料館
テーマ:「金沢市の生物文化多様性による
新しいコモンズの創出ー 保全・基礎ー」
講 師:フアンさん
(Dr. Juan PASTOR IVARS、スペイン出身、建築学)
◎金沢にある国連大学のブランチであるOUIKの研究 員。
金沢にある伝統庭園の研究と保全に取り組んでいます。
とくに庭園にある池と水系の生物多様性に関心を持ち、
曲水庭 園に関する研究を行っている。


フアンさんが研究されているお話を聞いたあとに質疑応答し、
最後に全員に感想を出してもらいました。
金沢で生活していてもなかなか庭園を訪れる機会は少ないのですが、
スペイン人であるフアンさんのお話を聞いて、
改めて金沢の緑地や庭園に視点が向き、
その貴重さを考えてみることができました。
「例え人工的に作られた場所であったとしても、
そこに自然は存在する」・・という意味の言葉を思い出しました。
14人が集まり、最後まで熱気のあるゼミ会となりました。

午前は,金沢市の中心を流れる犀川で
NHKの取材を受けました。テーマは,犀川と野鳥。
記者がこのほとりに在住でかなりの野鳥ファンの方のようでした。