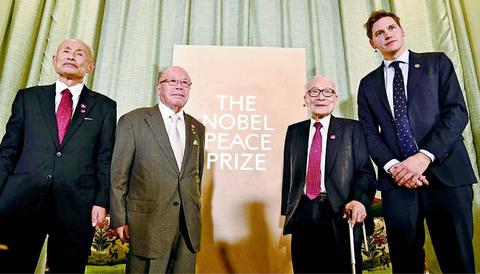衆院政治改革特別委 塩川氏が主張
 (写真)意見表明する塩川鉄也議員=10日、衆院政治改革特別委 |
衆院政治改革特別委員会が10日開かれ、政治改革に関して政治資金規正法改定に向け各党が意見表明を行いました。日本共産党の塩川鉄也国対委員長は「政治改革の根幹は企業・団体献金の禁止だ」と主張しました。(塩川議員の意見表明)
塩川氏は「この臨時国会は、総選挙での国民の審判に応え、自民党の裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃にどう取り組むのかが問われている」と述べました。裏金の原資は企業・団体からのカネであり「『企業・団体献金禁止せよ』が国民の声だ」として、企業献金に固執する自民党の姿勢を批判。1994年の「政治改革」関連法でつくられた「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」という企業・団体献金の「二つの抜け道をふさぐことこそ行うべきだ」と強調しました。
また、政治資金は主権者である「国民の浄財」で支えられるもので、国民一人ひとりの政党への寄付は、国民の選挙権・投票権と結びついた「国民固有の権利」だと指摘。一方「企業・団体献金は本質的に政治を買収する賄賂で、国民の参政権を侵害する」と批判し、「営利目的の企業が個人をはるかに超える巨額の金の力で政治に影響を与えれば、政治が大企業に向けたものになる」「国民主権を貫くためにも禁止が必要だ」と述べました。
立憲民主党、日本維新の会、有志の会なども企業・団体献金の禁止を主張。自民党・公明党は企業献金禁止に触れませんでした。
政党から議員個人に支出され使途不明の政策活動費について、共産党など6会派は、共同提出した政策活動費禁止法案の成立を求めました。自民党は政策活動費を廃止と言いながら外交上や営業の秘密などに関する支出は「公開方法工夫支出」として形をかえて温存する案を示しました。