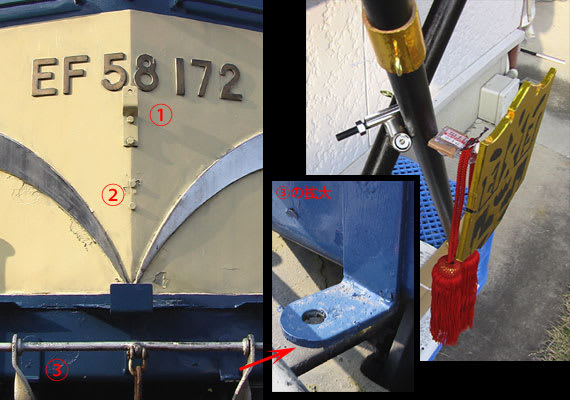国道17号バイパスを高崎方面に走っていく途中、
国道407号とクロスする手前で、なんだか怪しげな遊歩道?をまたぎます。
前々から気にはなっていたのですが、なんかの廃線跡なのでは?とふと頭をよぎったのでした。
秩父鉄道1007編成ラストランの待機中に、スマホで調べてみるとビンゴ!
それはまさに東武鉄道熊谷線、通称「妻沼線」(昭和58年廃止)という廃線跡だったのでした。
さらに調べてみると、妻沼展示館に当時の車両が静態保存されていることが判明。
せっかくなので廃線跡をたどって訪れてみました。
妻沼展示館の北側にひっそりとたたずむキハ2002
東武鉄道としては珍しい気動車で、キハ2000系を名乗っていたそう。
東急車輛製で2001~2003の3両が在籍していました。
鹿島鉄道でも似た車両がありましたね。
車内を見学することも可能です。(鍵が閉まっていなければ)
運転台。時速65kmで走っていたようだが、速度メーターは120km/hまである 
古めかしい車内。映画でも使えそうな雰囲気 
検査はかつての杉戸工場で行なわれていたことがわかる
ということは、妻沼~熊谷~羽生~東武動物公園と検査入出場していたことになるわけで。
秩父鉄道はデキ牽引か?と思って画像検索してみると・・・
熊谷線キハ2003の回送(東武鉄道想い出の73・78型さまのブログより)
これは魅力的・・・。
 妻沼展示館はこちら
妻沼展示館はこちら








































 おまけ
おまけ 



 おまけ
おまけ 







































 宮島・厳島神社
宮島・厳島神社 



















 おまけ
おまけ 

 してきました。当記事ではその“過酷”なコースを時系列に沿って、もしかしたら役に立つ情報とともにご紹介していきたいと思います。
してきました。当記事ではその“過酷”なコースを時系列に沿って、もしかしたら役に立つ情報とともにご紹介していきたいと思います。


 平等院鳳凰堂
平等院鳳凰堂 





 日本海を撮影し、いざ京都へ。10:30頃の駅前バスターミナルは観光客と修学旅行の生徒でごったがえしていました。あらかじめ前日に500円の「市バス専用一日乗車券カード」を購入しておいて正解でした。
日本海を撮影し、いざ京都へ。10:30頃の駅前バスターミナルは観光客と修学旅行の生徒でごったがえしていました。あらかじめ前日に500円の「市バス専用一日乗車券カード」を購入しておいて正解でした。
 清水寺
清水寺 

 平安神宮
平安神宮 

 銀閣寺
銀閣寺 
 11分後の次のバスに乗車して
11分後の次のバスに乗車して 同志社前で下車しました。すると、、、そこは女子大じゃないか
同志社前で下車しました。すると、、、そこは女子大じゃないか なんだかんだ10分遅れでやってきたこのバス、地元民に愛用されているのかこの先も全部のバス停に停車…。金閣寺に着いたのは、20分も遅れて15:05をまわっていました。
なんだかんだ10分遅れでやってきたこのバス、地元民に愛用されているのかこの先も全部のバス停に停車…。金閣寺に着いたのは、20分も遅れて15:05をまわっていました。





 祇 園
祇 園 
 。なんか嫌そうな顔の舞妓さんたち…。見ていてかわいそうになってしまいました。一言声をかければいいものを。彼女らは見世物じゃない、僕らと同じ人間ってのがわからないんですかね
。なんか嫌そうな顔の舞妓さんたち…。見ていてかわいそうになってしまいました。一言声をかければいいものを。彼女らは見世物じゃない、僕らと同じ人間ってのがわからないんですかね 笑
笑
 。
。 渡月橋
渡月橋 
 竹 林
竹 林