◆しばらく小笠原のM8・9とM8・5の続いた地震について考えていましたが、これらも宇宙人による米軍兵器へのアタックだと思って間違いないと思います。アメリカでは、このような記事がたくさん出ているようですが、宇宙への旅立ちブログしか、今のところ日本語で紹介されているサイトはないですね。日本にも宇宙人のアタックが行われるというのは、それなりの物があるってことです。
小笠原諸島は江戸時代に日本により統治された島ですが、海外の船の補給地として重要な拠点となっていたわけです。アメリカが統治後、日本に返還されましたが、そこには核兵器が隠されていたという、恐ろしい事実がありました。日本政府はむろん知っていたでしょう。沖縄と同じように、本土とは切り離されて、黙認されていたはずです。佐藤栄作の「核の三原則」は嘘でした。やはり左翼がその頃騒いでいたのは、本当に核が日本に持ち込まれていたからでした。
また、もう一つ気になることは、気象庁が全国に広がっている地震であると発表したことです。今までは震度1は計測されても、テレビで報道されることはありませんでした。気象庁は何かを知っていると思います。しかしどちら側なのかは、まだわかりません。
このように地震はこれからも、起きると思われます。ですから注意することは同じだとおもいますが、東日本大震災のような大災害は起きないと私は推察しています。
ここに紹介した文には、現在も核兵器が置かれているとは、書かれていません。しかしかつて置かれていたものが本当に持ち去られているのかどうかは、わかりません。
それに硫黄島は実際、アメリカ軍と自衛隊だけが使っている島です。小笠原諸島の南に位置する硫黄島は、今だに、謎が多いです。滑走路の下に遺骨が見つかったとも、あるいは地下基地の地図が見つかったという情報は過去にありました。
また、記事の写真は真新しいような入口のドアですよね。ステンレス製でしょうか。鉄なら錆びてしまうから、海の塩風から防ぐために、作られたに違いないのです。よほど長期にわたって中を保護するつもりの穴がここにあると思います。
~~~~~~~~~~~~
ウキペディアより転載しました。http://ja.wikipedia.org/wiki/小笠原諸島
米軍施政下の小笠原[編集]
米軍政時代にはアメリカ海軍の基地が設置され、物資の輸送は1か月に1回グアム島からの軍用船によって行われた。欧米系住民は戦前の土地区画に関係なく決められた区画に集められ、その多くは米軍施設で働いた。島民の自治組織として五人委員会が設けられた。島の子供たちは、軍の子弟のために1956年に設立されたラドフォード提督初等学校で軍の子弟と一緒に学び、高等教育はグアム島で行われた。米軍によって戦前の土地区画に関係なく決められた区画に集められたことは、日本返還後も効率的な開発の都合から踏襲され、戦前の土地所有者との補償交渉で揉める[8]こととなった。後に、日本政府の意向を無視して父島に核兵器の貯蔵施設が作られていたことがアメリカの情報公開によって知れ渡った[8]。軍政時代に数基の核弾頭が保管されていた[8]という。1950年代にも国務省が小笠原の日本返還を検討したが、アメリカ海軍を始めとする国防総省が反対したため、頓挫[8]した。その理由は核兵器の保管が理由[8]だったという。返還後、欧米系住民の子弟は、日本語教育の困難な問題により米国に移住した者もいた。
入植の歴史[編集]
19世紀初頭林子平の『三国通覧図説』から小笠原諸島がボニン・アイランズ(Bonin Islands)としてヨーロッパへ紹介されると、各国の船舶が小笠原諸島へと寄港するようになる。
1827年イギリス海軍のブロッサム号を率いるフレデリック・ウィリアム・ビーチーが現在の父島二見港から上陸すると、前年行方不明となったイギリスの捕鯨船ウィリアム号の乗組員2人と遭遇し、他国の船も来航していることを知る。ビーチーは島の領有宣言板を島内の木に打ち付け島を離れる。ビーチーより小笠原諸島の存在の報告を受けた在ホノルルイギリス領事は、ボニン・アイランズへの入植計画を進め、1830年欧米人とハワイ人による入植団をつくり現在[いつ?]の父島へ入植を果たす。この後も各国の船舶は、水や食料を確保したり病人を下船させるなど、様々な目的で頻繁に小笠原諸島に寄港する。
小笠原に漂着し外国船に助けられた日本人から伝わる情報や、ペリーの「小笠原諸島に関する覚書」におけるこの地への評価から、小笠原諸島は幕府首脳の関心を引く。1861年江戸幕府は列国公使に小笠原の開拓を通告する。1862年1月(文久元年12月)外国奉行水野忠徳の一行が咸臨丸で小笠原に赴き、外国人島民に日本が管理することを告げる。その後八丈島から日本人の入植者が送りこまれ開拓が始まる[18]。
- 外国人の入植については「欧米系島民」を参照
- ...........................................
- http://www.iwojima.jp/ogasa2.html#futami
- 小笠原・火山(硫黄)列島の歴史より転載しました。
- http://www.iwojima.jp/futami.html
- 二見海軍燃料貯蔵場(清瀬重油槽)
-
軍の補給拠点としての小笠原の歴史は、大正6年(1917)12月、二見海軍貯炭場が設置されたことに始まる。貯炭場が設置された場所は現在 の小笠原水産センターの付近である。ところが、第一次世界大戦の終了後、艦船の燃料は石炭から石油に移行していき、昭和の初期には主要艦船の汽罐が換装さ れた。このため昭和3年(1928)4月、貯炭場は横須賀海軍軍需部・二見燃料貯蔵場と改称されて重油の補給を行うことになった。
 その後、海 軍の増強や作戦計画の変更に伴い石油の必要量が増加したことから、二見燃料貯蔵場では需要に対処しきれなくなった。加えて秘匿性や抗堪性(耐弾性)も確保 するため地下式の設備が計画された。昭和12年(1928)に父島清瀬にこの写真にあるような重油槽が建造され、二見海軍燃料貯蔵場はここに移転した。
その後、海 軍の増強や作戦計画の変更に伴い石油の必要量が増加したことから、二見燃料貯蔵場では需要に対処しきれなくなった。加えて秘匿性や抗堪性(耐弾性)も確保 するため地下式の設備が計画された。昭和12年(1928)に父島清瀬にこの写真にあるような重油槽が建造され、二見海軍燃料貯蔵場はここに移転した。
高台の下に造られた地下洞窟式の重油槽は全部で3本あり、扉は半径2mあまりの半円形である。内部は幅10m、高さ10m、奥行き40mあ り、1槽につき300万リットル、全部で900万リットル(約8100トン)の重油を貯蔵することができた。これは当時の主力駆逐艦(燃料搭載量 400~650トン)なら12~20隻分、5,500トン級軽巡洋艦(燃料搭載量1260トン)なら6隻分の燃料をまかなえる規模である。戦艦や大型空母 (搭載量5000~6300トン)になると1隻にしか給油できないが、大型艦は航続距離が長いので父島で補給しなくても問題は少ないであろう(実際には艦の燃料タンクが空になる前に給油するので、補給可能な艦数はこれより多いことになる)。
昭和14年(1939)に小笠原近海で行われた海軍演習の際には、空母「赤城」を含む多くの艦艇が二見港に入港している。この時にこの貯蔵場から給油を受けた艦艇もあるだろう。
このタイプの重油槽は国内にこれしか現存せず、土木技術史上からも重要な戦跡といわれる。現在、この場所には都立小笠原高校が建てられてお り、施設は校舎の建つ高台の下にある。
(写真は平成15年9月に作者撮影)
この貯蔵場は昭和19年(1944)2月に父島軍需支庫と改称された。
 終戦後、小笠原は全域が米軍の占領下に置かれたが、硫黄島を除き、米軍は1946年10月に撤収した。その後は父島に帰島を許された欧米系島民のために海軍の船がグアムから年に数回訪れるだけとなった。
終戦後、小笠原は全域が米軍の占領下に置かれたが、硫黄島を除き、米軍は1946年10月に撤収した。その後は父島に帰島を許された欧米系島民のために海軍の船がグアムから年に数回訪れるだけとなった。
ところが、朝鮮戦争(1950~53)をきっかけにして小笠原の位置づけは急変する。その後の米ソ対決へと国際情勢の緊張が進む中、小笠原は日本本土の米軍基地とグアムの基地との中間に位置する拠点としての重要さを増すことになった。小笠原は日本国内や沖縄の米軍基地を支援する拠点である「二次的基地(secondary base)」と位置づけられたのである。1951年には米海軍が父島に再び配備された。万一、朝鮮戦争が東西の全面戦争に発展して日本国内の基地がソ連の攻撃により使用不能になった場合に備え、小笠原地域に数万単位の兵員を配置できるよう、硫黄島を中心に大掛かりな兵舎や施設の建設も行われたほどである。 硫黄島返還時にはこれらの施設が残っていたので、「米軍は硫黄島に1万人以上の兵員を常駐させていた」との説が出されたが、実際に配備されたことはなかっ た。
その中で、この施設周辺も米海軍によって新たに利用されることになった。その利用法とは「核兵器の貯蔵」である。父島の奥村地区にて核兵器の 貯蔵が行われており、二見港内に米潜水艦が入港する時には島民(当時は欧米系のみ)が周辺に近づくことは禁止されていた。加えて、当時は硫黄島にも核爆弾が配備されていたのである。
なお、以前はこの貯蔵所内に核爆弾が格納されていたとされており、当サイトでもそのように記述していましたが、「その後の調査で核兵器の貯蔵 所は同じ 山ではあるがもっと奥の方にあったことが判明している」と、ロバート=D=エルドリッヂ氏から御教示がありました。また、核兵器が父島に貯蔵されていたこ と について、全国紙などで大きく報道されたのは2000年だが、欧米系島民の間では返還時にすでに常識になっていたと、吹浦忠正氏の御指摘がありました。両氏に厚く御礼申し上げます。
小笠原を日本に返還することや本土に強制疎開となった旧島民の帰還について、米国務省は日米関係重視の視点から前向きであったが、国防省・海軍の反対により1950年代には実現しなかった。その理由が核兵器の配備に関係していたことはほぼ間違いのないところであろう。
だが、核戦略・戦術の変化により、60年代には小笠原・硫黄島の核兵器も撤去されたといわれる。そしてこのことが1968年(昭和43)の小笠原返還にもつながっていったのである。










 The White House
The White House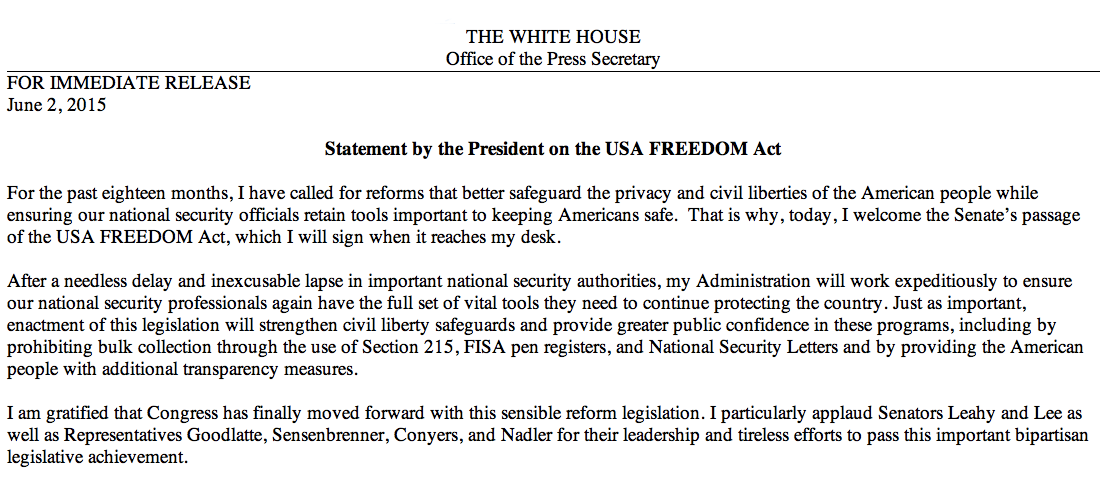
 ナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。また、長時間の運動による筋肉の痙攣などを防ぐ働きもあります。
ナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。また、長時間の運動による筋肉の痙攣などを防ぐ働きもあります。
 その後、海 軍の増強や作戦計画の変更に伴い石油の必要量が増加したことから、二見燃料貯蔵場では需要に対処しきれなくなった。加えて秘匿性や抗堪性(耐弾性)も確保 するため地下式の設備が計画された。昭和12年(1928)に父島清瀬にこの写真にあるような重油槽が建造され、二見海軍燃料貯蔵場はここに移転した。
その後、海 軍の増強や作戦計画の変更に伴い石油の必要量が増加したことから、二見燃料貯蔵場では需要に対処しきれなくなった。加えて秘匿性や抗堪性(耐弾性)も確保 するため地下式の設備が計画された。昭和12年(1928)に父島清瀬にこの写真にあるような重油槽が建造され、二見海軍燃料貯蔵場はここに移転した。 終戦後、小笠原は全域が米軍の占領下に置かれたが、硫黄島を除き、米軍は1946年10月に撤収した。その後は父島に帰島を許された欧米系島民のために
終戦後、小笠原は全域が米軍の占領下に置かれたが、硫黄島を除き、米軍は1946年10月に撤収した。その後は父島に帰島を許された欧米系島民のために





