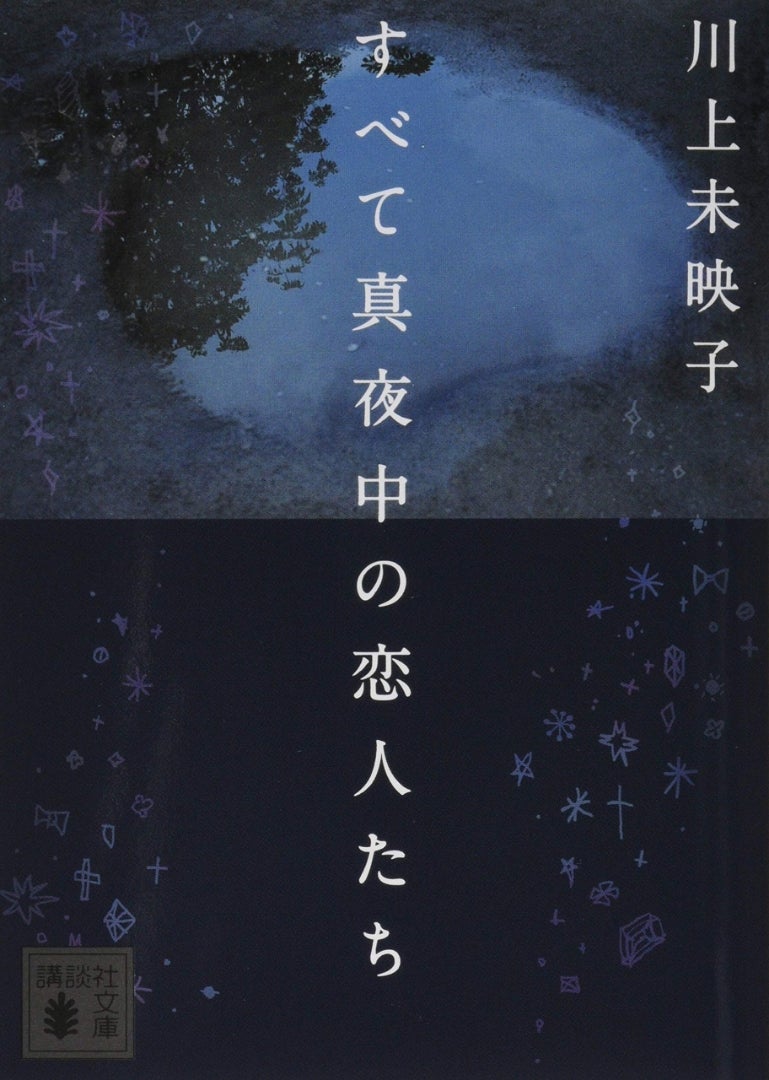小川洋子(1962年〜) 岡山市生まれ
は、1990年の「妊娠カレンダー」で芥川賞を受賞
以前、1994年の「薬指の標本」を読んで感動しましたが、同年に「密やかな結晶」も出版されていたんですね…
物語は、
『その島では、記憶が少しずつ消滅して いく。鳥、フェリー、香水、そして左足。何が消滅しても、島の人々は適応し、 淡々と事実を受け入れていく。小説を書くことを生業とするわたしも、例外では なかった。ある日、島から小説が消えるま では・・・・・・。 刊行から25年以上経った今も なお世界で評価され続ける、不朽の名作。』文庫本背表紙より
『その島では、記憶が少しずつ消滅して いく。』とは、島の人々に共通して、ある言葉とその概念が消えてしまうのです。例えば、「香水」だとすると、その香りはもちろん、何のためのものか、それにまつわる個人的記憶=物語まで消えてしまい、“小瓶に入ったただの水”になってしまうのです
住民は最初は戸惑い、懐かしがったりするが、“消えてしまったもの”は意味がない、しょうがないと、川に流したり、焼いたりして、二三日後にはそのことさえ忘れてしまい、誰も気にかけない
島の住民の中に少数だが記憶が無くならない特別な人がいる
記憶に関わる事を取り締まる「記憶狩り」を実行する秘密警察、に連行されて亡くなった“わたし”の母もその一人だ
毎日、何かが消えて行く島で
“わたし”の両親は亡くなり、兄弟もなく一人で暮らしている
“わたし”は小説家で、これまでに3冊の本を出した
3冊とも“何かをなくす”テーマだ
“わたし”が今書いている小説は、タイピストとその恋人の物語
“わたし”の担当の編集者R氏は、記憶をなくさない人だった
やがて、R氏は秘密警察にマークされ“わたし”が自分の家の秘密の部屋に匿うことになる…
小川洋子はこの小説を書くにあたって、「アンネの日記」をいつも手元に置いていたそうだ
ある日突然、ナチスドイツによって消されていくユダヤ人の記憶とユダヤ人自身
街の人々は、最初は理不尽さに憤ったが、次第に見て見ぬふりで無かったことと、無関心に慣れていく
アンネは、隠れ家で日記を書き、記憶を物語として残すことで、何もかも奪っていく「ナチス・ドイツ」へ抵抗した
「アンネの日記」が「密やかな結晶」の重要なモチーフになっている
私は一つの読み方として、
小川洋子は本質的に「エロティシズム」の小説家であり
密やかな結晶は、性的な言葉や
性的な表現を意識的に排除して
人間の無意識にあるサディズム、マゾヒズムを物語にひそませているのではないかと思っている それは、性的でもあり政治的でもある
“わたし”が書いているタイピストとその教師で恋人の物語では、彼によって、わたしの声が奪われ、言葉を打つタイプも壊れてしまう
彼によって塔の秘密の部屋に監禁され、彼が作った服を着せられ、煌々とした電灯の下、全裸にされ体の隅々まで彼にふかれる、彼が好きなように何でもされる、しかし、わたしはその部屋から逃げ出そうとはせず、ひたすら彼の登場を待っている
ついに、わたしは彼の言葉以外は理解できない、まさしく「彼のモノ」になってしまう
一方、小説家の“わたし”は、出産をひかえた妻がいるR氏を秘密警察から守るため、妻から引き離し、自宅の秘密の部屋に匿う
毎日、食事の世話をし、トイレの水をたし、体を洗うお湯を用意し、洗濯をする
書きかけの小説をR氏に見てもらうため秘密の部屋に行く
“わたし”はタイピストの小説を執筆していたが、ついに「小説」が消滅した
R氏は消えたものは、こころの奥底に沈んでおり(無意識領域)、頭で考えるのではなく手を動かして拾い上げる(自由連想法・自動記述)、精神分析医の手法で執筆をすすめる
島に地震は発生した日、“わたし”とR氏は結ばれる
“わたし”は秘密の部屋と会話のため繋がっているパイプに耳を添え、R氏がタライの湯で体を洗う音を聞き、R氏の体の部位を一つづつ思い出す…
サディズム、マゾヒズムが直接的な言葉を避け、端麗な文章で描かれる
作品には、精神分析の影が色濃く漂う、たとえば、“わたし”が書く小説の主人公は、七、八歳の時、従兄の男の子と廃墟の高い燈台の階段を上っていく、主人公の女の子は下にいる男の子にスカートの中を覗かれる事に気が気でないが、下を観ることが怖い… 「昼顔」のトラウマのようだ
フロイト、ユングならば、即座に分析し性的な意味付けを行うだろう
そして、人間が、生きるために必要な物語(化)がもつ重要性、“死に至るまでの生の称揚・エロティシズム”(バタイユ)と、モノ・無機質を志向する“死の欲動・タナトス”(フロイト)が描かれている
それは、川端康成が描く“魔界”にも通じる
いろいろな読み方ができる
小説であり、稀な傑作だと思う
★★★★★
ランキングに挑戦中
下のボタンを2つ、ポチッ、ポチッと押して頂けると嬉しいです!