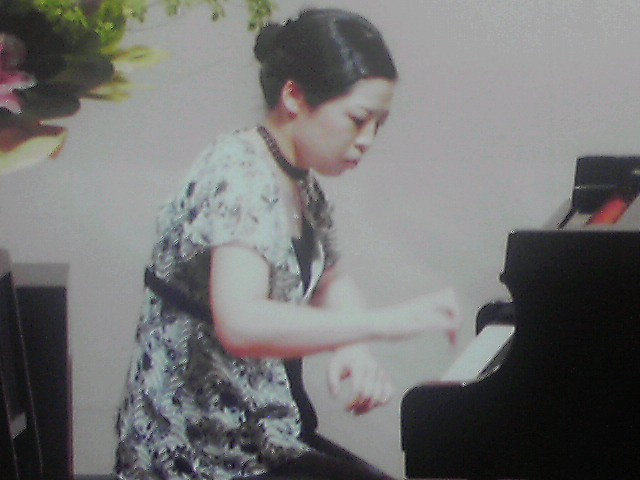お盆休み、皆さんはどのように過ごされましたか?
お盆を過ぎたら、なんだかあっという間に秋の気配で、朝晩は肌寒いくらいです
この前までの暑さはいずこへ・・・
さて、私はお盆中はお墓参りにも行ったりしましたが、近場へちょこちょこと出かけました

アートにも触れて来ましたよ~
宇都宮美術館『パウル・クレー展』
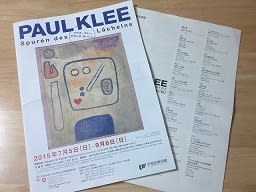
絵の中に込められているメッセージが謎めいているものもあり、
また、音楽記号なども隠されていて、面白かったです。
ポストカード

美術館へ向かう歩道も、気持ちの良い散歩コース


そして、渋谷のBunkamuraでの『エリック・サティとその時代展』

サティの作品はもとより、彼が生きたその時代のアーティストに関する展示もあり、興味深いものでした。
いつの時代も、様々な分野のアーティストが、お互いに影響し合っていたんですね
バレエ『パラード』のビデオ上映や、ピアノ組曲『スポーツと気晴らし』の楽譜を映し出しながらの演奏(録音)もありました。
サティの作品には、楽譜の中に詩が書かれているものもあるのですが、『スポーツと気晴らし』も然り、
ちょっと変わった面白い作品です。
面白いなと思って、かなり前ですが楽譜を買っていたんですよね。
少しお見せしましょう。久しぶりに出しました
表紙。全音から普通に買えました。『スポーツと気晴らし』だけが収録されてます。
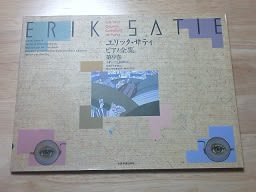
ページをめくると・・・挿絵等は当時のまま。
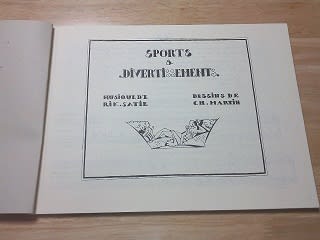
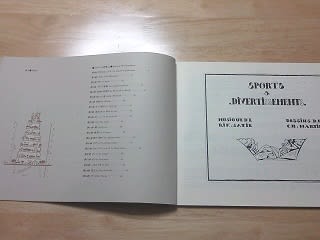
ここから先は、ご興味おありになる方は、楽譜屋さんへどうぞ。
音源も出てますので♪
《おまけ・ミュージアムショップで買ったお土産》
サティと言えばChat noirですね(これはメモ帳)。マスキングテープと珈琲。

マスキングテープの絵は・・コクトーが描いたもの。
サティの姿もあります。

もったいなくてまだ使ってません(笑)
どちらの展覧会も間もなく会期末ですが、ご興味ある方は足を運んでみて下さいね
ランキング参加してます
ポチッとクリックお願いします





恐れ入りますが、当ブログの本文・画像等の無断引用並びに転載は、固くお断り致します。
また、リンクご希望の場合も、予めご連絡下さいますよう、併せてお願い致します。
皆さまのご理解・ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。
お盆を過ぎたら、なんだかあっという間に秋の気配で、朝晩は肌寒いくらいです

この前までの暑さはいずこへ・・・
さて、私はお盆中はお墓参りにも行ったりしましたが、近場へちょこちょこと出かけました


アートにも触れて来ましたよ~

宇都宮美術館『パウル・クレー展』
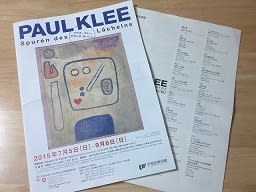
絵の中に込められているメッセージが謎めいているものもあり、
また、音楽記号なども隠されていて、面白かったです。
ポストカード

美術館へ向かう歩道も、気持ちの良い散歩コース


そして、渋谷のBunkamuraでの『エリック・サティとその時代展』

サティの作品はもとより、彼が生きたその時代のアーティストに関する展示もあり、興味深いものでした。
いつの時代も、様々な分野のアーティストが、お互いに影響し合っていたんですね

バレエ『パラード』のビデオ上映や、ピアノ組曲『スポーツと気晴らし』の楽譜を映し出しながらの演奏(録音)もありました。
サティの作品には、楽譜の中に詩が書かれているものもあるのですが、『スポーツと気晴らし』も然り、
ちょっと変わった面白い作品です。
面白いなと思って、かなり前ですが楽譜を買っていたんですよね。
少しお見せしましょう。久しぶりに出しました

表紙。全音から普通に買えました。『スポーツと気晴らし』だけが収録されてます。
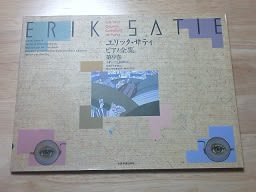
ページをめくると・・・挿絵等は当時のまま。
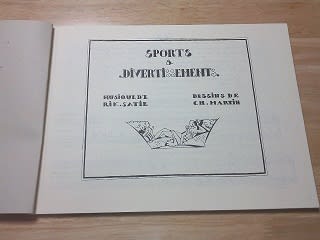
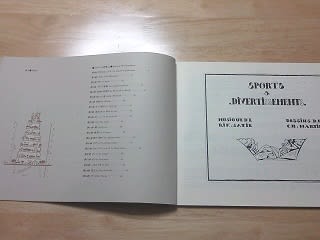
ここから先は、ご興味おありになる方は、楽譜屋さんへどうぞ。
音源も出てますので♪
《おまけ・ミュージアムショップで買ったお土産》
サティと言えばChat noirですね(これはメモ帳)。マスキングテープと珈琲。

マスキングテープの絵は・・コクトーが描いたもの。
サティの姿もあります。

もったいなくてまだ使ってません(笑)
どちらの展覧会も間もなく会期末ですが、ご興味ある方は足を運んでみて下さいね

ランキング参加してます
ポチッとクリックお願いします






恐れ入りますが、当ブログの本文・画像等の無断引用並びに転載は、固くお断り致します。
また、リンクご希望の場合も、予めご連絡下さいますよう、併せてお願い致します。
皆さまのご理解・ご協力、何卒よろしくお願い申し上げます。
















 )
)


 習ったはずのステップも忘れてたり・・
習ったはずのステップも忘れてたり・・
 だな~と、改めて実感。。。
だな~と、改めて実感。。。 でもある)
でもある) と、一番びっくりしたのは、古楽器の組み立てキットが紹介されているページ・・・
と、一番びっくりしたのは、古楽器の組み立てキットが紹介されているページ・・・
 と思ってしまいます(苦笑)。
と思ってしまいます(苦笑)。
 (笑)
(笑)

 』とも呼ばれた、フランス国王・ルイ14世です。
』とも呼ばれた、フランス国王・ルイ14世です。


 と思っていました
と思っていました