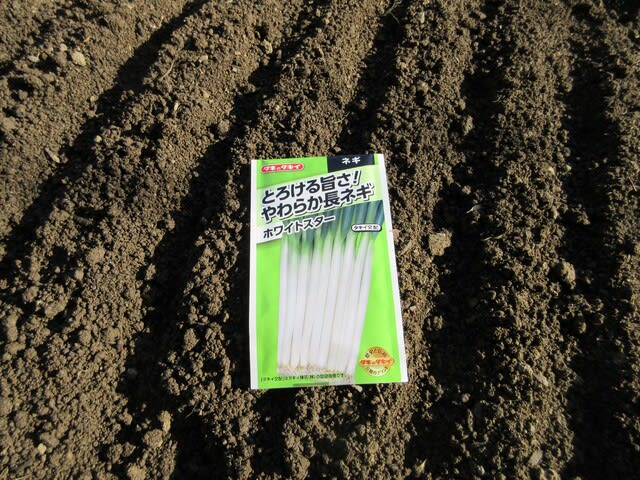春播き長ネギを植付けました。
種播きは3月末。以前はもっと早く播いていましたが、今はあまり早播きはしません。
品種はホワイトスター。

種播き時はポリトンネル掛け、その後不織布に掛け替え5月半ばに外しました。
育苗中は異常乾燥状態でしばしば灌水しました。追肥は灌水を兼ね液肥を数回。
薄播きにしており、間引きはほんの一部厚いところを間引いただけです。
薄播きにしており、間引きはほんの一部厚いところを間引いただけです。
若干混んでいますが、まずまずの苗でしょうか。

苗は十分すぎるほどあるので、良い苗だけを選んで植えます。
畑の方は全面に苦土石灰を入れて1度目の耕耘、元肥を帯状に散布し2度目の耕耘、植付け前に再度耕耘しました。
多少手直しをした後、植付け溝になるところに目印線を付けます。
多少手直しをした後、植付け溝になるところに目印線を付けます。

畝間は昨年同様に幅広の120㎝。
管理機の畝立てロータで土をはねあげ、植付け溝を作ります。
管理機の畝立てロータで土をはねあげ、植付け溝を作ります。

鍬で少々手直しをして植付け溝を整えます。

以前は白根(軟白部分)40㎝以上の長ネギを穫ることを目標に深さ30㎝ほどの溝を立てていました。
しかし、強粘土質のため水が抜けにくく根腐れを起こしやすいことから、今は深さを20㎝くらいの浅めの溝にしています。
それでも畝間を広くし土寄せすることで大分カバーできるようです。
植える時は小さいものは除外し、出来るだけ苗を揃えて植付けます。

植付け間隔は数㎝。直立に植えないと根元が曲がるのですが、あまり気にしないことにしました。
植付け後に、苗から少し離して粒状の殺虫剤と化成肥料を少々バラまき。

最後に鍬で少し土を掛け整えます。

これで植付けは終わりました。

さらに、乾燥防止と土の締まりを抑えるためたっぷりと敷きわらをします。

切りわらは昨年秋から堆積しておいたもので、腐っている部分もあります。
この作業は強粘土質の畑には必須。これが次第に腐れて土がほどよい状態になります。
土を少し埋め戻しわらを落ち着かせます。
土を少し埋め戻しわらを落ち着かせます。

これで植付け完了です。

苗は沢山余りました。当分の間補植用に取っておきます。
10月早々からの本格収穫を目指したい。