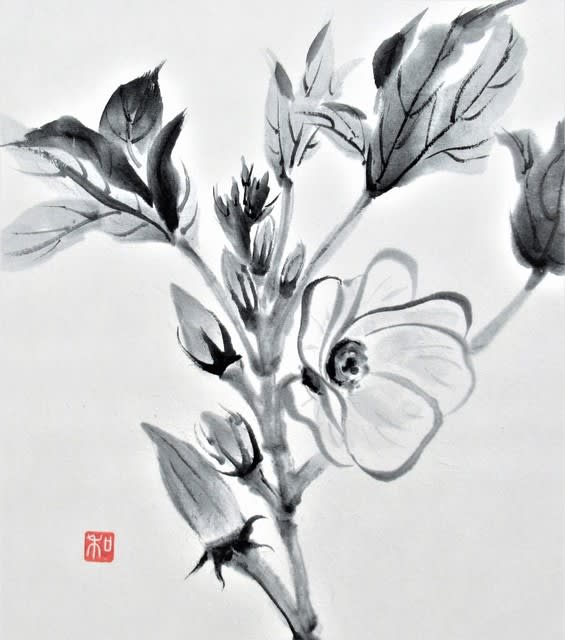春播きの長ネギに追肥と土寄せをしました。2回目となります。
前回は、連日の雨で機械が入れず、鍬だけで強引に追肥と土寄せを決行しました。と言っても土寄せはほんの軽くしただけです。葉色が落ちて肥え切れの症状が見えたからですが、多少は効果があったでしょうか。
この畑は粘土質が強く、昨年は大雨で根腐れをおこして多くを駄目にしたので、今年は植付け時の深い溝を立てるのを止め浅い溝にしました。そのためか、今年は7月の大雨にも耐えて何とか持っています。
8月は一転、連日の猛暑で全く雨が降りません。これでは高温嫌いのネギはたまりませんが、この程度の姿で夏を乗り切れるならしょうがないでしょう。しかし、粘土質の土も相当に硬くなってきました。ひび割れが見えます。
前回は、連日の雨で機械が入れず、鍬だけで強引に追肥と土寄せを決行しました。と言っても土寄せはほんの軽くしただけです。葉色が落ちて肥え切れの症状が見えたからですが、多少は効果があったでしょうか。
この畑は粘土質が強く、昨年は大雨で根腐れをおこして多くを駄目にしたので、今年は植付け時の深い溝を立てるのを止め浅い溝にしました。そのためか、今年は7月の大雨にも耐えて何とか持っています。
8月は一転、連日の猛暑で全く雨が降りません。これでは高温嫌いのネギはたまりませんが、この程度の姿で夏を乗り切れるならしょうがないでしょう。しかし、粘土質の土も相当に硬くなってきました。ひび割れが見えます。
畝は4列。

今回は機械でしっかりと追肥、土寄せをします。
この手前の1列は3月に早播きした苗を5月末に植えたもの。
この手前の1列は3月に早播きした苗を5月末に植えたもの。

品種はホワイトスター。

速効性の肥料を散布しました。

管理機のローターの爪を外向きにして逆転作業で土をはね上げます。

土がかなり硬くなっており、ごろ土もできます。植付けた時たっぷりと敷き藁をしたのが腐れて、ネギの近くはあまり土が硬くなっていないのが救いです。それなりに根は張っているようです。
左の3列は6月19日に植付けた長ネギ。

品種は右の2列がホワイトスター。

左の1列が白扇。

前回土寄せする時、少し葉が黄ばんでいましたが、今は直っています。と言うより乾燥で葉色が濃くなっているのでしょう。冴えた色ではありません。意外にもひどい葉枯れの症状や高温時によく出るスリップス(ネギアザミウマ)はあまり見られません。
こちらも同様に逆転ロータで土をはね上げました。
こちらも同様に逆転ロータで土をはね上げました。

鍬で少し手直しして終了です。

手前の早植えした畝は9月中からの収穫を目指していましたが、まともなネギはちょっと無理です。自家用には間引きながら薬味程度のネギには十分使えるでしょう。

今年は植え溝を浅くしたので、従来目標にしていた白根40センチ以上の長ネギは封印、ほどほどの軟白で歩留まりの良いネギを目指します。