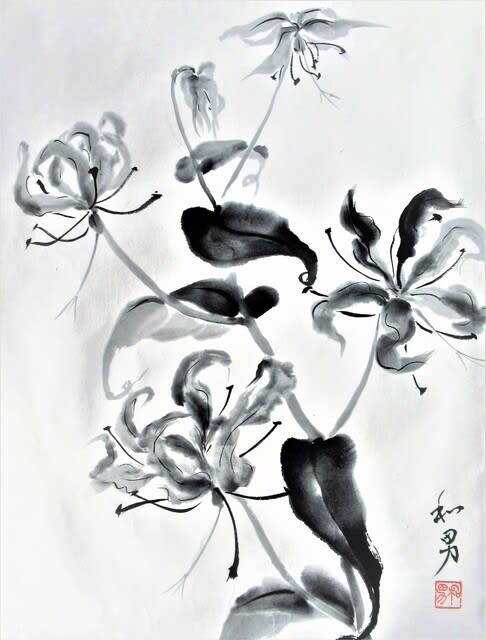「かき菜」の収穫を始めました。
すでにわき芽がたくさん出ています。

茎立ち菜として作っているのは「仙台雪菜」「かき菜」「三陸つぼみ菜」の3種。
何れも10月19日に直播き。
「かき菜」の収穫は、最も早い「三陸つぼみ菜」より2週間少々の遅れ。
「仙台雪菜」とは僅かの違いしかありません。
何れも10月19日に直播き。
「かき菜」の収穫は、最も早い「三陸つぼみ菜」より2週間少々の遅れ。
「仙台雪菜」とは僅かの違いしかありません。

例年なら「仙台雪菜」とは1週間ほどの違いがあるので、今年は差が少ない。
この「かき菜」がナバナ類としての最後。
これで茎立ち菜(とう立ち菜)として作っている3種が全て揃いました。
何れも昨年より1週間から10日は遅れており、確かに厳冬の影響が明確です。
しかし、近年が暖冬傾向だったのであって、これが普通と考えるべきなのかもしれません。
「かき菜」は北関東の在来アブラナの一種。
この「かき菜」がナバナ類としての最後。
これで茎立ち菜(とう立ち菜)として作っている3種が全て揃いました。
何れも昨年より1週間から10日は遅れており、確かに厳冬の影響が明確です。
しかし、近年が暖冬傾向だったのであって、これが普通と考えるべきなのかもしれません。
「かき菜」は北関東の在来アブラナの一種。

その名の通り、花芽が伸びてくる茎葉を掻き取って収穫します。
ナバナ類の一種でありながら、菜の花が見えるようになる前の若い茎葉を食べます。
ナバナ類の一種でありながら、菜の花が見えるようになる前の若い茎葉を食べます。
知らなければ単なる葉物のように見えるかもしれません。
同様の在来アブラナは全国各地に見られます。
トウが伸びてきても花芽はなかなか見えてきません。
同様の在来アブラナは全国各地に見られます。
トウが伸びてきても花芽はなかなか見えてきません。
蕾が大きくなってから穫るのでは遅く、硬くなり美味しくありません。

最も早くから収穫が始まった「三陸つぼみ菜」より2週間ほど遅い。
しかし、この違いは収穫のピークをずらす上では、むしろ好都合とも言えます。
「つぼみ菜」はその名の通り蕾が見えてから収穫しても軟らかい。
それに比べ「かき菜」はさらに早く蕾が見え始めるくらいまでに穫らないといけません。
この3種の中では、「かき菜」が最も丈夫で作りやすい。

「かき菜」も一般より早めに播いて大株にします。その方がわき芽も多くなり沢山穫れます。
「かき菜」は生育が旺盛。
「かき菜」は生育が旺盛。
主枝の茎は太いですが、若いので軟らかく、美味しく食べられます。
すでにわき芽が主枝と区別がつかないくらい伸びてきた株もあります。

花芽は隠れてよく見えません。

よくよく目を凝らしてみると辛うじて確認できます。このくらいのうちに穫るのがベスト。

この後は一気に盛りになることが予想されます。
こちらは「仙台雪菜」。今年は「かき菜」と収穫期が殆ど変わらなくなりました。
こちらは「仙台雪菜」。今年は「かき菜」と収穫期が殆ど変わらなくなりました。

こちらは「三陸つぼみ菜」。

収穫開始から2週間ほど経ち、すでに主枝の収穫は終わってわき芽の盛り。
全体的に茎が細身になってきました。
「かき菜」と「三陸つぼみ菜」はよく似ています。穫ったものを並べて比較してみます。
全体的に茎が細身になってきました。
「かき菜」と「三陸つぼみ菜」はよく似ています。穫ったものを並べて比較してみます。

右が「かき菜」左が「三陸つぼみ菜」。
「三陸つぼみ菜」はわき芽のせいもありますが、「かき菜」の方が大柄です。
ともに穫ったときは葉色が淡く見えても、湯がくと濃い緑になります。
「三陸つぼみ菜」はわき芽のせいもありますが、「かき菜」の方が大柄です。
ともに穫ったときは葉色が淡く見えても、湯がくと濃い緑になります。