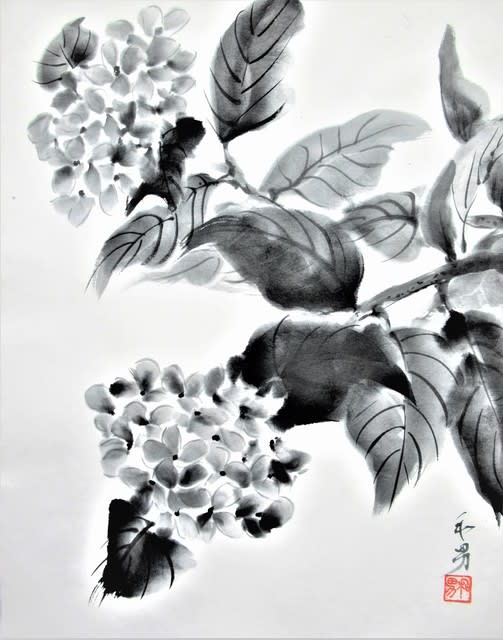今年も無事ネジバナが可憐な姿を見せてくれました。

この場所は田んぼの畦で、下は大きな土手になっています。この土手の一部が昨年10月の台風19号の豪雨で崩落しました。このネジバナが咲く付近は無事だったのですが、補修で通る際、数え切れないくらい踏みつけたので、どうなるかと思っていました。その時は補修が最優先で、ネジバナのことを考える余裕はありませんでしたが、落ち着いてからは、内心生き残っていてくれと思っていました。

先日、畦の刈り払いをしながら、気をつけて見ると咲き出していました。例年、大概が草刈りの時期に咲くため、刈り倒さないよう注意します。普通に刈り倒しても雑草と同じに再生するでしょうが、残してやるのが人情というもの。そして、ほっと一息和みの時が得られます。

先日は咲き始めでしたが、すっかり咲き揃ったようです。

ネジバナを避けながら刈り払うため周りに草が残っています。辺りは野芝とともにチガヤが多い。
ここは日当たりがよく、周りはが野芝が中心で、年に何回か刈り払いをするため雑草に埋もれないことで絶えないのではないかと思います。

小さな花がらせん状に綺麗に並んでいます。ネジバナとは誠にもって姿通りの名前です。この辺りではネジリバナと言うのが一般的です。
よく見るとなかなか面白い。確かに右巻きと左巻きがあります。これからも自然のままにして、この時期、一時の安らぎを得たい。

ネジバナは、昔はもっと方々にありましたが、見えなくなりました。と思いきや、偶然こんなところに見つけました。

注意すれば、もっとあるのかもしれません。