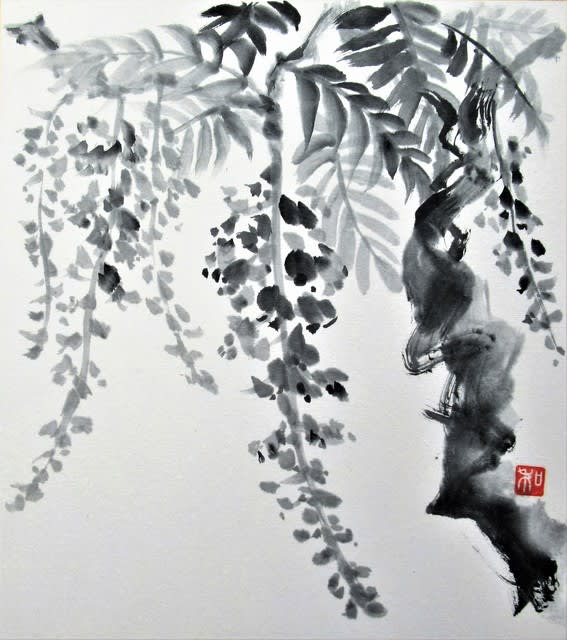アヤメが満開になってきました。
アヤメにハナショウブにカキツバタ。
同じアヤメの類いで、違いはどこかよく話題になります。
これは、間違いなくアヤメ。
小型のアヤメです。
アヤメにハナショウブにカキツバタ。
同じアヤメの類いで、違いはどこかよく話題になります。
これは、間違いなくアヤメ。
小型のアヤメです。

年々株が増えて群生化してきました。
これは庭と言えるかどうか。後ろの育苗ハウスと道路脇の側溝の間のスペースです。

花びらの付け根に黄色と紫の網目模様。
乾いているところに生えています。
草丈は数十センチで、葉も細く葉脈は目立たちません。アヤメの典型的な特徴があります。
草丈は数十センチで、葉も細く葉脈は目立たちません。アヤメの典型的な特徴があります。
これは畑の脇の方にあり、後ろにウルイが見える変わったコラボです。

これは。白のアヤメ。

植えられたはずがないので、おそらく変異したものと思われますが、確証はありません。
ちなみにハナショウブの特徴は、花びらの根元が黄色で、草丈が1メートルくらいと高いものが多く、葉にはしっかりとした中肋。半湿地を好むが適地の範囲は広いようです。
カキツバタは花びらの付け根に白い線模様。アヤメ園などで見るとハナショウブなどより花びらがすっきりした感じがします。草丈はアヤメよりは高いがハナショウブほどはなく、葉の中肋は目立たない。完全な湿地に生えるのが特徴とされます。
我が家にカキツバタはありません。
カキツバタは花びらの付け根に白い線模様。アヤメ園などで見るとハナショウブなどより花びらがすっきりした感じがします。草丈はアヤメよりは高いがハナショウブほどはなく、葉の中肋は目立たない。完全な湿地に生えるのが特徴とされます。
我が家にカキツバタはありません。