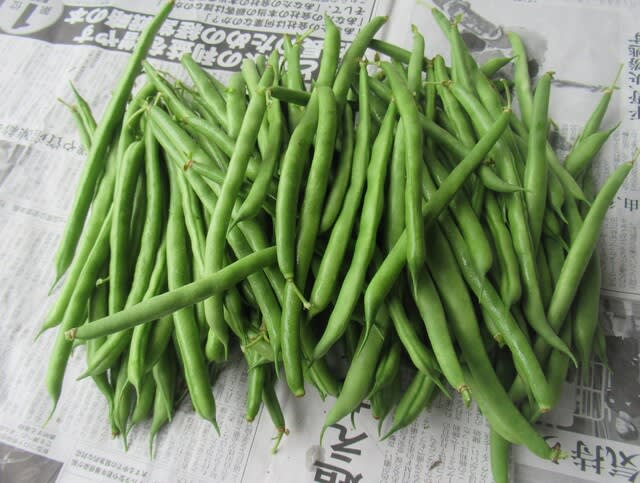夏秋きゅうりは収穫開始から約2ヵ月半。
惨めな姿になりました。
惨めな姿になりました。

今年は、生育のペースが速く、7月早々には主枝のピンチが終わり2本仕立てが完成。
一気に収穫最盛期となりました。
特に7月下旬から8月上旬の成り込みは凄く、1株から1日数本穫れる日が続きました。
助っ人が音を上げるほど。大量に塩漬けにしたようです。
成り疲れが心配されましたが、さほどのことはありませんでした。
勢いのいい孫蔓が沢山伸び、長期収穫が望める姿で後半戦に入りました。
今年は例年になく上手くいきそうだと自己満足していましたが。
中下旬の長雨には参った。
台風9号崩れの強風のダメージも。
一気に収穫最盛期となりました。
特に7月下旬から8月上旬の成り込みは凄く、1株から1日数本穫れる日が続きました。
助っ人が音を上げるほど。大量に塩漬けにしたようです。
成り疲れが心配されましたが、さほどのことはありませんでした。
勢いのいい孫蔓が沢山伸び、長期収穫が望める姿で後半戦に入りました。
今年は例年になく上手くいきそうだと自己満足していましたが。
中下旬の長雨には参った。
台風9号崩れの強風のダメージも。

そして、一転ここ数日の真夏のカンカン照りで、この姿に。
それでも、まだ頑張ろうとする蔓があります。

伸びようとする孫蔓。

ひ孫蔓も。

しっかりした雌花も着いています。

これらを放棄してしまうのは忍びない。

厳しい状況ですが、まだ諦めず孫蔓をとことん活かしてみます。
隙間のあるところに蔓をネットに掛け伸びるようにしてやります
隙間のあるところに蔓をネットに掛け伸びるようにしてやります

主枝の葉は大半摘み終わり、子蔓の葉もかなり摘んでいます。
枯れ葉も沢山出てしまいましたが、きれいに除くのは手間が掛かります。
邪魔にならなければ、見てくれは気にしないことにしました。
追肥は、マルチをまくり上げ、ベットの肩から通路の敷きわらの上にバラ播いています。
枯れ葉も沢山出てしまいましたが、きれいに除くのは手間が掛かります。
邪魔にならなければ、見てくれは気にしないことにしました。
追肥は、マルチをまくり上げ、ベットの肩から通路の敷きわらの上にバラ播いています。

ただ、追肥は沢山穫れている時にするものなので、ここではやりません。
残念ながら、目標収穫日数100日は達成できませんでした。
残念ながら、目標収穫日数100日は達成できませんでした。
終了のゴングまで、あとどのくらいしぶとく頑張れるか。