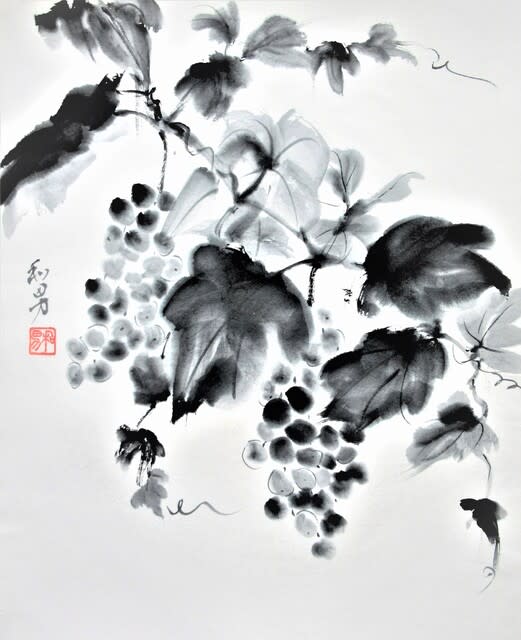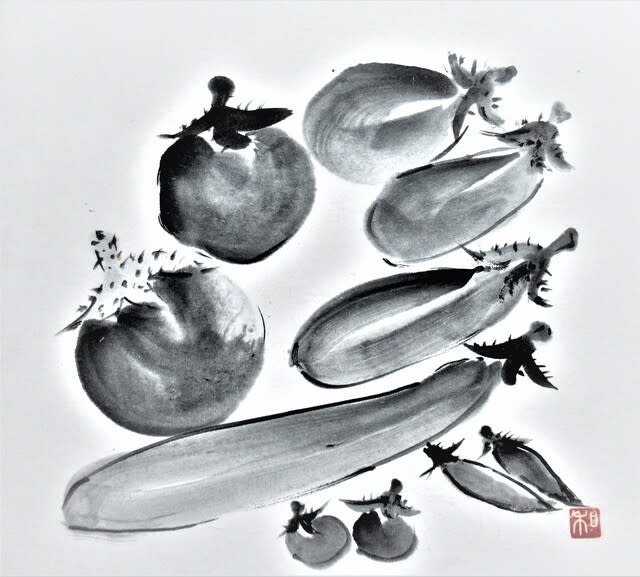ハクサイに追肥と土寄せをしました。一昨日です。
8月25日に直播き。
8月25日に直播き。
品種はトーホク種苗の中晩生種「郷秋80日」。
85日タイプの予定が80日タイプになりました。
発芽もその後の生育もまずまず。
間引きは台風14号来襲前に終え1本立てになっています。
発芽もその後の生育もまずまず。
間引きは台風14号来襲前に終え1本立てになっています。
これはその時のもの。この時点では土はかなり乾いていました。

この時に管理機の逆転ローターで中耕しています。中耕とは畝間を軽く耕すこと。

普通なら土寄せ時に合わせてやります。葉を傷めやすいので、機械作業だけ終えることにしたもの。
台風はさしたることはなかったのですが、その後にかなりの雨。未だ水分が多い状態です。

まず追肥。
畝の両側に速効性の肥料を施します。

ここからの土寄せは手作業。
鍬で根元にしっかりと寄せます。
鍬で根元にしっかりと寄せます。

少し水分が多いながらも作業は問題なく出来ました。

これで終了です。姿としては悪くなさそう。

結球前に再度追肥土寄せできれば理想ですが。
こちらは早生ハクサイ。
こちらは早生ハクサイ。


概ね順調に見えますが、気温が高過ぎます。結球が始まって高温だと腐敗が心配。
10月半ばからの収穫が目安、どうなりますか。
10月半ばからの収穫が目安、どうなりますか。