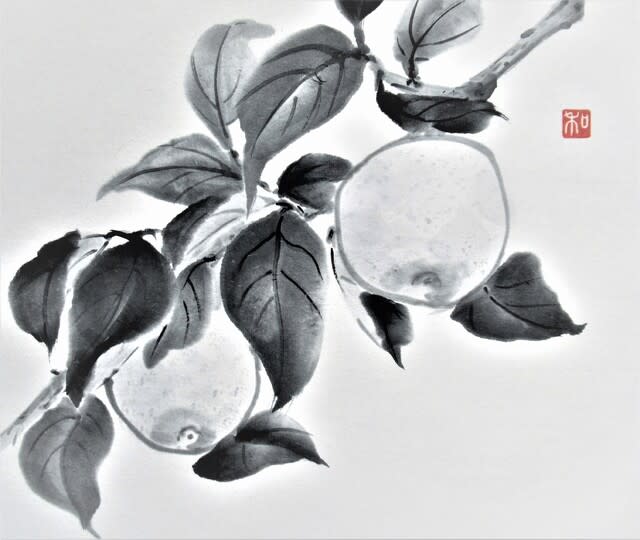完熟した九重栗カボチャの3番果を一斉に収穫しました。
品種は九重栗。
4月28日に我流の省力直播きし、親蔓1本仕立てにしています。
3番果まで穫るよう蔓を伸ばしており、10メートルくらいに達しています。
全体的に少し遅れましたが、1番果はもちろん、2番果も9月上旬までに収穫は終わっています。
3番果まで穫るのは、昨年に引き続き2度目。
大半が自然着果です。
2番果は揃ってよく実が留まりましたが、3番果の留まりはあまり良くありません。
3番果は株元から5~6メートルあたりに着いています。
品種は九重栗。
4月28日に我流の省力直播きし、親蔓1本仕立てにしています。
3番果まで穫るよう蔓を伸ばしており、10メートルくらいに達しています。
全体的に少し遅れましたが、1番果はもちろん、2番果も9月上旬までに収穫は終わっています。
3番果まで穫るのは、昨年に引き続き2度目。
大半が自然着果です。
2番果は揃ってよく実が留まりましたが、3番果の留まりはあまり良くありません。
3番果は株元から5~6メートルあたりに着いています。

昨年からみると遅れていますが、着果後45日以上経過したので、完熟に達しています。
蔓の先に着く実は、通称末(うら)成り、まずいカボチャの代表格です。
しかし、それは蔓先には葉が少なく、しかも熟さない実を穫るのでまずいのは当然。
3番果であっても十分な葉が確保されて完熟すれば美味い実が穫れるはずです。
蔓の先に着く実は、通称末(うら)成り、まずいカボチャの代表格です。
しかし、それは蔓先には葉が少なく、しかも熟さない実を穫るのでまずいのは当然。
3番果であっても十分な葉が確保されて完熟すれば美味い実が穫れるはずです。

どの実も軸は変色し、ひび割れが多数出ているので完熟していると思います。

ただ、さすがに雑草が茂り、葉も枯れてきているので、どうでしょうか。

前に穫った2番果がまだ残っているため、3番果は一度も収穫していません。
いくら完熟がいいとは言っても、これ以上畑に置くと劣化が早まります。
いくら完熟がいいとは言っても、これ以上畑に置くと劣化が早まります。

ここで、一斉に収穫することにしました。
着果がイマイチとは言え、このくらい穫れました。
着果がイマイチとは言え、このくらい穫れました。
形も大きさもまずまずです。

こちらは、7月1日に直播きした遅穫り用のカボチャ。

冬至カボチャに使う貯蔵用として作っています。
品種は「雪化粧」。
昨年の「白爵」は収穫ゼロ。
今年も不調です。1番果は途中で腐ってしまい、結局ゼロ。
これは2番果。
品種は「雪化粧」。
昨年の「白爵」は収穫ゼロ。
今年も不調です。1番果は途中で腐ってしまい、結局ゼロ。
これは2番果。

果たしてどのくらいものになるか。

九重栗カボチャの3番果の一部も遅くまで残してみようと思います。
こちらは残っている2番果。まだ盛んに食べています。
軸は劣化してきましたが。

まず、こちらから食さないといけません。
追熟も限度に近づいています。一つ切ってみます。
追熟も限度に近づいています。一つ切ってみます。

問題ありません。オレンジに近い濃い黄色です。

この九重栗カボチャは強粉質の栗カボチャで、ホクホク感が際立ちます。