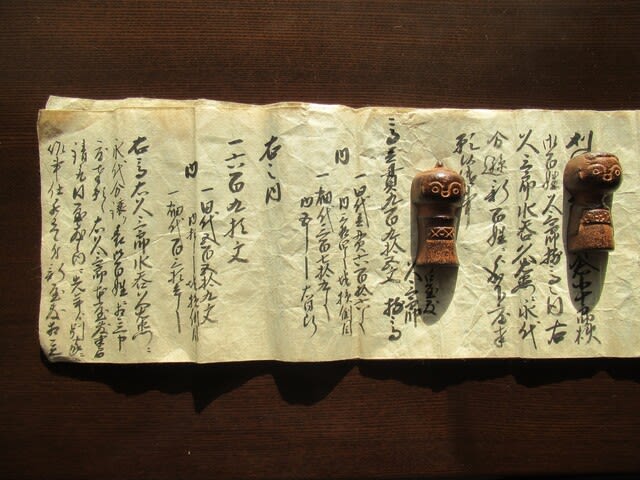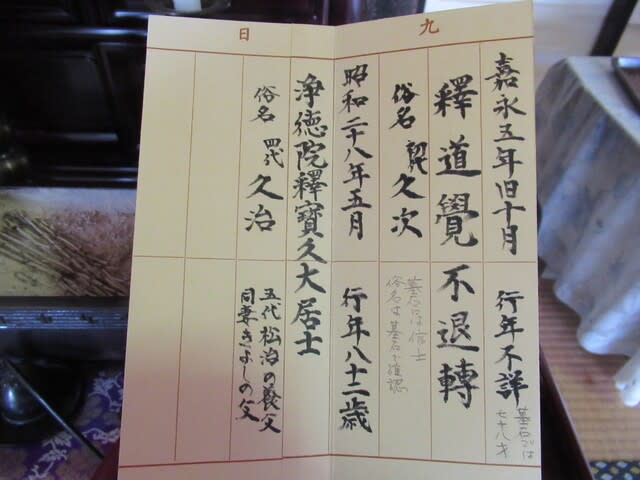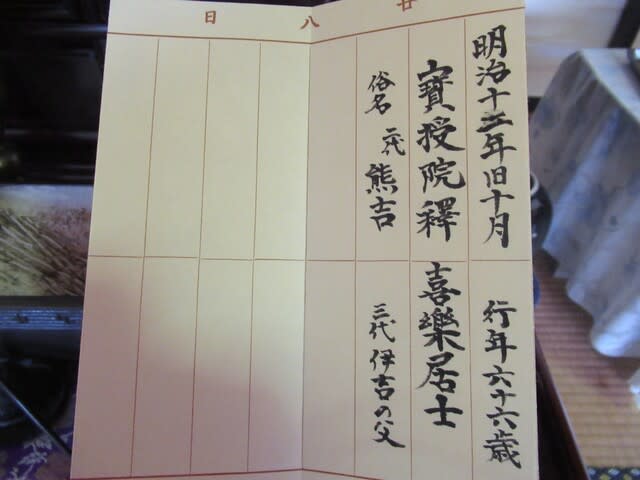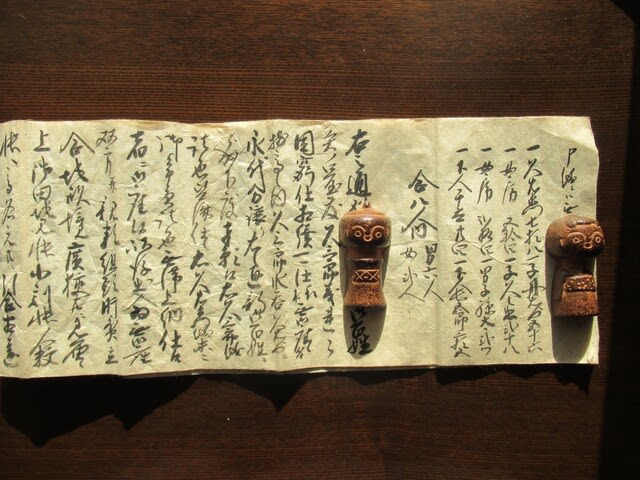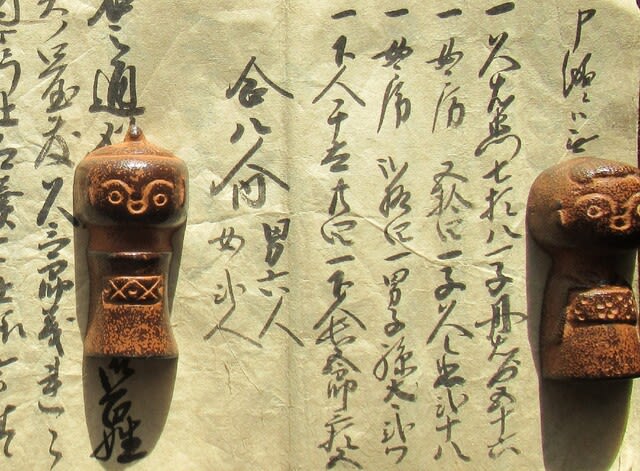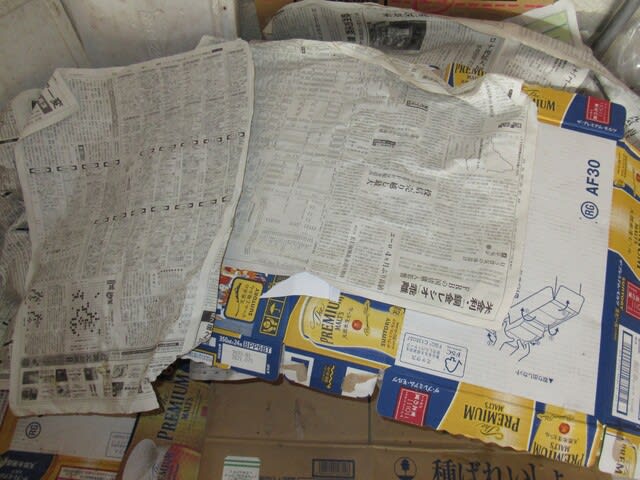フキノトウを採りました。
フキノトウは春を告げる山菜と言えるでしょうか。
今年は厳冬。先週は2日連続で真冬日を記録するなど繰り返し寒波が襲来しています。
今年は遅れることは確実と思っていました。
ここ2、3日急に気温が上がったので様子を見に行ってきました。
我が家の田んぼの土手です。結構出ています。
フキノトウは春を告げる山菜と言えるでしょうか。
今年は厳冬。先週は2日連続で真冬日を記録するなど繰り返し寒波が襲来しています。
今年は遅れることは確実と思っていました。
ここ2、3日急に気温が上がったので様子を見に行ってきました。
我が家の田んぼの土手です。結構出ています。
群生と言うほどではないものの、それなりにまとまって出ています。

例年なら2月20日頃には出始めるので、数日の遅れといったところでしょうか。
厳冬と言ってもそれほどは遅れないものです。
朝の8時半頃でしたが、霜が降りてまだ土や草が凍っていました。
厳冬と言ってもそれほどは遅れないものです。
朝の8時半頃でしたが、霜が降りてまだ土や草が凍っていました。

この土手は南向きのため他より早い可能性はあります。
これはすでに開き始まっていました。
これはすでに開き始まっていました。

この脇は水路で、補修をした際、泥上げをしました。そこから生え出したものもあります。

フキノトウは面白い。
地下茎からまず地上に蕾を出し、それからトウが生長して花が咲きます。
その後から葉っぱが地上に伸びてきます。
地下茎からまず地上に蕾を出し、それからトウが生長して花が咲きます。
その後から葉っぱが地上に伸びてきます。

大概の植物はまず葉っぱが伸び、ある程度大きくなったところで最後にトウが伸び出し、花が付きます。まるで逆さま。
昔、我が家ではフキノトウを食べる習慣はなかったように思います。
ですから、意識してフキノトウを採るということはありませんでした。
昔、我が家ではフキノトウを食べる習慣はなかったように思います。
ですから、意識してフキノトウを採るということはありませんでした。
かつて県北部で仕事をしていた折り、たまたま「ばっけ味噌」をご馳走になったことがあります。
「ばっけ」とはフキノトウのこと。それまでは「ばっけ」も「ばっけ味噌」も知りませんでした。
「ばっけ味噌」はフキノトウと味噌を和えたもので、これが独特の風味で美味しい。
もっとも、我が家ではせいぜい天ぷら程度ですが。
フキノトウの採り頃は短い。苞葉が開いて中の花が見える前の蕾のうちです。
「ばっけ」とはフキノトウのこと。それまでは「ばっけ」も「ばっけ味噌」も知りませんでした。
「ばっけ味噌」はフキノトウと味噌を和えたもので、これが独特の風味で美味しい。
もっとも、我が家ではせいぜい天ぷら程度ですが。
フキノトウの採り頃は短い。苞葉が開いて中の花が見える前の蕾のうちです。

これくらいまで。

左のはぎりぎり、右のはまだ硬く早い。

20数個持ち帰りました。

凍害で葉先が黒変しているのが気になりますが、今年はしょうがないでしょう。
ささやかな早春の香りを味わいました。
当地のような寒冷地でも確実に春に向かっていることを知らせてくれます。
ささやかな早春の香りを味わいました。
当地のような寒冷地でも確実に春に向かっていることを知らせてくれます。