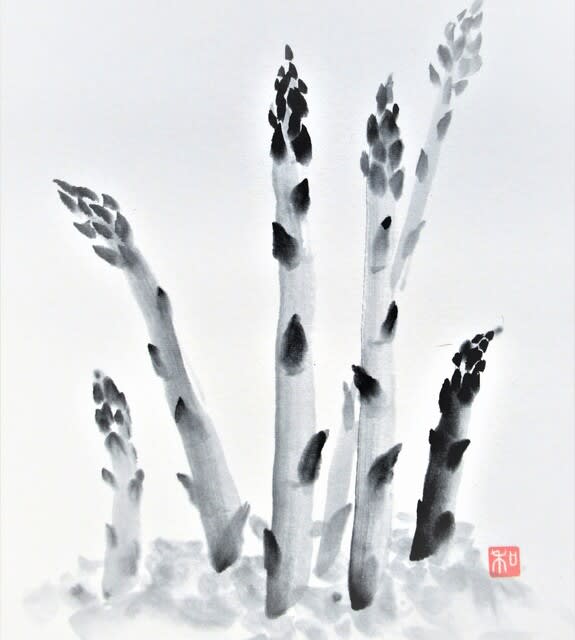キュウリの蔓上げをしました。
蔓上げとは、この辺りの通称でネットや支柱への最初の誘引のことです。
植付けから約2週間。予定より少し遅れました。
本来なら、今頃が当地の植え付け適期です。
それよりも早い植付けだったので、周りを不織布で覆いました。
蔓上げとは、この辺りの通称でネットや支柱への最初の誘引のことです。
植付けから約2週間。予定より少し遅れました。
本来なら、今頃が当地の植え付け適期です。
それよりも早い植付けだったので、周りを不織布で覆いました。

品種は初めて作る「OS交配ニーナ」。
苗は、本葉3枚半程度で葉色も良くしっかりした苗でした。
不織布はどちらかというと強風対策ですが、効果は十分あったと思います。
先週末は強風が吹き荒れ、トマトの枝葉が折れるなど酷いものでした。
苗は、本葉3枚半程度で葉色も良くしっかりした苗でした。
不織布はどちらかというと強風対策ですが、効果は十分あったと思います。
先週末は強風が吹き荒れ、トマトの枝葉が折れるなど酷いものでした。
それで、キュウリの蔓上げを見合わせていました。ようやく落ち着いたので不織布を外しました。

この時期になればキュウリにとってもほぼ適温期。
今のキュウリの大きさは本葉7枚くらいで、揃っています。

キュウリを植付けたままにすると、このように地べたを這うものが出てきます。

蔓上げは蔓が立っているうちにやるのが原則。
遅くなると樹勢に影響してきます。それからすると、少々遅めとなりました。
植付け時からみると本葉4枚が展開しており、悪くありません。
不織布で囲わないときは、風で折られないよう植付けてすぐ脇に割り箸を刺して誘引していました。
今のところ生育は順調。葉色も良くがっちりと放射形に伸び充実した姿に見えます。
植付け時からみると本葉4枚が展開しており、悪くありません。
不織布で囲わないときは、風で折られないよう植付けてすぐ脇に割り箸を刺して誘引していました。
今のところ生育は順調。葉色も良くがっちりと放射形に伸び充実した姿に見えます。

今回はネットに直接誘引します。

全て蔓上げしました。

夏から秋にかけネット栽培される、いわゆる夏秋キュウリでは株間との関係で仕立て方は様々。
我が家では、株間75㎝で親蔓と子蔓1本を伸ばす2本仕立てです。

これから生長に合わせ整枝をしていきます。

すでにわき芽が伸び雌花も見えます。

下位2、3節までの伸びているわき芽や見える雌花は搔きました。

初めて作る品種「ニーナ」。
今見る限りでは、葉はやや小型で全体的に締まった姿のように見えます。
今見る限りでは、葉はやや小型で全体的に締まった姿のように見えます。

ときわ交配かOS交配が希望だったので購入しましたが、後で確認すると周年とは言えハウス用品種でした。
雨除けにも適するとは言うものの何分露地。作ってみないことには分らず不安ではあります。