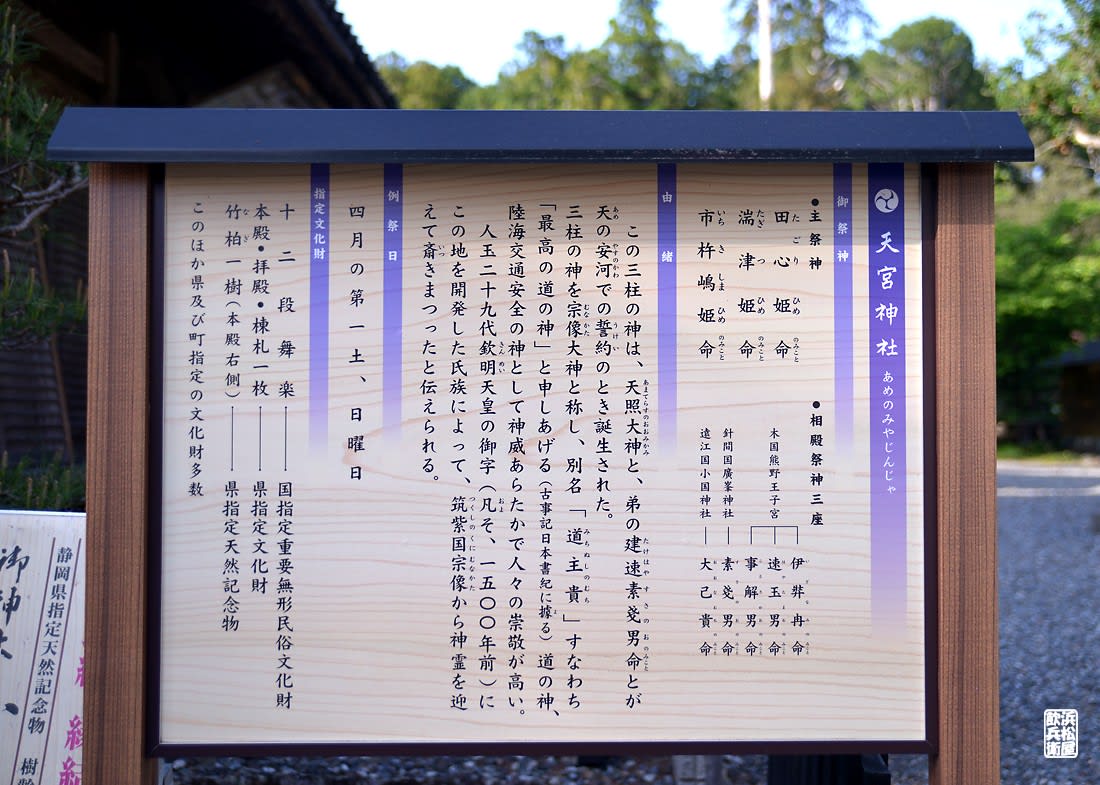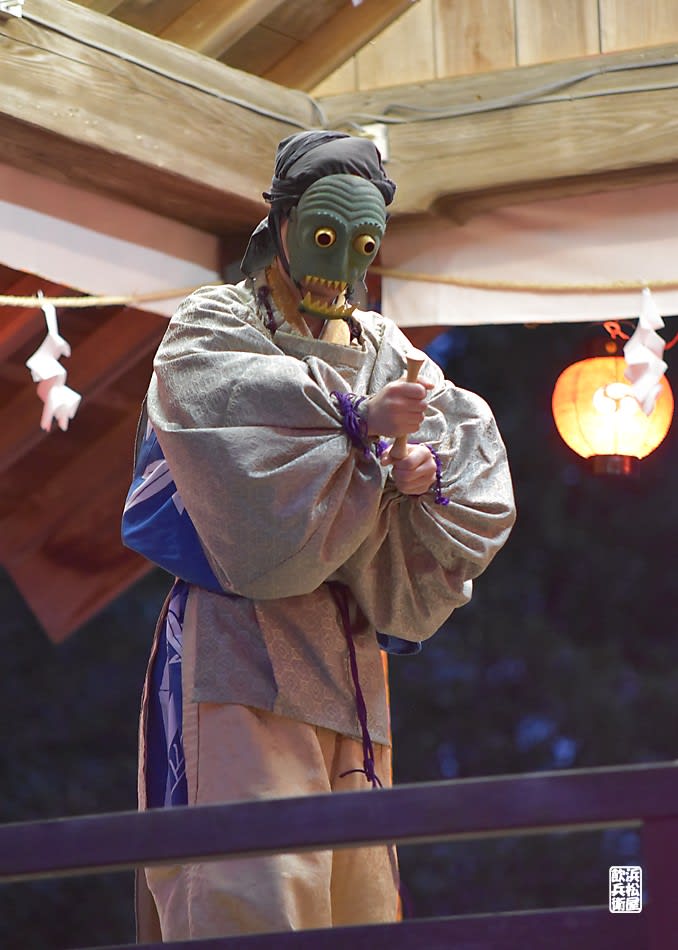山名神社八段舞楽より、
6番目「龍(りょう)の舞」
この舞の見所は、龍の二人が柱によじ登り、逆さになって
上体を煽るアクロバッットな場面です。
山名神社八段舞楽の中で最も人気の高い舞いで、
ここぞとばかりカメラ親爺やカメラ女子が集まってきました。

右側の柱では。



もう一人は左の柱で。


7~8年前に始めて山名神社を訪れた時には、
まさかこのようなアクロバット場面があろうとは思わず、
撮り逃してしまいました。
2度目の今回はヘボながらも何とか上体を煽る瞬間を
撮ることができて、やれやれです。
7番目「蟷螂(とうろう)の舞」
蟷螂(とうろう)とはカマキリのことです。
京都祇園祭では屋台の曳山として登場しますが、
「蟷螂の舞」が原型のまま存続しているのは、ここ山名神社のみ、
国指定重要無形民族文化財の所以であります。
手に持つ紐でカマキリの前肢を動かします。



8番目「優填(うでん)獅子の舞」
山名神社の御蔡神・素戔嗚尊(すさのおのみこと)は
疫病を退散させる力のある神様。
荒ぶる獅子を伏せて夏の流行病を防ぐ舞いです。