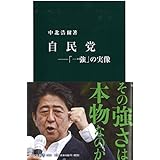私はアマゾンのまわしものではありませんがGWにこの2冊をじっくり読みたいと思っています。バカでキチガイじみた安倍政権ですがバックに自民党がいるので崩壊しないのです。問題は自民党一強なのです。
『自民党』は菅野完さんもアルルの男ヒロシさん(副島隆彦さんの弟子)も完読しているようです。彼らはお若いのにたいしたものです。
自民党―「一強」の実像 (中公新書)
2017/4/19中北 浩爾
新書
¥ 950プライム
コメント
投稿者 さきこマイラブ 投稿日 2017/4/23
コメント 7人のお客様がこれが役に立ったと考えています.
コメント 4人のお客様がこれが役に立ったと考えています.
現在の政界は、安倍首相率いる自民党の「一強」体制にあると言われるが、それは本当であろうか。
本書は、自民党について、派閥、総裁選挙、政策決定過程、国政選挙、友好団体、地方組織と個人後援会といった様々な角度から、自民党の独自性、強さと脆さを綿密に分析している。ただし、野党についての記載は全くと言っていいほど少ない。あくまでも純粋に自民党のことを研究した本である。
これから自民党はどこへ向かおうとしているのか?安倍政権は本当に長期政権であり続けるのか?それを考察する際に大いに参考になる本である。けして読み易い本ではなかったが、これはなかなかの力作である。
本書は、自民党について、派閥、総裁選挙、政策決定過程、国政選挙、友好団体、地方組織と個人後援会といった様々な角度から、自民党の独自性、強さと脆さを綿密に分析している。ただし、野党についての記載は全くと言っていいほど少ない。あくまでも純粋に自民党のことを研究した本である。
これから自民党はどこへ向かおうとしているのか?安倍政権は本当に長期政権であり続けるのか?それを考察する際に大いに参考になる本である。けして読み易い本ではなかったが、これはなかなかの力作である。
投稿者 保武佳吾 トップ500レビュアー 投稿日 2017/4/20
Amazonで購入
率直に言って、党員と献金は激減している。
これを埋め合わせているのが、選挙結果とそれに基づく交付金である。
よって、次の政権交代で自民党は壊滅する可能性すら大きいだろう。
勿論、これに対応した野党の動きは一見鈍いものがあり、本書でも最後の最後ではそんなに簡単にはいかないとする。
現政権に対比されているのは、自民党が主題であることからも旧民主党政権ではなく小泉政権であり、ポピュリズムからナショナリズムに移行して異様な無風状態が出現していると理解できる。
結論の逆接を再度覆しておくと、それでも自己完結に終始している(政権交代を前提としていない)今の自民党は、基軸(二大政党の一翼)としてははっきりと失格であると言っておかねばならないだろう。
これを埋め合わせているのが、選挙結果とそれに基づく交付金である。
よって、次の政権交代で自民党は壊滅する可能性すら大きいだろう。
勿論、これに対応した野党の動きは一見鈍いものがあり、本書でも最後の最後ではそんなに簡単にはいかないとする。
現政権に対比されているのは、自民党が主題であることからも旧民主党政権ではなく小泉政権であり、ポピュリズムからナショナリズムに移行して異様な無風状態が出現していると理解できる。
結論の逆接を再度覆しておくと、それでも自己完結に終始している(政権交代を前提としていない)今の自民党は、基軸(二大政党の一翼)としてははっきりと失格であると言っておかねばならないだろう。
コメント 12人のお客様がこれが役に立ったと考えています.
生前退位をめぐる安倍首相の策謀 (宝島社新書)
2017/2/10五味 洋治
文庫
¥ 842プライム
コメント
投稿者 YH 投稿日 2017/2/28
Amazonで購入
コメント 9人のお客様がこれが役に立ったと考えています. .
東京新聞編集委員の五味洋治さんは、「新聞社での仕事の大半は、北東アジアに関する国際報道」(「まえがき」)だ。特に、北朝鮮問題には詳しく、『父・金正日と私 金正男独占告白』『女が動かす北朝鮮』などの著書がある。その五味さんが今度は、『生前退位をめぐる安倍首相の策謀』と題する本を出した。書名が気にいったので読んでみた。
五味さんは、「この本を書こうと思った動機は、この『生前退位』に込められたメッセージは何か、ということだ」と「まえがき」で述べている。そして、自分でその答えも出していて「私は安倍首相の政治姿勢に対する『疑問符』『抵抗』という気がしてならない」(P2)と続けている。
明仁天皇(1989年即位)は、日本国憲法第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」の規定に基づき即位した初めての天皇である。前天皇、裕仁天皇は大日本帝国憲法第1条「第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」との規定のもとで即位した。そして、1945年8月15日のポツダム宣言受諾-大日本帝国の敗戦、1946年1月1日の「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本... 他方、明仁天皇は違う。彼は、天皇となり、天皇を生きるうえで、ふたつの課題を自らに課したと推測する。一つは、父である裕仁天皇が為した過ちの「克服」である。二つめは、「象徴天皇」というものの確立とその求心性の獲得である。ふたつの課題は別のものであるようで、その実は表裏一体のものであった。
一つ目の課題は難儀であった。裕仁天皇には明らかに戦争責任があった。それは誰も否定することのできないことであった。それ故、裕仁天皇自身も一時は退位を考えざるを得なかったし、周辺で退位を勧める者もいた。天皇退位問題については、国会で中曽根康弘議員が国会予算委員会(1952年1月31日)で質問もした、と五味さんは本書で紹介している(P151~153)。その質問に対し吉田首相(当時)は「これを希望するがごとき者は、私は非国民と思うのであります」となじった。しかし「議場からは拍手が起こった」(P153)と言う。裕仁天皇の退位を当然とする声は、その当時、左右を問わず一定存在したのである(注1)。
しかし、GHQ-マッカーサーは日本の占領統治のために裕仁天皇を利用することを決め、彼を極東軍事裁判所に訴追することも、退位を迫ることもしなかった。裕仁天皇は戦争責任を免れた。その裕仁天皇と皇后が、1975年9月30日~10月14日にかつての敵国・米国を訪問した。訪米に先立って外務省・宮内庁は、戦争責任、パール・ハーバー攻撃等について追及される恐れなどを想定し、天皇が米国で発する「お言葉」を練りあげた。それを受けて、裕仁天皇は10月2日にホワイトハウスで行われたフォード大統領主催の晩餐会で次のように述べた-「私が、深く悲しみとする、あの不幸な戦争の直後、貴国が、我が国の再建のために、温かい好意と援助の手をさし延べられたことに対し、貴国民に直接感謝の言葉を申し述べる」。米国民がこの言葉をどう受けとめたかは定かではないが、米政府は当然これを受け入れた。
ただ、この「お言葉」をめぐっては、その続きがある。訪米後の10月31日、裕仁天皇は初めての公式記者会見を行った。その中である記者(「ザ・タイムズ」)が、「天皇陛下はホワイトハウスで『私が深く悲しみとするあの不幸な戦争』というご発言がありましたが、このことは戦争に対しての責任を感じておられるという意味に解してよろしゅうございますか。また、陛下はいわゆる戦争責任についてどのようにお考えになっておられますか、おうかがいいたします」と問うた。これに対し裕仁天皇は「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしていないのでよくわかりませんから、そういう問題についてはお答えできかねます」とハグラカシ、回答を拒んだ。裕仁天皇は、自らが大元帥として指導した戦争が引き起こした惨禍、自国民、他国民に与えた甚大な被害、苦痛に対する責任について明確にしなかったのである。それは実質的には責任の否定であり、無責任を決め込んだも同然であった。明仁天皇はそのような父親を批判することはなかったが、しかし、父親が為した罪過を無視・閑却することは却って天皇制を危うくするものであるとの認識を抱いたに違いない。それは明仁天皇が天皇となって以降に選択、実行した「公務」に端的にあらわれている。
明仁天皇が自らに課した二つ目の課題も簡単ではなかったと思われる。日本国憲法第1条は、天皇について「日本国」と「日本国民統合」の「象徴」であると規定した。しかし、「象徴」とは何か、どうあれば、何をすれば「象徴」なのか、「象徴」たり得るのか、具体的な規定は何も書かれていない。明仁天皇は自らでその解答をさぐり、実行していかなければならなかった。天皇と天皇制への国民の関心、親近感も薄れていく中で、求心性をも回復していかなければならなかった。そのために明仁天皇は美智子皇后とともにそれを模索、試行錯誤した。その結果辿りついたのが「国事行為」とは別の、天皇の意向、意思を忍ばせることのできる「公的行為」と、その範囲の拡大であった。明仁天皇・美智子皇后は、ふたつの課題を同時に「解決」していく道として、「公的行為」に精励することにしたのである。
明仁天皇が、上記の目的を達成していくために重ねた「公的行為」は主要に2つある。第1は、戦争犠牲者追悼、第2は、災害被災者等の見舞い、加えて、折にふれての「護憲」の表明である。
安倍首相は「地球儀を俯瞰する外交」と称して各国訪問を繰り返している。直近では、2016年12月末に真珠湾を訪問した。そこで安倍首相は、戦死者(米兵)に哀悼の意を表するとともに、米国の「寛容の心、和解の力」を称えた。1975年10月に裕仁天皇が米国で述べた「お言葉」と瓜二つであることに気づく。
他方、同じく戦死者を追悼、慰霊するために明仁天皇・美智子皇后も各所に足を運んできた。安倍首相は戦後70年に米国アーリントン墓地を訪れたが、天皇・皇后が訪ねたのはパラオ(2015年4月8日~9日)。パラオ国王主催の晩餐会(4.8)において、明仁天皇は次のように挨拶した-「先の戦争においては、貴国を含むこの地域において日米の熾烈な戦闘が行われ、多くの人命が失われました。日本軍は貴国民に、安全な場所への疎開を勧める等、貴国民の安全に配慮したと言われておりますが、空襲や食糧難、疫病による犠牲者が生じたのは痛ましいことでした。ここパラオの地において、私どもは先の戦争で亡くなったすべての人々を追悼し、その遺族の歩んできた苦難の道をしのびたいと思います」。天皇は、日本の植民地支配責任についてまでは言及していないが、曖昧な表現であるとはいえ戦争責任については半ば認めていると言える。
また、2016年安倍首相は真珠湾を訪ねたが、天皇・皇后が訪問したのはフィリピン(2016年1月26日~30日、公式訪問)と長野県阿智村にある「満蒙開拓平和記念館」(11月17日、私的旅行)。マニラに向かうに先立って羽田空港で(1.26)、天皇は、以下のように述べた-「フィリピンでは、先の戦争において、フィリピン人、米国人、日本人の多くの命が失われました。中でもマニラの市街戦においては、膨大な数に及ぶ無辜のフィリピン市民が犠牲になりました。私どもはこのことを常に心に置き、この度の訪問を果たしていきたいと思っています」。
さらに「満蒙開拓平和記念館」を訪れ、引揚者などと交流した天皇は、「こういう歴史(注2)があったことを、経験がない人たちに伝えることが大切だと思います。そういうことを経て今の日本が作られたわけですから」と語りかけた。皇后は「よくお苦しみに耐えてくださいましたね」と声をかけ、労をねぎらった。
天皇・皇后はまた、「沖縄に対して強いこだわりがある」(P192)。皇太子時代の訪問時(1975年7月)には活動家から火炎瓶を投げつけられるという事件もあった。しかし、彼らは事件後も公式日程をきちんとこなした。二人は薩摩藩の「琉球征伐」、明治維新後の琉球王国廃止-併合の歴史を承知していた。また、「遅すぎた聖断」により沖縄が地上戦にまき込まれ、県民の4人に一人が亡くなるという多大の犠牲を強いられたこと、戦後も「天皇メッセージ」により「本土」から切り離され、異民族支配の下に置かれたことをも知っていたに違いない。「沖縄に行く前には『石ぐらいなげられてもよい。そうしたことを恐れず県民の中に入っていきたい』と話していた」(P191)のは、その「歴史」に向き合うという表明であったと思われる。
パラオ、フィリピン、満蒙開拓平和記念館、そして沖縄。いずれも満州事変に始まるアジア・太平洋戦争の戦地であり、関連施設である。天皇・皇后はそこを訪ね、犠牲者を追悼し、遺族らに慰藉の言葉をかけている。明仁天皇は、裕仁天皇の戦争責任を認めてはいないし、それを「肩代わり」するとも述べていない。しかし、戦争の「後始末」は終わっていないと考え、彼なりのやり方-「公的行為」を実行すること-でそれを果たしているとも見える。それを戦争責任の果たし方であると首肯することは私には到底できない。しかし、彼はそれこそが天皇制を生き延びさせる道であると考えているのではないだろうか。
また、明仁天皇は1989年即位して以降、災害現場に足を運び、その犠牲者を弔い、被災者らを慰める「公的行為」を積み重ねてきた。1990年11月、即位礼の5日後に雲仙・普賢岳が噴火し、翌年6月に起きた火砕流で多くの死者・行方不明者が出た。この大惨事の5週間後に天皇・皇后は「定期便の民間機で、民間人に交じって長崎空港に着き、政府専用ヘリコプターで県立島原工業高校のグラウンドに着いた。宿泊を伴うと現地の人たちに手間をかけるとして、日帰りとした。随行員も通常の地方訪問の4分の1の5人だけだった。災害が続いている間に、天皇が現地を訪問するのは、歴史上初めてのことだった」(P178)。
これを嚆矢として以降、天皇・皇后は阪神淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)などが発生する度に被災地に足を運び、慰問を重ねてきた。
加えて明仁天皇・美智子皇后は折にふれて、「憲法を守る」という立場、決意を披瀝してきた。「1989(平成元)年即位後、『朝見の儀』という儀式で、天皇は『皆さんとともに日本国憲法を守る』と表明した」(P161)。さらに「結婚50年となった2009年4月の記者会見で、『象徴とはどうあるべきかということはいつも私の念頭を離れず、その望ましいあり方を求めて今日に至っています。なお大日本帝国憲法下の天皇の在り方と日本国憲法下の天皇の在り方を比べれば、日本国憲法下の天皇の在り方の方が、天皇長い歴史で見た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものと思います』と述べた」(P161~162)。既に2009年段階で、明仁天皇はこんなことを語っていた。自民党改憲草案(2012年)に、「天皇は日本国の元首」(第1条)との規定が入れられることをあたかも予想していたかのような対応と言うべきである。
そして、このような「公的行為」の積み重ねは、確実に天皇に対する国民の見方を変えてきた。「天皇に『尊敬の念を持っている』という人の割合が1998年の19%から徐々に上がり、2013年には34%になった」(P26)。「天皇に『好感を持っている』という人の割合も、平成に入る前年の1988年には22%と低かったが、平成5年である1993年には43%と急増。その後30~40%台を維持している」(P26~27)。
明仁天皇は今、齢80歳を超え、心身の衰えを自覚する中で、自分の歩んできた道が間違いではなかったと考えたと思われる。それと同時に、政治権力を執行している安倍首相の所業、振る舞いを見て危機感を覚えたに違いない。教育基本法を変え、戦争法を制定し、改憲への道をひた走る安倍首相を見て、明仁天皇はそれが「象徴天皇」制を危うくするものであると直観した。そして、「象徴天皇制」を維持するために自分がなしうることは何かを考え、「生前退位」を表明した。「全身全霊をもって象徴としての務めを果たしていくことが難しくなるのではないか」との懸念を表明しつつ、他方で「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われ」ると明言した。予想される「負担軽減」論に釘を刺しつつ、摂政を置くことも否定し、あくまで「生前退位」を希望したのである。それは、政治・軍事的権威、権能から距離を置き、「象徴天皇制」を規定した現行日本国(平和)憲法の下で、それに沿う存在であり続けるための行動と、その自由を担保しようという意思の表明であった。
これに対し、安倍首相は直ぐに明仁天皇の「生前退位」の真意を見抜いたに違いない。そして、安倍首相が打ち出したのは、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」であった。明仁天皇の求める「生前退位」ではなく、あくまで「公務の負担軽減」で対応するというのである。有識者会議で、平川祐弘などは「特に問題と感じますのは、その御自分で拡大解釈した責務を果たせなくなるといけないから、御自分は元気なうちに皇位を退き、次に引き継がせたいというお望みを『おことば』として発表されたこと」と言い、「天皇家は続くことと祈るという聖なる役割に意味があるので、それ以上のいろいろな世俗のことを天皇の義務としての役割とお考えになられるのはいかがなものか」と明仁天皇の「生前退位」をあからさまに否定した。しかし、天皇の「生前退位」表明に対しては圧倒的多数の国民が賛成している。さすがの安倍首相もこの事実を無視することはできない。そこから、明仁天皇一代限りに適用する「特別法」を制定し、「生前退位」を認める方向を打ち出した。これに対し、「天皇は、特例法制定の流れについて『自分が思った方向に行っていないようですね』と語っているという」(P6)。
この天皇の言葉がどこで誰に語られたものか、五味さんは出典を明らかにしていない。しかし、いかにも明仁天皇がこのような思いで事態の推移を見ているだろうとは推測しうる。
五味さんは、「まえがき」で、「皇室や天皇制は決して『遠い世界のこと』ではなく、法律や歴史、文化、伝統、アジアと日本の関係、そして1つの魅力のある家族の物語だった」と書いている。天皇家が「魅力のある家族」とは思わないが、私も「興味深い家族」であるとは思う。また、天皇制はこの国の「法律や歴史、文化、伝統、アジアと日本の関係」を映し出す鏡のようなものであるとも思う。明仁天皇と安倍首相、二人はともに戦争責任を負い、戦争犯罪人として訴追されるべきであった者を父、祖父(岸信介)に持つ。しかし、この二人の振る舞いはここまで違い、「対照性」を有している。 二人とも、1945年8月の前と後をつなぎ、戦前・戦後の「連続性」を維持しようとしている。そこに違いはない。明仁天皇は、天皇制-「皇統」をひたすら維持するべく、戦前天皇制=父親の為したことについて「否定」してみせ、それによって“新しい”天皇制が米国-旧連合国及び「主権者=国民」によって認知され、再構築されることを追求してきた。ヴァイニング夫人が書いているように、明仁天皇は「綿密で、思慮深くあられるが、事にあたっては、思い切って伝統を断ち切ることのできる、真の保守主義者の能力を持っておられる」『皇太子の窓』(P172)人であった。他方、安倍首相は祖父・岸信介を肯定=歴史を否定し、変わることのない「日本」を現実世界に引き寄せようと行動を積み重ねている。
そして、この国の多くの人びとは、両者をともに認めている。しかし、「生前退位」をめぐって今、両者の間で静かな(?)つば迫り合い・葛藤が展開されている。五味さんは本書を通じてそれを私たちの前に「可視化」してくれた。ぜひ、多くの人に読んでいただきたい。
最後に。私は、明仁天皇が護憲の立場に立ち、平和をだいじにする気持を持っている人であることは殆ど疑っていない。しかし、私は、真の平和は「共和制」を基礎とする、というカントの主張を信じている。
(注1)児玉誉士夫(雑誌『正論』1975年8月号-「私の内なる天皇」)「私は法的な開戦の責任所在などどうでもいいと思っている。(略)陛下に戦争責任をとっていただきたいなどと言うつもりはない。ただ、陛下に天皇としての責任を明らかにしていただきたかったのである。具体的に言うならば、天皇のご退位を願いしたかったと言うことだ」林房雄『大東亜戦争肯定論』-「『戦争責任』は天皇にも皇族にもある。これは弁護の余地も弁護の必要もない事実だ」石原慎太郎(『自由』1974年4月号-「日本の道義」)「天皇の戦争責任が退位という形で示されなかったことは、天皇制にとっても不幸であった」
(注2)満蒙開拓団は満州事変(1931年)の後、日本政府が旧満州などに送り込んだ農業移民団。約27万人と推計される。国が掲げる「王道楽土(おうどうらくど)」のスローガンに導かれて満州へ渡ったが、多くの人々が、旧ソ連の参戦と日本軍の撤退の際に置き去りにされた。引き揚げの混乱の中、約8万人が亡くなったとみられ、集団自決も起きた。残留孤児・婦人となった人もいた。"}">続きを読む ›
五味さんは、「この本を書こうと思った動機は、この『生前退位』に込められたメッセージは何か、ということだ」と「まえがき」で述べている。そして、自分でその答えも出していて「私は安倍首相の政治姿勢に対する『疑問符』『抵抗』という気がしてならない」(P2)と続けている。
明仁天皇(1989年即位)は、日本国憲法第1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」の規定に基づき即位した初めての天皇である。前天皇、裕仁天皇は大日本帝国憲法第1条「第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」、第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」との規定のもとで即位した。そして、1945年8月15日のポツダム宣言受諾-大日本帝国の敗戦、1946年1月1日の「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本... 他方、明仁天皇は違う。彼は、天皇となり、天皇を生きるうえで、ふたつの課題を自らに課したと推測する。一つは、父である裕仁天皇が為した過ちの「克服」である。二つめは、「象徴天皇」というものの確立とその求心性の獲得である。ふたつの課題は別のものであるようで、その実は表裏一体のものであった。
一つ目の課題は難儀であった。裕仁天皇には明らかに戦争責任があった。それは誰も否定することのできないことであった。それ故、裕仁天皇自身も一時は退位を考えざるを得なかったし、周辺で退位を勧める者もいた。天皇退位問題については、国会で中曽根康弘議員が国会予算委員会(1952年1月31日)で質問もした、と五味さんは本書で紹介している(P151~153)。その質問に対し吉田首相(当時)は「これを希望するがごとき者は、私は非国民と思うのであります」となじった。しかし「議場からは拍手が起こった」(P153)と言う。裕仁天皇の退位を当然とする声は、その当時、左右を問わず一定存在したのである(注1)。
しかし、GHQ-マッカーサーは日本の占領統治のために裕仁天皇を利用することを決め、彼を極東軍事裁判所に訴追することも、退位を迫ることもしなかった。裕仁天皇は戦争責任を免れた。その裕仁天皇と皇后が、1975年9月30日~10月14日にかつての敵国・米国を訪問した。訪米に先立って外務省・宮内庁は、戦争責任、パール・ハーバー攻撃等について追及される恐れなどを想定し、天皇が米国で発する「お言葉」を練りあげた。それを受けて、裕仁天皇は10月2日にホワイトハウスで行われたフォード大統領主催の晩餐会で次のように述べた-「私が、深く悲しみとする、あの不幸な戦争の直後、貴国が、我が国の再建のために、温かい好意と援助の手をさし延べられたことに対し、貴国民に直接感謝の言葉を申し述べる」。米国民がこの言葉をどう受けとめたかは定かではないが、米政府は当然これを受け入れた。
ただ、この「お言葉」をめぐっては、その続きがある。訪米後の10月31日、裕仁天皇は初めての公式記者会見を行った。その中である記者(「ザ・タイムズ」)が、「天皇陛下はホワイトハウスで『私が深く悲しみとするあの不幸な戦争』というご発言がありましたが、このことは戦争に対しての責任を感じておられるという意味に解してよろしゅうございますか。また、陛下はいわゆる戦争責任についてどのようにお考えになっておられますか、おうかがいいたします」と問うた。これに対し裕仁天皇は「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしていないのでよくわかりませんから、そういう問題についてはお答えできかねます」とハグラカシ、回答を拒んだ。裕仁天皇は、自らが大元帥として指導した戦争が引き起こした惨禍、自国民、他国民に与えた甚大な被害、苦痛に対する責任について明確にしなかったのである。それは実質的には責任の否定であり、無責任を決め込んだも同然であった。明仁天皇はそのような父親を批判することはなかったが、しかし、父親が為した罪過を無視・閑却することは却って天皇制を危うくするものであるとの認識を抱いたに違いない。それは明仁天皇が天皇となって以降に選択、実行した「公務」に端的にあらわれている。
明仁天皇が自らに課した二つ目の課題も簡単ではなかったと思われる。日本国憲法第1条は、天皇について「日本国」と「日本国民統合」の「象徴」であると規定した。しかし、「象徴」とは何か、どうあれば、何をすれば「象徴」なのか、「象徴」たり得るのか、具体的な規定は何も書かれていない。明仁天皇は自らでその解答をさぐり、実行していかなければならなかった。天皇と天皇制への国民の関心、親近感も薄れていく中で、求心性をも回復していかなければならなかった。そのために明仁天皇は美智子皇后とともにそれを模索、試行錯誤した。その結果辿りついたのが「国事行為」とは別の、天皇の意向、意思を忍ばせることのできる「公的行為」と、その範囲の拡大であった。明仁天皇・美智子皇后は、ふたつの課題を同時に「解決」していく道として、「公的行為」に精励することにしたのである。
明仁天皇が、上記の目的を達成していくために重ねた「公的行為」は主要に2つある。第1は、戦争犠牲者追悼、第2は、災害被災者等の見舞い、加えて、折にふれての「護憲」の表明である。
安倍首相は「地球儀を俯瞰する外交」と称して各国訪問を繰り返している。直近では、2016年12月末に真珠湾を訪問した。そこで安倍首相は、戦死者(米兵)に哀悼の意を表するとともに、米国の「寛容の心、和解の力」を称えた。1975年10月に裕仁天皇が米国で述べた「お言葉」と瓜二つであることに気づく。
他方、同じく戦死者を追悼、慰霊するために明仁天皇・美智子皇后も各所に足を運んできた。安倍首相は戦後70年に米国アーリントン墓地を訪れたが、天皇・皇后が訪ねたのはパラオ(2015年4月8日~9日)。パラオ国王主催の晩餐会(4.8)において、明仁天皇は次のように挨拶した-「先の戦争においては、貴国を含むこの地域において日米の熾烈な戦闘が行われ、多くの人命が失われました。日本軍は貴国民に、安全な場所への疎開を勧める等、貴国民の安全に配慮したと言われておりますが、空襲や食糧難、疫病による犠牲者が生じたのは痛ましいことでした。ここパラオの地において、私どもは先の戦争で亡くなったすべての人々を追悼し、その遺族の歩んできた苦難の道をしのびたいと思います」。天皇は、日本の植民地支配責任についてまでは言及していないが、曖昧な表現であるとはいえ戦争責任については半ば認めていると言える。
また、2016年安倍首相は真珠湾を訪ねたが、天皇・皇后が訪問したのはフィリピン(2016年1月26日~30日、公式訪問)と長野県阿智村にある「満蒙開拓平和記念館」(11月17日、私的旅行)。マニラに向かうに先立って羽田空港で(1.26)、天皇は、以下のように述べた-「フィリピンでは、先の戦争において、フィリピン人、米国人、日本人の多くの命が失われました。中でもマニラの市街戦においては、膨大な数に及ぶ無辜のフィリピン市民が犠牲になりました。私どもはこのことを常に心に置き、この度の訪問を果たしていきたいと思っています」。
さらに「満蒙開拓平和記念館」を訪れ、引揚者などと交流した天皇は、「こういう歴史(注2)があったことを、経験がない人たちに伝えることが大切だと思います。そういうことを経て今の日本が作られたわけですから」と語りかけた。皇后は「よくお苦しみに耐えてくださいましたね」と声をかけ、労をねぎらった。
天皇・皇后はまた、「沖縄に対して強いこだわりがある」(P192)。皇太子時代の訪問時(1975年7月)には活動家から火炎瓶を投げつけられるという事件もあった。しかし、彼らは事件後も公式日程をきちんとこなした。二人は薩摩藩の「琉球征伐」、明治維新後の琉球王国廃止-併合の歴史を承知していた。また、「遅すぎた聖断」により沖縄が地上戦にまき込まれ、県民の4人に一人が亡くなるという多大の犠牲を強いられたこと、戦後も「天皇メッセージ」により「本土」から切り離され、異民族支配の下に置かれたことをも知っていたに違いない。「沖縄に行く前には『石ぐらいなげられてもよい。そうしたことを恐れず県民の中に入っていきたい』と話していた」(P191)のは、その「歴史」に向き合うという表明であったと思われる。
パラオ、フィリピン、満蒙開拓平和記念館、そして沖縄。いずれも満州事変に始まるアジア・太平洋戦争の戦地であり、関連施設である。天皇・皇后はそこを訪ね、犠牲者を追悼し、遺族らに慰藉の言葉をかけている。明仁天皇は、裕仁天皇の戦争責任を認めてはいないし、それを「肩代わり」するとも述べていない。しかし、戦争の「後始末」は終わっていないと考え、彼なりのやり方-「公的行為」を実行すること-でそれを果たしているとも見える。それを戦争責任の果たし方であると首肯することは私には到底できない。しかし、彼はそれこそが天皇制を生き延びさせる道であると考えているのではないだろうか。
また、明仁天皇は1989年即位して以降、災害現場に足を運び、その犠牲者を弔い、被災者らを慰める「公的行為」を積み重ねてきた。1990年11月、即位礼の5日後に雲仙・普賢岳が噴火し、翌年6月に起きた火砕流で多くの死者・行方不明者が出た。この大惨事の5週間後に天皇・皇后は「定期便の民間機で、民間人に交じって長崎空港に着き、政府専用ヘリコプターで県立島原工業高校のグラウンドに着いた。宿泊を伴うと現地の人たちに手間をかけるとして、日帰りとした。随行員も通常の地方訪問の4分の1の5人だけだった。災害が続いている間に、天皇が現地を訪問するのは、歴史上初めてのことだった」(P178)。
これを嚆矢として以降、天皇・皇后は阪神淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)などが発生する度に被災地に足を運び、慰問を重ねてきた。
加えて明仁天皇・美智子皇后は折にふれて、「憲法を守る」という立場、決意を披瀝してきた。「1989(平成元)年即位後、『朝見の儀』という儀式で、天皇は『皆さんとともに日本国憲法を守る』と表明した」(P161)。さらに「結婚50年となった2009年4月の記者会見で、『象徴とはどうあるべきかということはいつも私の念頭を離れず、その望ましいあり方を求めて今日に至っています。なお大日本帝国憲法下の天皇の在り方と日本国憲法下の天皇の在り方を比べれば、日本国憲法下の天皇の在り方の方が、天皇長い歴史で見た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものと思います』と述べた」(P161~162)。既に2009年段階で、明仁天皇はこんなことを語っていた。自民党改憲草案(2012年)に、「天皇は日本国の元首」(第1条)との規定が入れられることをあたかも予想していたかのような対応と言うべきである。
そして、このような「公的行為」の積み重ねは、確実に天皇に対する国民の見方を変えてきた。「天皇に『尊敬の念を持っている』という人の割合が1998年の19%から徐々に上がり、2013年には34%になった」(P26)。「天皇に『好感を持っている』という人の割合も、平成に入る前年の1988年には22%と低かったが、平成5年である1993年には43%と急増。その後30~40%台を維持している」(P26~27)。
明仁天皇は今、齢80歳を超え、心身の衰えを自覚する中で、自分の歩んできた道が間違いではなかったと考えたと思われる。それと同時に、政治権力を執行している安倍首相の所業、振る舞いを見て危機感を覚えたに違いない。教育基本法を変え、戦争法を制定し、改憲への道をひた走る安倍首相を見て、明仁天皇はそれが「象徴天皇」制を危うくするものであると直観した。そして、「象徴天皇制」を維持するために自分がなしうることは何かを考え、「生前退位」を表明した。「全身全霊をもって象徴としての務めを果たしていくことが難しくなるのではないか」との懸念を表明しつつ、他方で「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われ」ると明言した。予想される「負担軽減」論に釘を刺しつつ、摂政を置くことも否定し、あくまで「生前退位」を希望したのである。それは、政治・軍事的権威、権能から距離を置き、「象徴天皇制」を規定した現行日本国(平和)憲法の下で、それに沿う存在であり続けるための行動と、その自由を担保しようという意思の表明であった。
これに対し、安倍首相は直ぐに明仁天皇の「生前退位」の真意を見抜いたに違いない。そして、安倍首相が打ち出したのは、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」であった。明仁天皇の求める「生前退位」ではなく、あくまで「公務の負担軽減」で対応するというのである。有識者会議で、平川祐弘などは「特に問題と感じますのは、その御自分で拡大解釈した責務を果たせなくなるといけないから、御自分は元気なうちに皇位を退き、次に引き継がせたいというお望みを『おことば』として発表されたこと」と言い、「天皇家は続くことと祈るという聖なる役割に意味があるので、それ以上のいろいろな世俗のことを天皇の義務としての役割とお考えになられるのはいかがなものか」と明仁天皇の「生前退位」をあからさまに否定した。しかし、天皇の「生前退位」表明に対しては圧倒的多数の国民が賛成している。さすがの安倍首相もこの事実を無視することはできない。そこから、明仁天皇一代限りに適用する「特別法」を制定し、「生前退位」を認める方向を打ち出した。これに対し、「天皇は、特例法制定の流れについて『自分が思った方向に行っていないようですね』と語っているという」(P6)。
この天皇の言葉がどこで誰に語られたものか、五味さんは出典を明らかにしていない。しかし、いかにも明仁天皇がこのような思いで事態の推移を見ているだろうとは推測しうる。
五味さんは、「まえがき」で、「皇室や天皇制は決して『遠い世界のこと』ではなく、法律や歴史、文化、伝統、アジアと日本の関係、そして1つの魅力のある家族の物語だった」と書いている。天皇家が「魅力のある家族」とは思わないが、私も「興味深い家族」であるとは思う。また、天皇制はこの国の「法律や歴史、文化、伝統、アジアと日本の関係」を映し出す鏡のようなものであるとも思う。明仁天皇と安倍首相、二人はともに戦争責任を負い、戦争犯罪人として訴追されるべきであった者を父、祖父(岸信介)に持つ。しかし、この二人の振る舞いはここまで違い、「対照性」を有している。 二人とも、1945年8月の前と後をつなぎ、戦前・戦後の「連続性」を維持しようとしている。そこに違いはない。明仁天皇は、天皇制-「皇統」をひたすら維持するべく、戦前天皇制=父親の為したことについて「否定」してみせ、それによって“新しい”天皇制が米国-旧連合国及び「主権者=国民」によって認知され、再構築されることを追求してきた。ヴァイニング夫人が書いているように、明仁天皇は「綿密で、思慮深くあられるが、事にあたっては、思い切って伝統を断ち切ることのできる、真の保守主義者の能力を持っておられる」『皇太子の窓』(P172)人であった。他方、安倍首相は祖父・岸信介を肯定=歴史を否定し、変わることのない「日本」を現実世界に引き寄せようと行動を積み重ねている。
そして、この国の多くの人びとは、両者をともに認めている。しかし、「生前退位」をめぐって今、両者の間で静かな(?)つば迫り合い・葛藤が展開されている。五味さんは本書を通じてそれを私たちの前に「可視化」してくれた。ぜひ、多くの人に読んでいただきたい。
最後に。私は、明仁天皇が護憲の立場に立ち、平和をだいじにする気持を持っている人であることは殆ど疑っていない。しかし、私は、真の平和は「共和制」を基礎とする、というカントの主張を信じている。
(注1)児玉誉士夫(雑誌『正論』1975年8月号-「私の内なる天皇」)「私は法的な開戦の責任所在などどうでもいいと思っている。(略)陛下に戦争責任をとっていただきたいなどと言うつもりはない。ただ、陛下に天皇としての責任を明らかにしていただきたかったのである。具体的に言うならば、天皇のご退位を願いしたかったと言うことだ」林房雄『大東亜戦争肯定論』-「『戦争責任』は天皇にも皇族にもある。これは弁護の余地も弁護の必要もない事実だ」石原慎太郎(『自由』1974年4月号-「日本の道義」)「天皇の戦争責任が退位という形で示されなかったことは、天皇制にとっても不幸であった」
(注2)満蒙開拓団は満州事変(1931年)の後、日本政府が旧満州などに送り込んだ農業移民団。約27万人と推計される。国が掲げる「王道楽土(おうどうらくど)」のスローガンに導かれて満州へ渡ったが、多くの人々が、旧ソ連の参戦と日本軍の撤退の際に置き去りにされた。引き揚げの混乱の中、約8万人が亡くなったとみられ、集団自決も起きた。残留孤児・婦人となった人もいた。"}">続きを読む ›
投稿者 Seaborn 投稿日 2017/2/19
Amazonで購入
コメント 11人のお客様がこれが役に立ったと考えています.
東京新聞の五味記者と言えば、韓国・北朝鮮報道の専門家としての印象が強い。その五味記者が天皇陛下の生前退位に関する本を書いたと知ったときには正直あまりピンと来なかったが、本書を一読して「やはり五味記者だ」と感じた。マレーシアで殺害された金正男氏との単独インタビューや彼とのメールでのやり取りの内容をまとめた「父・金正日と私 金正男独占告白」と通じて、謎に包まれた北朝鮮のロイヤルファミリーの一端に触れることができたが、今回もその手法は同じだ。天皇のこれまでの発言や行動を通じて「生前退位」の背後にある心情や真の意図に迫っていくと同時に、天皇家の苦悩やこれまでの歩みを知ることができる。
そこで明らかになるのは、タイトルに象徴されているように「特例法で一代限りの退位を可能にしようとする安倍首相」との違いだ。生前退位問題は早く片付けて、憲法改正を進めたい思惑が見え隠れするというのが著者の分析。これまで天皇家に対して強い関心をもたなかった当方としては、筆者の考え方をすべて受け入れるには判断する知識が不足している。しかし、少なくとも、中国や韓国と関係が悪化していることは、天皇陛下が望んでおられることではないだろう。東アジア情勢を考える上で新たな視点を与えてくれる一冊だと言える。
そこで明らかになるのは、タイトルに象徴されているように「特例法で一代限りの退位を可能にしようとする安倍首相」との違いだ。生前退位問題は早く片付けて、憲法改正を進めたい思惑が見え隠れするというのが著者の分析。これまで天皇家に対して強い関心をもたなかった当方としては、筆者の考え方をすべて受け入れるには判断する知識が不足している。しかし、少なくとも、中国や韓国と関係が悪化していることは、天皇陛下が望んでおられることではないだろう。東アジア情勢を考える上で新たな視点を与えてくれる一冊だと言える。
投稿者 haidora 投稿日 2017/3/9
今上天皇と下○が対決姿勢なのを知るまでもないですが、確実に天皇の威光を利用しながら
発言力を削いでいく蛭のようなやり口には空いた口が塞がらない。
策謀より姦計の方が正しい言葉に思えるほどに。
発言力を削いでいく蛭のようなやり口には空いた口が塞がらない。
策謀より姦計の方が正しい言葉に思えるほどに。
投稿者 おさるのジョージ 投稿日 2017/2/14
天皇陛下は昨年8月、ビデオメッセージで「生前退位」の意向をにじませ、全国民に衝撃を与えた。ただ、高齢による退位を制度として定着させたい陛下の希望とは裏腹に、安倍政権は一代限りの特例法で乗り切ろうとしている。これは憲法改正の支障にしたくないという意図があるからだろう。一方、野党側は、特例法ではなく、皇室の在り方を定めた「皇室典範」を改正するよう求めており、政治問題化は必至だ。本書は、天皇陛下や皇太子の公式発言を丁寧に追いかけ、昨年末に官邸で開かれた生前退位をめぐる有識者会合での議論を読み込み、幅広い視野からまとめている。尚、天皇陛下の発言や、有識者会合の資料について、短縮サイトが掲載されており、一次資料にすぐにあたれるのは便利だ。
コメント 16人のお客様がこれが役に立ったと考えています.