今日は体調が悪い。久しぶりの不快感。
午後からあまり動かず、寝ようと思ったけどあまり寝られない。
BS「たそがれ清兵衛」をダラ見したが、何度見ても名作は引き込まれる。たそがれの感想は、以前に書いた覚えがあるが、(たぶん消してしまった)感動したので、再度感想を。
清兵衛が最後に対決した男、余吾善右衛門は、もう一人の清兵衛だったかも…という見方に気づいた。
この映画の最大の見所はラストの果し合いシーン。見逃していまいがちなのだが、殺陣のシーンで、途中一瞬、余吾善右衛門が鴨居を見上げる。ここ瞬きしないで、ぜひ確かめて欲しいシーンで本当の一瞬。
このシーンの意味を考えた時、俳優の凄さ・作品の奥深さが分かる。ネタばれではないが、彼が何故鴨居を見上げたのか?を考えると、つまり清兵衛に討たれることを計算して動いていた?という結論になる。清兵衛はそれに気付かないが、観客はそれに気づく演出。
では何故彼が清兵衛に討たれることを望んだのか?彼の人生そのものが、清兵衛の人生と重なる部分があるからというのが答えだと、私は思う。二人とも宮仕えの身、現代だと会社に逆らうことのできないサラリーマン、組織の中で与えられたポジションをひたすらこなす「忠勤」けれど恩義を感じ実直に生きてきたゆえの、「死」なのだ。これほどの不条理を簡単に受け入れられるだろうか?
余吾善右衛門は清兵衛の実直さに好感を抱くが、その甘さ、人の好さに憤りを覚える。けれどかつての自分にも、そういう部分があったはずで、(酒を断って懸命に働いたという告白シーンから)また清兵衛自身が武士として剣の達人であったことが分かると、剣を交えながら考えが変わる。どうせ死ぬなら、清兵衛に討たれて死んだほうがと考えた、そこであの鴨居を見上げる目線になったのではないか?清兵衛の境遇を思うと家族を亡くした自分より、価値がある男だと思ったのでは?
対決シーンでのは鬼気迫る迫力が、それだけでなく、こういった心の変化が、刀を交えるシーン同様流れるような美しさ、凄然さで表現される。この後清兵衛は、余吾善右衛門と対決に勝利し、愛する人を妻に迎えたが、結局その幸せは3年しか続かなかった。明治維新を迎えた激動の時代の中で、清兵衛は戊辰戦争で戦死する。
ここは岸さんのナレーションでしか語られないが、あまりに悲しい。清兵衛も余吾善右衛門も、「もう武士の時代ではない」と分かっていた、分かっていたが自分にはどうすることもできない、ただ実直にその与えられた場で生きるしかなかった…
そういう愚直な生き方を「運がない」というのだろうか?「可哀想」なのだろうか?「悲しい」のだろうか?この作品が温かいのは、清兵衛の娘が「父はそんなことを思ったこともなかった」という語り。山田監督らしい人への優しさにあふれる言葉、最後に清々しく救われる思いがする。日本人の感性というのかなぁ、そういうものが根底にあって凄い映画だと思う。
稀勢の里優勝カッコよかった~神懸り的な。今は気分が少し良くなったので、「直虎」見てます。直虎の感想ですね、本当は書きたいけど…う~ん、難しい。もっと田島とか(→やっぱここね )深い苦悩を描いて欲しかったな。では頑張ってアガサを見るぞと。
)深い苦悩を描いて欲しかったな。では頑張ってアガサを見るぞと。










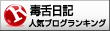




 ミステリというより、独特の日本ホラーみたいな世界観。今見ても色あせないというのかなぁ。古くない。
ミステリというより、独特の日本ホラーみたいな世界観。今見ても色あせないというのかなぁ。古くない。



