
日本の食は本当に安全なのだろうか。元農水官僚で、東京大学大学院教授の鈴木宣弘氏は、「輸入食品へのチェックがザル化している。遺伝子組み換え牛成長ホルモンは、日本国内では許可されていないが、使用しているアメリカの乳製品が輸入されている」という――。(第3回)
※本稿は、鈴木宣弘『農業消滅』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。
牛乳生産量を20%も増加する「牛成長ホルモン」
成長ホルモン(エストロゲンなど)の肉牛への投与による牛肉への残留問題に比べて、乳牛に対する遺伝子組み換え牛成長ホルモン(rBST、recombinant Bovine Somatotropin。別名、rBGH、recombinant BovineGrowth Hormone)のことはあまり議論されていない。
アメリカではrBSTのほうが一般的な呼称だが、成長ホルモンに否定的な見解の人は rBGHと呼ぶ傾向がある。
だから、rBGHという呼び方をしていれば、否定的な見解の人だとわかる。
BST(牛成長ホルモン)は牛の体内に自然に存在するが、これを遺伝子組み換え技術により大腸菌で培養して大量生産し、乳牛に注射すると、1頭当たりの牛乳生産量が20パーセント程度増加するため(一種のドーピング)、牛乳生産の夢の効率化技術としてアメリカで1980年代に登場し、1993年に認可され、1994年から使用が開始された。
ただし、乳牛はある意味「全力疾走」させられて、搾れるだけ搾られてヘトヘトになり、数年で用済みとなる。
そのアメリカでも、1993年に認可されるまでに、人や牛の健康への悪影響や倫理的な問題を懸念する消費者団体・動物愛護団体などの10年に及ぶ反対運動があり、やっと認可にこぎつけたという経緯がある。
日本やEUやカナダでは認可されていない。
rBST(商品名はポジラック)を開発・販売したアメリカのグローバル種子企業のM社は、農水省勤務当時の私を訪ねてきて、日本での認可の可能性について議論した。
とにかく何から何まで、いいことしか言わなかったことを思い出す。
私は、「そんないいことばかり言っていたら、誰も信用しませんよ」と、回答した。そして、かりに日本の酪農家に売っても消費者が拒否反応を示す可能性を話した。
結局、M社は日本での認可申請を見送った。
ところが、認可もされていない日本では、1994年以降、アメリカのrBSTが使用された乳製品が港を素通りして、消費者の元に運ばれている。
所管官庁(農水省と厚生労働省)は双方とも、「管轄ではない(所管は先方だ)」と言っていたのをいまでも鮮明に覚えている。
官庁・製薬会社・研究機関の「疑惑のトライアングル」
私は1980年代から、この成長ホルモンを調査しており、約40年前にアメリカでのインタビュー調査をおこなった。
だが、「絶対に大丈夫、大丈夫」と認可官庁、M社、試験をしたC大学は共に、同じテープを何度も聞くような同一の説明ぶりで、「とにかく何も問題はない」と大合唱していた。
私は、このような三者の関係を「疑惑のトライアングル」と呼んでいる(図表1)。
認可官庁とM社では、M社の幹部が認可官庁の幹部に「天上がり」、認可官庁の幹部がM社の幹部に「天下る」。
そして、M社から巨額の研究費をもらって試験して、「大丈夫だ」との結果をC大学の世界的権威の専門家が認可官庁に提出する。
だから、本当に大丈夫なのかどうかはわからない。
つまり、逆説的だが、「専門家が安全だと言っている」のは、「安全かどうかはわからない」という意味になる。
なぜなら、「安全でない」という実験・臨床試験結果を出したら、研究資金は打ち切られ、学者生命も危険にさらされる可能性すらあり得る。
だから、特に、安全性に懸念が示されている分野については、生き残っている専門家は、大丈夫でなくても「大丈夫だ」と言う人だけになってしまう危険性さえ否定できない。
アメリカでは、認可前の反対運動が大きかったことを受けて、rBSTの認可直後には、全米の大手スーパーマーケットが rBST 使用乳の販売ボイコットを相次いで宣言した。
しかし、rBSTが牛乳に入っているかどうかは識別が困難なこともあり、ボイコットは瞬く間に収束し、1995年には「rBST はもはや消費者問題ではない」と多くのアメリカの識者が、筆者のインタビューに答えた。
また、バーモント州が、rBSTの使用の表示を義務化しようとしたが、M社の提訴で阻止された。
かつ、rBST未使用(rBST-free)の任意表示についても、そういう表示をする場合は、必ず「使用乳と未使用乳には成分に差がない」との注記をすることを、M社の働きかけで、FDA(食品医薬品局)が義務付けた。
通例、次のように表示されている。
「rBST/rbST-free, but, no significant difference has been shown between milk from rBST/rbST-treated and untreated cows」
スターバックス・ウォルマート・ダノンが牛成長ホルモンを排除
ところが、事態は一変した。
rBSTが注射された牛からの牛乳・乳製品には、インシュリン様成長因子(IGF-1)が増加することはわかっていたが、1996年には、アメリカのがん予防協議会議長のイリノイ大学教授が、IGF-1の大量摂取による発がん・リスクを指摘して、さらには、1998年にも科学誌の『サイエンス』と『ランセット』に、IGF-1の血中濃度の高い男性の前立腺がんの発現率が4倍、IGF-1の血中濃度の高い女性の乳がんの発症率が7倍という論文が発表された。
この直後から、アメリカの消費者のrBST反対運動が再燃し、最終的にスターバックスやウォルマートなどが、自社の牛乳・乳製品には不使用にする、との宣言をせざるを得なくなり、rBSTの酪農生産への普及も頭打ちとなった。
そして、もうからなくなったとみたM社は、rBSTの販売権を売却するに至ったのだ。
このことは、自身のリスクを顧みずに真実を発表した人々(研究者)の覚悟と、それに反応して、表示をできなくされても、rBST入りの牛乳の可能性があるなら、その牛乳は飲まない、という消費者の声と行動が業界を動かしたということだ。
その点で、もう一つ注目されるのは、ヨーグルトなどで世界的食品大手のダノンが、rBSTだけでなく、全面的な脱GM(遺伝子組み換え)宣言をアメリカでしたことにあろう。
ダノンは2016年4月、主力の3ブランドを対象に、2018年までにGM作物の使用をやめると発表したのだ。
これまでは砂糖の原料のテンサイや、乳牛の餌となるトウモロコシなどにGM作物を使ってきたが、それ以外の作物に切り替えるという。
日本の酪農・乳業関係者も、風評被害で国産品が売れなくなることを心配して、rBST のことには触れないでおこうとしてきた。
これは人の命と健康を守る仕事にたずさわるものとして当然、改めるべきである。
むしろ、消費者にきちんと伝えることで、自分たちが本物を提供していることをしっかりと認識してもらう必要がある。
「TPPプラス」(TPPを上回る譲歩)の日米FTA(自由貿易協定)の第二弾が結ばれたら、rBST使用乳製品がさらに押し寄せてくる。
TPPレベルで、アメリカ政府の試算では日本への乳製品輸出は約600億円増加すると見込んでいる。
しかし、恐れずに真実を語る人々がいて、それを受けて、最終的には消費者(国民)の行動が事態を変えていく力になることを、私たちは決して忘れてはならない。
アメリカの消費者は、個別表示できなくされても、店として、流通ルートとして「不使用」にして、いくつかの流れをつくって安全・安心な牛乳・乳製品の調達を可能にした。
M社はrBSTの権利を売却した。このことは、日本の今後の対応についての示唆となる。消費者が拒否をすれば、企業をバックに政治的に操られた「安全」は否定され、危険なものは排除できる。
なぜ、日本はそれができず、世界中から危険な食品の標的とされるのか――。
消費者・国民の声が小さいからだろう。今こそ奮起のときである。
---------- 鈴木 宣弘(すずき・のぶひろ) 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 1958年三重県生まれ。82年東京大学農学部卒業。農林水産省、九州大学大学院教授を経て2006年より現職。FTA 産官学共同研究会委員、食料・農業・農村政策審議会委員、財務省関税・外国為替等審議会委員、経済産業省産業構造審議会委員、コーネル大学客員教授などを歴任。おもな著書に『農業消滅』(平凡社新書)、『食の戦争』(文春新書)、『悪夢の食卓』(KADOKAWA)、『農業経済学 第5版』(共著、岩波書店)などがある。 ----------
以上、プレジデントオンライン
日本はアメリカから、やられ放題状態ですね。
日本人はモルモット?
さらに癌も3倍に増えているそうです。
食が問題なのです。
小麦が癌の原因らしいです。
つまり、日本食にもどし、肉も牛乳も危ないとなると
ご飯とみそ汁、メザシ、刺身みたいなメニューにしないと
日本人の健康も守れないし、医療費もすごいです。
医療を半額以下にできるのです。
アメリカの食料植民地を粉砕しないと日本は餌食にされたままだ。
★「今だけ、金だけ、自分だけ」の政治家、官僚は去れ!!
★観たことある?
参政党のユーチューブ、本当に面白い!!感動しますよ。


















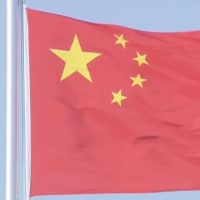


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます