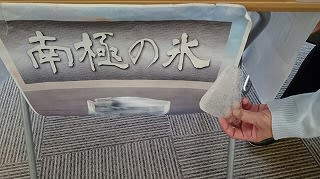。



台風が接近しています。
週初めはかなりの雨が予報されているので
皆さま、お気をつけてください。
私も台風に備え、「いざ」という時のために
準備をしつつあります。
さて、土曜日は朝から雨。
時にはかなりの強さで降りました。
午前中、あきる野市の「秋川橋河川公園バーベーキュ場」で
公共交通に携わる皆さんとの夏季交流会が開催されました。
雨だったので「開催するのか?」半信半疑で現地へ向かうと
多くの皆さんがご参集!
雨は止むことはありまんでしたが、情報交換などなど、
有意義なひと時を過ごすことができました。
議長の挨拶も傘が必要・・・
「水もしたたるいい男!」
かなり強く降っていたので、どこからかエールが飛びました。
会場は予約ができないので、役員の皆さんは朝6時からテント確保していたとのこと!!
本当にお世話になりました。
その後、打ち合わせを1件すませ、夕刻は双葉富士見町内会の納涼祭りへ。

雨の中での準備、本当にご苦労があったと思います。
開催時には小雨になっていましたが・・・・・。
焼き鳥、焼きそば、フランク等々、美味しくいただきました!
地域の皆さんが一体となって開催されるお祭り。
今年も楽しく過ごさせていただきました。
大変、お世話になりました。
月曜日はいよいよ一般質問の通告開始です。
今回は2項目を考えています。