少し前に、息子を幼稚園に迎えに行って、こんなことがありました。
「B君に僕の家に来てもらいたい!」と息子。
すでに約束していたようで、OKをだすと、2人とも大喜びで手をつないで仲良くスキップをしています。
そこへ、これまた息子と仲良しのC君がやってきて、2人に絡みます。
「だったら、C君も誘って2人に来てもらえば?」と私。
息子は聞こえないふりをしたり、C君から逃げたりするので、仲間外れになってしまったC君に申し訳ない気持ちになって、
「聞いてるのっ?」
と大きい声をだすと、息子も大きい声をあげました。涙まじりに。
「今日は、どうしてもB君と2人で遊びたいのっ!!」
C君の気持ちを考えなさい、とか、仲間外れにされたらどんな気持ちになるの?、とか言いかけようとしてハッとする私。私、息子に何かを押し付けようとしてる。
C君には「また今度遊びに来てね」とホローして、ザワザワした気持ちを引きずりながら息子の意思・欲求を尊重しました。
🔹🔹🔹
この時、ある場面が私の脳裏に浮かんでました。
しばらく前に、息子がこのC君のような立場になったことがありました。息子に優しかったA君が、手をつなぎたがる息子の手を払い、別の数名のお友達に抱きつきにいく。
「どうして?」と悲しげに言う息子に、A君はただ「あっち行ってよ」と逃げ回るだけ。
その場面を偶然みた私、猛烈に悲しくなりました。A君に怒りすら湧いた。そんな目に遭っても、仲間外れにされても、物凄く落ち込むわけでもない息子にも苛立ちを感じました。
子どもは気まぐれだから、とか、男の子はそんなものだから、とか、頭ではわかるけど、そんな言葉で心底自分を納得させることなんてできなかった。
その日から、A君に対して、あの場面に対して、ずっとモヤモヤしたものが残り、私の心に小さな小骨が刺さったままでした。
そして、今、息子はあの日のA君と同じことをしている。でも、私は、それを体験してみたいと思ったんです。
心屋仁之助さんのブログのかつてのこの記事を思い出して、それに背中を押されたのもあります。
🔹🔹🔹
でね、
自宅でB君と夕食の時間ギリギリまで楽しそうに生き生き遊ぶ息子を見ていて、気づいたんです。やっと腹に落ちました。
息子も、あの日のA君も、その日、その時の意思に従って、遊ぶ人を選んでいるんだ、ってこと。私は、過去の経験や傷から「仲間外れ」に反応しているだけなんだってこと。
彼らの行為を、「選ぶ力」と呼ぶのか、「仲間外れ」と呼ぶのか。大人が仲間外れと認定すれば加害者と被害者を作り、何かを選ぶことは悪だと思わせ、たまたまその日選ばれなかっただけの人を、「選ばれない人」に認定してしまう。
もともと、子どもたちは、自分が自由に選んでもいいことを知っているから、他人が選ぶことにも実は寛容なんです。
だから、今日選ばれなくて一時的に淋しさを味わっても、明日も選ばれないなんて思っていない、もし選ばれなかったら、自分の方が別の子と遊べばいいことも感覚的に知っている。1人で遊ぶということを含めて。
だから、わが家の息子も、ある時お友達に遊んでもらえなくても、私みたいに傷ついたり、落ち込んだりしないのでしょう。
「うちの子が仲間外れにされた」とか「うちの子がいじめられた」とか「いつも1人で遊んでいるのは何かある」と親が先走れば、子どもは、自分をそうされる子、可哀想な子なんだと認定してしまう。一人遊びはダメなんだと考えてしまう。
親の中にある反応点、傷って、結果として、まっさらの子どもの心に反応点や傷を与えてしまう。
だから、親は、自分のその反応点や傷に自覚的であることが大切なんだと思います。
ちなみに、息子は、「C君には、いつ来てもらおうかなー」と話してますから、彼はC君を排除したかったのではなくて、「家遊びは一対一がいい」という今現在の彼の好みを行使したかっただけのようでした。あの日自分を選ばなかったA君も、相変わらず好きなお友達なんだと教えてくれました。
その日たまたま自分が選ばなかった人への最低限の配慮は、少しずつ洗練されていくのかなって思ってます。
🔹🔹🔹
さて、私たち、大人はどうでしょう。
自分を選ばなかった恋人、自分を選ばなかった友だち、自分を選ばなかった学校、自分を選ばなかった会社にこだわっているのは、「選ばれなかった」という傷がそうさせます。
選ばれない側にばかり立とうとするのも、その心情にばかり同情するのも、「選ばれなかった自分は惨め」「選ばなかった自分は非道」という傷がそうさせます。
「選ばれない」に焦点を当てる前に、そもそも私たちは、自分のために、自分の気持ちに従って、何かを自由に選んできたでしょうか。「選ぶ力」を育て、行使してきたでしょうか。
「選ばれなかった対象」「選ばなかった対象」を傷つけないことばかりに焦点を置いて、自分の選ぶ力を台無しにする。それは、「選ばれない自分」を際だたせるだけなのかもしれません。
人生、選ばれないこともあります。でも、それはたまたまだったり、他からは選ばれる可能性であったり、自分の方が違う何かを選ぶ機会ととらえることもできます。
もっといえば、選ばれなかったということは、自分もそれを選んでないということです。
大人が選ぶ事を自分に許していなければ、子どもにそれを許せるわけがない。人は自分を許せる範囲でしか、他人の事も許せない、そんな存在だからです。
私は、この自分が選ぶということに、今更ながら自覚的でありたいと思っています。
息子とその小さく、自由な友人たちに、大切なことを教えてもらいました。
「B君に僕の家に来てもらいたい!」と息子。
すでに約束していたようで、OKをだすと、2人とも大喜びで手をつないで仲良くスキップをしています。
そこへ、これまた息子と仲良しのC君がやってきて、2人に絡みます。
「だったら、C君も誘って2人に来てもらえば?」と私。
息子は聞こえないふりをしたり、C君から逃げたりするので、仲間外れになってしまったC君に申し訳ない気持ちになって、
「聞いてるのっ?」
と大きい声をだすと、息子も大きい声をあげました。涙まじりに。
「今日は、どうしてもB君と2人で遊びたいのっ!!」
C君の気持ちを考えなさい、とか、仲間外れにされたらどんな気持ちになるの?、とか言いかけようとしてハッとする私。私、息子に何かを押し付けようとしてる。
C君には「また今度遊びに来てね」とホローして、ザワザワした気持ちを引きずりながら息子の意思・欲求を尊重しました。
🔹🔹🔹
この時、ある場面が私の脳裏に浮かんでました。
しばらく前に、息子がこのC君のような立場になったことがありました。息子に優しかったA君が、手をつなぎたがる息子の手を払い、別の数名のお友達に抱きつきにいく。
「どうして?」と悲しげに言う息子に、A君はただ「あっち行ってよ」と逃げ回るだけ。
その場面を偶然みた私、猛烈に悲しくなりました。A君に怒りすら湧いた。そんな目に遭っても、仲間外れにされても、物凄く落ち込むわけでもない息子にも苛立ちを感じました。
子どもは気まぐれだから、とか、男の子はそんなものだから、とか、頭ではわかるけど、そんな言葉で心底自分を納得させることなんてできなかった。
その日から、A君に対して、あの場面に対して、ずっとモヤモヤしたものが残り、私の心に小さな小骨が刺さったままでした。
そして、今、息子はあの日のA君と同じことをしている。でも、私は、それを体験してみたいと思ったんです。
心屋仁之助さんのブログのかつてのこの記事を思い出して、それに背中を押されたのもあります。
🔹🔹🔹
でね、
自宅でB君と夕食の時間ギリギリまで楽しそうに生き生き遊ぶ息子を見ていて、気づいたんです。やっと腹に落ちました。
息子も、あの日のA君も、その日、その時の意思に従って、遊ぶ人を選んでいるんだ、ってこと。私は、過去の経験や傷から「仲間外れ」に反応しているだけなんだってこと。
彼らの行為を、「選ぶ力」と呼ぶのか、「仲間外れ」と呼ぶのか。大人が仲間外れと認定すれば加害者と被害者を作り、何かを選ぶことは悪だと思わせ、たまたまその日選ばれなかっただけの人を、「選ばれない人」に認定してしまう。
もともと、子どもたちは、自分が自由に選んでもいいことを知っているから、他人が選ぶことにも実は寛容なんです。
だから、今日選ばれなくて一時的に淋しさを味わっても、明日も選ばれないなんて思っていない、もし選ばれなかったら、自分の方が別の子と遊べばいいことも感覚的に知っている。1人で遊ぶということを含めて。
だから、わが家の息子も、ある時お友達に遊んでもらえなくても、私みたいに傷ついたり、落ち込んだりしないのでしょう。
「うちの子が仲間外れにされた」とか「うちの子がいじめられた」とか「いつも1人で遊んでいるのは何かある」と親が先走れば、子どもは、自分をそうされる子、可哀想な子なんだと認定してしまう。一人遊びはダメなんだと考えてしまう。
親の中にある反応点、傷って、結果として、まっさらの子どもの心に反応点や傷を与えてしまう。
だから、親は、自分のその反応点や傷に自覚的であることが大切なんだと思います。
ちなみに、息子は、「C君には、いつ来てもらおうかなー」と話してますから、彼はC君を排除したかったのではなくて、「家遊びは一対一がいい」という今現在の彼の好みを行使したかっただけのようでした。あの日自分を選ばなかったA君も、相変わらず好きなお友達なんだと教えてくれました。
その日たまたま自分が選ばなかった人への最低限の配慮は、少しずつ洗練されていくのかなって思ってます。
🔹🔹🔹
さて、私たち、大人はどうでしょう。
自分を選ばなかった恋人、自分を選ばなかった友だち、自分を選ばなかった学校、自分を選ばなかった会社にこだわっているのは、「選ばれなかった」という傷がそうさせます。
選ばれない側にばかり立とうとするのも、その心情にばかり同情するのも、「選ばれなかった自分は惨め」「選ばなかった自分は非道」という傷がそうさせます。
「選ばれない」に焦点を当てる前に、そもそも私たちは、自分のために、自分の気持ちに従って、何かを自由に選んできたでしょうか。「選ぶ力」を育て、行使してきたでしょうか。
「選ばれなかった対象」「選ばなかった対象」を傷つけないことばかりに焦点を置いて、自分の選ぶ力を台無しにする。それは、「選ばれない自分」を際だたせるだけなのかもしれません。
人生、選ばれないこともあります。でも、それはたまたまだったり、他からは選ばれる可能性であったり、自分の方が違う何かを選ぶ機会ととらえることもできます。
もっといえば、選ばれなかったということは、自分もそれを選んでないということです。
大人が選ぶ事を自分に許していなければ、子どもにそれを許せるわけがない。人は自分を許せる範囲でしか、他人の事も許せない、そんな存在だからです。
私は、この自分が選ぶということに、今更ながら自覚的でありたいと思っています。
息子とその小さく、自由な友人たちに、大切なことを教えてもらいました。










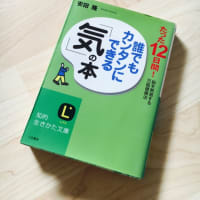

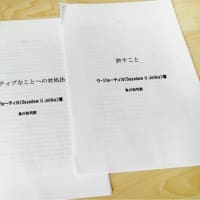
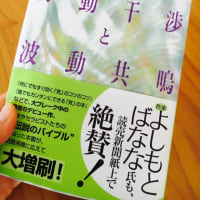




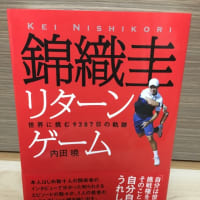
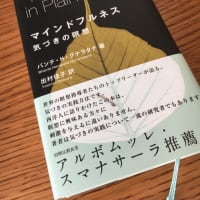
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます