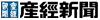聖教新聞(2016/ 6/ 4) 〈駒崎弘樹の未来をつくる〉 第18回 「食品ロス」の活用
2016年6月4日
この深刻な状況をにわかに信じられないという人がいるかもしれません。それは、日本は発展途上国で見られる貧困とは違い、表面的には見えにくいものとして存在しているからです。
例えば、身なりだけを見れば、日本の子どもたちはボロボロの衣服を着ているわけではないので、一見普通の生活をしているように見えます。しかし、食事は1日に1食しかとっていないなど、家庭的に不安定な状況下に置かれている子どもたちがいます。
この問題の解決策の1つとして財源がなくても今すぐにできることがあります。それが「食品ロス」の活用です。食品ロスとは、食べられる状態であるにもかかわらず廃棄される食品のことです。
フランスでは、大量の食品ロスへの対策として、食品廃棄禁止法という法律をつくりました。この法律により、国内の大型スーパーを対象に、売れ残りの食料を廃棄することが禁じられ、代わりに慈善団体へ寄付することが義務付けられることになりました。
国連食糧農業機関(FAO)の統計(2011年)によれば、実は日本も世界有数の食料廃棄国の1つであることが分かります。日本の「食品ロス」の量は、年間で約640万トンにのぼり、これは東京都民が1年間に食する量に匹敵します。これは実に“もったいない”ことだと思います。
日本における食品ロスに関する議論は、この“もったいない”の観点で行われてきました。しかし、「食品ロス」の問題をより効果的に解決していくために、これまでの議論から、もう一歩進めて考えてみたい。それは、食品ロスを、「衣食住の食の部分で困っている子どもたちを助ける」という貧困問題解決と紐付けて、パッケージとして考えていくことです。
いずれにしても、こうした取り組みを踏まえた上で、政治の力がより発揮されていくことが望まれます。そのためには、与野党の壁を超えた心ある政治家の方々の結束が必要です。ぜひとも、子どもの貧困問題に熱心に取り組んできた公明党が中心となって、超党派による議員連盟などが創設され、幅広く議論が交わされていくことを期待しています。
(認定NPO法人フローレンス代表理事)
やっと駒崎氏のコラムを参照できた!
いつも、子どもの貧困というテーマに立ち返らせてくれる、貴重なコラムです。