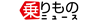踏切を通過する地下鉄銀座線の1000系電車(写真出典:東京メトロ。6月19日の特別列車ではない)。
(乗りものニュース)
「地下鉄の踏切」が日本でただ1か所、東京メトロにあります。ある事情からふだん、電車に乗ってそこを通過することはできませんが、2016年6月19日、この「日本唯一の踏切」を通過する特別列車が運行されました。ちなみにこの特別列車、大変珍しいルートで運行されています。
東京にある日本でただひとつの踏切
2016年6月19日(日)、「地下鉄の踏切」を通過する特別列車が運行されました。
浅草駅と渋谷駅を結ぶ東京メトロの銀座線には1か所だけ、踏切があります。ですがこの路線によく乗る人でも、その踏切を見たことがある人はほとんどいないでしょう。踏切は、列車が乗客を乗せて走る「本線」ではなく、地上に設けられた車庫(上野車両基地)へ向かう「引き込み線」の途中に存在しているからです。「地下鉄の踏切」は、日本でこの1か所しかありません。
この「地下鉄の踏切」は車庫への引き込み線にあるため、ふつう、電車に乗ってそこを通ることはできません。しかし「父の日」であるこの6月19日(日)、上野車両基地を“始発駅”にして、父母への感謝をテーマにした特別列車「メトロワンダフルトレイン」が走行。抽選で招待された合計およそ200人の親子たちが、「踏切を通る地下鉄」という珍しい体験に歓声をあげていました。東京メトロによると、この踏切を通る特別列車の運行は大変珍しいそうです。
また、この日本唯一である踏切には「地下鉄」という以外にもうひとつ、珍しい特徴があります。線路側にも柵状の“遮断機”があるのです。ふだん、線路側の遮断機は下りており、列車が接近するとそれが上昇、あわせて道路側の遮断機が下降します。
線路側にも遮断機がある銀座線らしい理由、そして珍しい終着駅
なぜ日本唯一である「地下鉄の踏切」は、線路側にも遮断機が設けられているのでしょうか。そこには地下鉄のトンネル内に人や動物などが侵入することを防ぐ、ということのほか、“銀座線ならではの理由”があります。
一般的な電車は、屋根上に搭載するパンタグラフを使い、線路上空に張られた架線から、走行に必要な電気を取り入れます(架空電車線方式)。しかし銀座線は、電気の供給源が架線ではなく、線路脇にある3本目のレール(サードレール)。車輪部分にある「集電靴」という部品をそのサードレールに接触させることで、必要な電気を取り入れています(第三軌条方式)。
つまり銀座線は線路の脇、すなわち地上付近に直流600ボルトの電気が流れており、線路に人が侵入した場合の危険度が通常の踏切より高いことから、線路側にも遮断機が設けられ、厳重に管理されているのです。線路側の遮断機に書かれている「高圧通電中 危険」という文字は、そうした銀座線の「第三軌条方式」を象徴するものといえるでしょう。もちろん、「地下鉄の踏切」の道路と交差する箇所ではサードレールが部分的に途切れているため、感電の危険はありません。
ちなみに「第三軌条方式」は高速走行に向かないなどのデメリットがありますが、上空に架線を通す必要がないため、トンネルのサイズを小さくできる(建設費が安い)といったメリットがあります。
またこの「父の日」に運行された、「地下鉄の踏切」経由の上野車両基地発「メトロワンダフルトレイン」は、渋谷駅の先にある車庫まで走行。そこで折り返し、車内で子どもたちが「ありがとうカード」を父母へ手渡したのち、終着駅の「幻の新橋駅」に到着しています。1939(昭和14)年に誕生するもわずか8か月しか利用されず、当時の雰囲気を残したまま車庫などに使われてきたことから、「幻」と呼ばれている新橋駅のホームです。年に一度のこの日、始発駅も終着駅も“特別”な列車でした。
うらやましいなぁ。
どこか旅に出たいなぁ。