昼ごはんは早速のパスタソース…。
ラーメンどんぶりなのはご愛嬌でね。(*^^*)

動けないのにカロリー高! (^_^;)













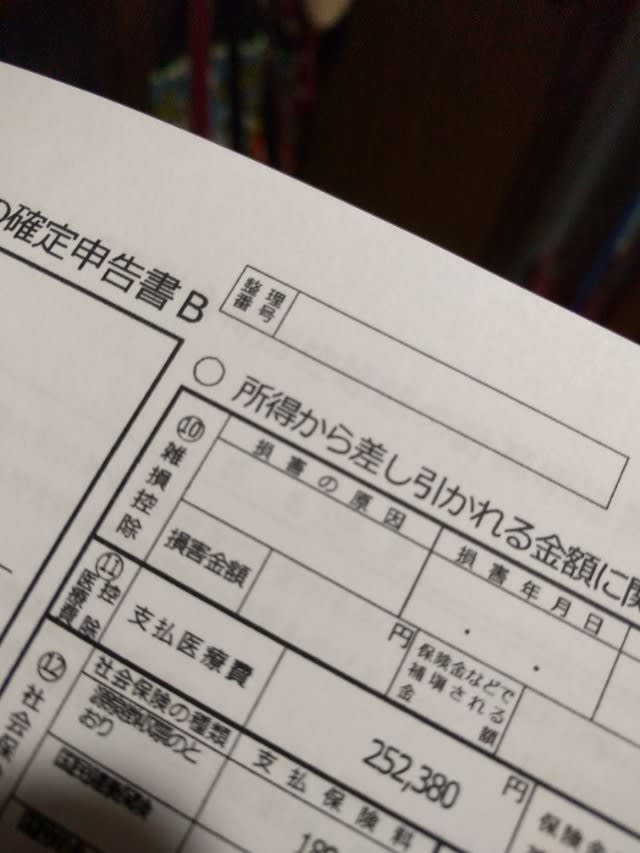

〈オピニオン〉 トランプ米大統領の就任演説を聞いて 青山学院大学 会田弘継教授
2017年1月29日 聖教新聞
米国のドナルド・トランプ新大統領が20日、就任演説を行いました。新政権の政策について、演説から何を読み解けるのか。長年にわたり、ジャーナリストとして米国を見続けた会田弘継・青山学院大学教授に、演説全体の印象と国際社会への影響について語ってもらいました。(聞き手・光澤昭義記者)
――今回の就任演説に、どのような印象を持ちましたか。
会田弘継教授 まず、かなり短かったということ。約16分のスピーチでした。
言葉づかいも、短文でストレートな表現に終始しました。「平易な言葉だが、深みに欠く」とも批判されましたが、彼は米国の中間階層の中でも、とりわけ苦しい生活を強いられ、貧困層に転落しかねない人々の支持を得て、大統領になった。そのことを忘れてはならないでしょう。トランプ大統領は彼らに向けて語り掛けたわけです。
米国社会は今、深刻な分断状況にあります。それは、中間層が近年のグローバル資本主義の中で搾取されてきたことに起因しますが、新大統領はその状況を「Carnage(殺戮)」という言葉で表現しました。
〈演説では「この米国の殺戮は、今、ここで終わります」と〉
この単語は生々しい流血を想起させます。異様な表現ですが、労働者が置かれた状況を、そう捉えているのでしょう。
教育問題に触れた点も重要です。
〈「資金は十分でも、若く輝かしい生徒たちが知識を得られていない教育制度」と〉
米国では、教育と経済の格差が同時に拡大しています。かつては親が貧しくとも、子どもは高水準の教育を受け、貧困から抜け出す道がありました。しかし、今や大学の授業料は高騰し、貧しい家庭の子どもが進学できない。格差が固定されている状況なのです。
――自由や民主主義、法の支配といった高邁な政治理念や建国の歴史などは語られませんでした。
会田 全体を通して、労働者が直面する雇用問題に目を向け、SOSと、救援を求める彼らの叫びを半ば代弁しつつ、「私が助ける」と訴えたスピーチでした。
私はこれまでジャーナリストの立場から4年ごとに米大統領の就任演説を聞いてきましたが、異例の内容だったといえます。ジョージ・W・ブッシュ大統領は2005年1月、イラク戦争の最中での就任演説(2期目)でも政治の理想を訴えました。共和党、民主党を問わず、どの大統領も米国政治の伝統や理想に言及しましたが、今回はありませんでした。また、共和党の“錦の御旗”だった「小さな政府」にも触れませんでした。
トランプ大統領が当選したことは一面では、合衆国憲法が保証する「制御された革命」ともいえます。そもそもは、大英帝国に抑圧されてきた人民が自由や人権を勝ち取ったというのが米国建国の歴史です。その観点からすれば、苦境に立つ(白人)労働者たちによって“革命的な国家”という本来の姿が現れたともいえます。
白人中間層の危機的な状況について、トランプ大統領が選挙期間中から問い掛けてきたことは重大な意味を持ちます。ただ、その問題が解決されるかというと、指名閣僚の顔ぶれを見て、少し違う気がしました。特に、金融大手、エネルギー最大手の出身者が労働者の支持で勝った政権の要職を占めており、説得力に欠けるといわざるを得ません。
――就任演説では「米国第一主義」を政権運営の核心に据えると表明しました。国際的な自由貿易を主導してきた米国が保護主義へと政策を転換することに対し、各国で警戒感が広がっています。
会田 グローバリゼーションの進展によって世界経済が底上げされ、中国やインドでは新たな中間層が生まれました。生活水準も医療環境も向上している点はグローバリゼーションのプラスの側面ですが、米国はじめ先進国では、トップ1%ほどの富裕層がどんどん豊かになる一方、こうしたグローバル化の流れに取り残された中間層との格差が一段と広がってしまいました。
取り残された人々をどう支援するかは先進国共通の課題ですが、だからといって保護主義に走るべきではありません。自由貿易がなければ、そもそも世界全体の繁栄も実現し得ないからです。
1929年、世界大恐慌が起きた際に保護主義が台頭。大国がブロック経済圏をつくりましたが、それが国際社会内の対立・分裂を先鋭化してしまいました。そうした歴史の反省に立つ必要があるでしょう。よりよい自由貿易のあり方を問い直す時代に突入したということだと考えます。
――トランプ大統領は23日、TPP(環太平洋経済連携協定)離脱の大統領令に署名しました。
会田 保護主義への転換は既に始まっているといえます。もはやTPPの発効は困難でしょう。
一方で、トランプ大統領の政策が多くの矛盾を抱えていることも確かです。例えば、保護主義政策の一環として関税を上げれば、国内の物価が上昇します。そのあおりを食うのは労働者です。大統領の政策が実現するほど、矛盾が明らかになり、長期的には米国経済が大きな痛手を被ることになりかねないのです。
既に世界経済は長期停滞に入っていると指摘する識者もいます。トランプ政権は大規模なインフラ(社会基盤)向け公共投資によって、雇用増と経済活性化を実現しようとしていますが、それが全ての解決策にはなり得ないでしょう。世界経済の安定に向けて、国際社会全体で取り組むことが求められます。
――G7(主要先進7カ国)のような枠組みが一層重要となるのでしょうか。
会田 G7の先進各国が危機に際して、どう行動するかは、中進国や新興国にとっては前例となります。数十年後には同じ問題に直面するからです。雇用問題一つとっても、ここで先進国グループが解決策を示せなければ、混乱はずっと続くでしょう。米国だけでなく、英国、フランス、イタリアなど欧州の先進国で自国中心主義の動きが極端に強まっているだけに、G7でも特に、ドイツや日本の役割が重要になると思われます。
――25日には、メキシコとの国境沿いに壁を築くよう命じる大統領令にも署名しました。
会田 残念なのは、中間階層の人々が苦境に立たされると、国内に“敵”を探す傾向があることです。どうしても「排除の思想」が出てきてしまう。現在の米国では、ヒスパニック(中南米系)やイスラム系の移民は白人中間層の職を奪う存在と見なされており、トランプ大統領は、それを利用しているといえます。
――外交・安全保障政策は、どんな特徴をもつと考えられますか。
会田 トランプ大統領が、いかなる外交観を持つのかは分かりません。
米国は第2次大戦以降、自由主義圏の盟主を担ってきました。トランプ大統領にも同じリーダーシップを発揮するように期待したいけれど、まだはっきりしない現状です。
日本に対しては、大統領選挙の最中から米軍駐留経費の負担増を求める発言を繰り返してきましたが、日本の負担額は既に他の同盟国とは比較にならないほど高い。幸い、(国務省や国防総省など)米政府の関係者は、そのことを理解していますが、沖縄の海兵隊をグアムに移転するプランが端的に示しているように、米軍が日本から徐々に退いていくという流れは今後も続くかもしれません。
――アジア地域は、中国の海洋進出や北朝鮮の核開発問題に直面しています。日米同盟の重要性も含めて、日本政府にはトランプ大統領に理解してもらう努力も必要ではないでしょうか。
会田 新政権に入った軍出身のジェームズ・マティス国防長官はじめ高官たちは、しっかりした安全保障観に立っています。彼らを通じて、正確な情報をトランプ大統領に把握してもらうよう努力するべきでしょう。
トランプ大統領が、外交を「ディール(取り引き)」として扱うのでは、という懸念は常にあります。例えば、ロシアがシリア国内の過激派組織「IS(イスラム国)」と戦う見返りに、クリミア併合に対する対ロ制裁を解除することがあるかもしれません。(武力による国境線の変更は認められないという)国際法の原則を取り引きの材料にしてしまえば、法の支配は崩れてしまいます。
日米両国は、緊密なコミュニケーションを取り合いながら、自由や民主主義に基づく国際秩序を共有しなければなりません。
大統領就任式と併行して、全米各地で反トランプの集会やデモが盛ん。米国社会の亀裂があらわになったが融和の兆しはない。会田教授はトランプ現象について「知識人、エリートは大失敗した。労働者の気持ちが分からなかった」と自戒を込める。
ご感想をお寄せください opinion@seikyo-np.jp
約10日前の記事だけどね。
アメリカ国内で、いつまでトランプ人気が続くのか…。
そして世界はどうなってしまうのか…。 
1月12日付のウォールストリート・ジャーナル紙で、同紙論説委員のフェイスが、韓国外交の漂流を懸念し、北朝鮮が近々危機を起こした場合、韓国は対応できるのだろうかと述べています。主要点は次の通りです。
スキャンダルが発覚して3カ月、韓国政治が混迷している。朴槿恵は弾劾され、今や大統領の運命は憲法裁判所の手中にある。北朝鮮の核脅威への対処に、韓国は不可欠の存在である。韓国がその役割を果たすためには安定した政治が必要だ。韓国は戦略的思考、強い軍、米国との健全な関係、日本との一層深い関係を持つことが必要だ。
朴槿恵は当初習近平に接近したが、その後それが無用だと分かり、米国の仲介も得た日本からの求めに応じ、2015年末に慰安婦について日韓で合意した。しかし朴槿恵は政治スキャンダルに見舞われ、左派は今や合意を破棄すべきだと主張している。左派活動家達が釜山日本総領事館前に慰安婦像を立てたことに抗議して、日本は大使と総領事を召還した。
報道によれば、韓国は、米国が提案していた日米韓3カ国の対潜水艦合同演習への参加を拒んだ。背景に反日感情の高まりと日米との関係強化に対する中国の懸念があったと見られている。6カ月前には、韓国が初めて日米と三国ミサイル防衛演習に参加し、その後、日韓は引き延ばされてきた防衛情報保護取決めを締結した。その直後に朴槿恵にスキャンダルが持ち上がった。
最大の問題は、韓国が決定通りTHAADミサイル防衛システムを配備するかである。次期大統領候補達は異なる考えを持っている。一方、中国は、韓国の化粧品の輸入などを規制し、9日には中国軍用機が韓国の防空識別圏を通過した。
次期大統領世論調査でトップにある野党の文在寅などはTHAADの配備延期を主張し、大統領になれば訪朝し、北朝鮮に年間1.3億ドルをもたらすとされる開城工業団地を再開すると述べている。
北朝鮮は、米国を攻撃する能力を持つICBMを発射するとみられている。選挙戦では韓国をフリー・ライドと批判していたトランプは、大統領選に勝った後は韓国を称賛し米韓同盟の重要性を再確認している。が、金正恩が近い将来に危機を起こした場合、韓国は対応できるのだろうか。
出 典:David Feith‘North Korea Advances, South Korea Drifts’(Wall Street Journal, January 12, 2017)
http://www.wsj.com/articles/north-korea-advances-south-korea-drifts-1484243137
韓国の外交が漂流を始め、米国や日本等にとり大きな懸念材料になりつつあることはその通りです。論説では、具体例として、慰安婦合意を巡る最近の日韓関係の悪化や日米韓対潜水艦作戦合同演習への韓国の不参加が挙げられています。三国対潜合同演習は、北朝鮮の潜水艦能力の向上が懸念され、昨年12月の日米韓次官補級の防衛実務者協議で提案されたものでした。
最大の問題は、ポスト朴槿恵でも韓国外交の方向が改善する見通しが全くないことです。大統領選挙は弾劾裁判がどうなるかに拘わらず本年12月19日までには行われます。1月16日の次期大統領人気世論調査では、最大野党「共に民主党」の文在寅前代表が26.1%で1位、潘基文前国連事務総長が22.2%で2位、3位は「共に民主党」の李在明城南市長で11.7%、4位は第二野党「国民の党」の安哲秀前代表7.0%でした。
潘は、THAADの配備は支持するが、慰安婦合意については「合意が少女像の撤去と関係があるなら誤り」と世論迎合の発言を繰り返し、日韓合意を守る気はないようでした。しかし2月1日、その潘が大統領選への不出馬を表明しました。一方、人気調査1位で、廬武鉉左派政権の側近だった文はTHAADの配備延期を主張し、対北朝鮮融和政策、慰安婦合意の再交渉等を主張するなど、政策について問題があります。
米大統領選中は、対北朝鮮対話に前向きなトランプを称賛する論評を出していた北朝鮮ですが、目下はトランプの出方を見定めているようです。金正恩は一定の合理主義者です。早晩行うと見られるICBMの実験についても種々の計算をしているのでしょう。他方、ICBM発射に対してトランプはすかさず「そのようなことは許さない」とツイッターで述べています。なお、国防長官に指名されているマティスは、12日の議会承認公聴会で、北朝鮮によるICBM開発について「深刻な脅威で、軍事的対応も選択肢の一つ」と述べました。
韓国の内政は当面憲法裁判所と特別検察官を中心に動いています。そのうち特別検察官チームは大々的に捜査範囲を広げるつもりの様です。同チームは16日、「贈賄」などの容疑で李在鎔サムスン電子副会長の逮捕状を請求しました。これは韓国財界に衝撃を与え、次はSKかロッテかと憶測されています。
これまで一貫して対日強硬であった尹炳世外相が13日の国会で「外交関係に関するウィーン条約によれば、他国の公館前に問題となる造形物を設置するのは望ましくない」と証言したところ、政界などから「親日派」、「売国行為」だと非難する声が一斉に出始めました。韓国の状況は全く変わっていません。流石にこれには朝鮮日報が「日本との外交関係における根本問題は、何よりもまずわれわれの国力が日本に及ばないことにある。日本を追い越すには国民の誰もが骨を削るような努力をしなければならないが、デモに参加して感情を表に出すだけでは何も変わらない。政治家も同じだ」と批判しています。
アジアの隣国同士、いつまでいがみ合うんだろう。
