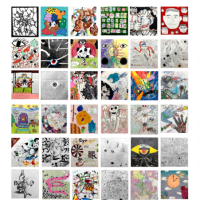ジブリの作品は、子育てと共にありました。幼稚園の運動会の入場行進は「となりのトトロ」の「♪歩こう、歩こう、私は元気」で、背が一番小さな三歳の次男が果たして、きちんと歩けるのかとどきどきしながら、トトロの音楽を聞きました。この歌の作詞は、中川李枝子。幼稚園の保護者なら、多くの方が知っている、ロングセラー絵本「ぐりとぐら」シリーズの作者です。トトロの主人公、さつきの妹、メイは、まさにこうした幼稚園の子どもたちの象徴のような存在でした。あの不安定で元気で、いつこけてもおかしくない動き。なんでも大騒ぎする元気なメイと、対して姉のしっかり者のさつきの凸凹に、きょうだいの良さを我が家に当てはめて見られたおうちも多かったことでしょう。
と言っても、私はジブリ映画が公開されたらすぐ見に行くタイプではなく、もっぱらテレビで見て知るタイプ。ですので、宮崎駿さんのことも、ファンのように詳細にはよく知りません。
ジブリのことで、有り難いなと思うことは、直木賞作家、野坂昭如氏の「火垂るの墓」をアニメにしてくれたこと。これは宮崎さんでなく、高畑勲さん。ジブリのもう一人の主です。平たい言い方になりますが、アニメの「火垂るの墓」があるおかげで、「戦争」についてのことを、お母さん方が情報の一つとして持てる、この意義は大きいと思います。余程、意識しないと、平和な暮らしの中で、ネガティブな戦争ということについて、お互い話すことはないでしょう。けれども、「火垂るの墓」の兄妹の姿を見ながら、自分の子どもがこういう状況だったら…と少なくとも、子育て中の人なら、この映画を見れば考えながら見ると思います。「戦争」を伝えることは、中々、難しい時代になりましたが、この
「火垂るの墓」があることは、とても意味のあることと思います。
さて、引退宣言をした宮崎さんが、テレビにとなると、ファンにしてみれば、それは大変なことですよね。私はたまたま、テレビがついていた延長で見た感じですが…これが中々、面白かった。理由は二つあります。
一つは、「毛虫のボロ」という作品をCGで作るための作業で、宮崎さんがCGで動き出す「毛虫のボロ」に対して、ダメ出しをします。ボロが誕生し、周りを見るために「顔を動かす」のですが、この「顔の動き」にダメ出しをする宮崎さん。その風景は、まるで演劇のダメ出しのようで、思わず見入ってしまいました。
何がダメかというと、宮崎さん曰く「初めて世界を見るボロが、そんなに早く首を回すわけはない」というようなことだったと思います。その通りで、CGの動きというのは、いわば物理的な計算式の果ての動きでしょうから、「初めての世界を目の当たりにする」毛虫のボロの「ものを見る」といった「個別」で「未熟」な赤ちゃんの手触りは、出ないわけです。宮崎さんは「メイだよ、メイ。」と言ってましたが、まさにそうで、子どもを知る手触り感がCGでは出てこない。なるほど、宮崎駿のアニメというのは、それぞれの登場人物の「個別」の動きの演出も兼ねているのだと思うと、これはものすごいことでないか、とやっと、この番組を見て、思った次第です。演劇ならば、それぞれの役者ならではの動きがあり、それが演出家の思うようになるところとならないところと、そのせめぎ合いが面白い共同作業のようなところがありますが、アニメの場合、絵は役者のように動いてくれないのだから、自分で動きをつける、それも、先に言った「毛虫のボロ」ならではの。これは凄いことです。
さて、番組を見入った二つ目の理由は、若手の方たちが、ある映像を宮崎さんに見せているシーンでした。それは頭がない、ゾンビのような、けれど、頭がないから、人間ではあり得ない、独特の動きをする生きものが動く映像でした。
宮崎さんはゾンビのような動きの画像を見て「非常に不愉快、いのちに対する冒涜」と怒りました。身近な知り合いに障がいを持った方がいて、ハイタッチをするのも難しい、とも言われました。画像を見ながら、そういう方たちのことが頭によぎるのは、やはり、本当に「動く」ということ一つがどれだけ大変か、宮崎さんがわかっているからでないかと思いました。「動くということ」を考え続けているから、「怒り」になるのでしょう。「絵」を「動かす」プロの宮崎さんにしてみれば、どれだけ障がいを持っている人が、「ハイタッチ」をするのに、一期一会のような動きをされるのかを、いつも切実に感じているのではと思いました。
というわけで、これまで漠然と宮崎駿作品を見ていましたが、この番組から、あらためて「絵」が「動く」ということの奥深さを感じた次第です。
「毛虫のボロ」の初めての「振り向く」動き、どんな風に、その「動き」から「初めての世界」を見つめるのか、興味津々でいます。
と言っても、私はジブリ映画が公開されたらすぐ見に行くタイプではなく、もっぱらテレビで見て知るタイプ。ですので、宮崎駿さんのことも、ファンのように詳細にはよく知りません。
ジブリのことで、有り難いなと思うことは、直木賞作家、野坂昭如氏の「火垂るの墓」をアニメにしてくれたこと。これは宮崎さんでなく、高畑勲さん。ジブリのもう一人の主です。平たい言い方になりますが、アニメの「火垂るの墓」があるおかげで、「戦争」についてのことを、お母さん方が情報の一つとして持てる、この意義は大きいと思います。余程、意識しないと、平和な暮らしの中で、ネガティブな戦争ということについて、お互い話すことはないでしょう。けれども、「火垂るの墓」の兄妹の姿を見ながら、自分の子どもがこういう状況だったら…と少なくとも、子育て中の人なら、この映画を見れば考えながら見ると思います。「戦争」を伝えることは、中々、難しい時代になりましたが、この
「火垂るの墓」があることは、とても意味のあることと思います。
さて、引退宣言をした宮崎さんが、テレビにとなると、ファンにしてみれば、それは大変なことですよね。私はたまたま、テレビがついていた延長で見た感じですが…これが中々、面白かった。理由は二つあります。
一つは、「毛虫のボロ」という作品をCGで作るための作業で、宮崎さんがCGで動き出す「毛虫のボロ」に対して、ダメ出しをします。ボロが誕生し、周りを見るために「顔を動かす」のですが、この「顔の動き」にダメ出しをする宮崎さん。その風景は、まるで演劇のダメ出しのようで、思わず見入ってしまいました。
何がダメかというと、宮崎さん曰く「初めて世界を見るボロが、そんなに早く首を回すわけはない」というようなことだったと思います。その通りで、CGの動きというのは、いわば物理的な計算式の果ての動きでしょうから、「初めての世界を目の当たりにする」毛虫のボロの「ものを見る」といった「個別」で「未熟」な赤ちゃんの手触りは、出ないわけです。宮崎さんは「メイだよ、メイ。」と言ってましたが、まさにそうで、子どもを知る手触り感がCGでは出てこない。なるほど、宮崎駿のアニメというのは、それぞれの登場人物の「個別」の動きの演出も兼ねているのだと思うと、これはものすごいことでないか、とやっと、この番組を見て、思った次第です。演劇ならば、それぞれの役者ならではの動きがあり、それが演出家の思うようになるところとならないところと、そのせめぎ合いが面白い共同作業のようなところがありますが、アニメの場合、絵は役者のように動いてくれないのだから、自分で動きをつける、それも、先に言った「毛虫のボロ」ならではの。これは凄いことです。
さて、番組を見入った二つ目の理由は、若手の方たちが、ある映像を宮崎さんに見せているシーンでした。それは頭がない、ゾンビのような、けれど、頭がないから、人間ではあり得ない、独特の動きをする生きものが動く映像でした。
宮崎さんはゾンビのような動きの画像を見て「非常に不愉快、いのちに対する冒涜」と怒りました。身近な知り合いに障がいを持った方がいて、ハイタッチをするのも難しい、とも言われました。画像を見ながら、そういう方たちのことが頭によぎるのは、やはり、本当に「動く」ということ一つがどれだけ大変か、宮崎さんがわかっているからでないかと思いました。「動くということ」を考え続けているから、「怒り」になるのでしょう。「絵」を「動かす」プロの宮崎さんにしてみれば、どれだけ障がいを持っている人が、「ハイタッチ」をするのに、一期一会のような動きをされるのかを、いつも切実に感じているのではと思いました。
というわけで、これまで漠然と宮崎駿作品を見ていましたが、この番組から、あらためて「絵」が「動く」ということの奥深さを感じた次第です。
「毛虫のボロ」の初めての「振り向く」動き、どんな風に、その「動き」から「初めての世界」を見つめるのか、興味津々でいます。