新茶はすがすがしい初夏の風物詩、お茶屋さんには、香り高い新茶が販売されています。現代はお茶は買う物ですが、私の母の子供時代、昭和初期の農家では、お茶はそれぞれの家で作られていたそうです。

※当時お茶の木は畑の風景の一部でした。
当時はどこの農家でも、畑の端には必ずお茶の木が植えられていて、自宅で飲むお茶は全て自宅で製茶していました。収穫された茶の葉を蒸篭で蒸して、「ほいろ」で乾燥し、撚って製茶します。

※古民家・民族資料館に展示されている「製茶ほいろ」
今は民族資料館でしか見られなくなった「ほいろ」ですが、当時の農家には、土間や物置に必ずこの「ほいろ」があり、初夏になると製茶の為に使われました。「ほいろ」の中にはクヌギの木で作られた上質な桜炭が焚かれました。現代の電気ほいろ で、その構造をご確認下さい。
上部の木枠には和紙が張られ、その上に茶葉をのせ、手の平で揉みながら乾燥させるので、かなりな力仕事で祖父は汗だくになって製茶していたそうです。紙は貴重品であった時代ですので、木枠に張る和紙は和紙製の“こいのぼり”を使用していたそうです。今では「ほいろ」を見る機会はありませんが、本郷ふじやま公園 の古民家の土間には、当時のままの姿が保存されていました。
 ご参考に名人の製茶をこちらで、ご覧下さい。
ご参考に名人の製茶をこちらで、ご覧下さい。

※ふじやま公園内の旧小岩井邸
 新茶はその年の最初に生育した新芽を摘み取ったお茶のことで「一番茶」とも呼ばれています。新茶のさわやかですがすがしい香りは、「二番茶」「三番茶」に比べて苦渋いカテキンやカフェインが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多い傾向にあるのが、その理由のようです。
新茶はその年の最初に生育した新芽を摘み取ったお茶のことで「一番茶」とも呼ばれています。新茶のさわやかですがすがしい香りは、「二番茶」「三番茶」に比べて苦渋いカテキンやカフェインが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多い傾向にあるのが、その理由のようです。
立春(2月4日)から数えて88日目の日を「八十八夜」に摘み採られたお茶を飲むと、一年間無病息災で元気に過ごせると言い伝えがあります。
現代では、お茶はペットボトルでしか飲まない家庭も増えていると聞きます、急須が家にないことも当たり前な生活になってゆくのかも知れません。でも淹れ方で味わが変化する茶葉は美味しく、とても楽しいですし、地球にも優しいですね♪
 美味しいお茶を更に美味しくする常滑焼の急須については、コチラ をご覧下さい。
美味しいお茶を更に美味しくする常滑焼の急須については、コチラ をご覧下さい。
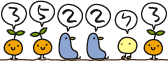
横浜桜木町シベリアのコテイベーカリーHP

※当時お茶の木は畑の風景の一部でした。
当時はどこの農家でも、畑の端には必ずお茶の木が植えられていて、自宅で飲むお茶は全て自宅で製茶していました。収穫された茶の葉を蒸篭で蒸して、「ほいろ」で乾燥し、撚って製茶します。

※古民家・民族資料館に展示されている「製茶ほいろ」
今は民族資料館でしか見られなくなった「ほいろ」ですが、当時の農家には、土間や物置に必ずこの「ほいろ」があり、初夏になると製茶の為に使われました。「ほいろ」の中にはクヌギの木で作られた上質な桜炭が焚かれました。現代の電気ほいろ で、その構造をご確認下さい。
上部の木枠には和紙が張られ、その上に茶葉をのせ、手の平で揉みながら乾燥させるので、かなりな力仕事で祖父は汗だくになって製茶していたそうです。紙は貴重品であった時代ですので、木枠に張る和紙は和紙製の“こいのぼり”を使用していたそうです。今では「ほいろ」を見る機会はありませんが、本郷ふじやま公園 の古民家の土間には、当時のままの姿が保存されていました。
 ご参考に名人の製茶をこちらで、ご覧下さい。
ご参考に名人の製茶をこちらで、ご覧下さい。
※ふじやま公園内の旧小岩井邸
 新茶はその年の最初に生育した新芽を摘み取ったお茶のことで「一番茶」とも呼ばれています。新茶のさわやかですがすがしい香りは、「二番茶」「三番茶」に比べて苦渋いカテキンやカフェインが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多い傾向にあるのが、その理由のようです。
新茶はその年の最初に生育した新芽を摘み取ったお茶のことで「一番茶」とも呼ばれています。新茶のさわやかですがすがしい香りは、「二番茶」「三番茶」に比べて苦渋いカテキンやカフェインが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸(テアニン)が多い傾向にあるのが、その理由のようです。立春(2月4日)から数えて88日目の日を「八十八夜」に摘み採られたお茶を飲むと、一年間無病息災で元気に過ごせると言い伝えがあります。
現代では、お茶はペットボトルでしか飲まない家庭も増えていると聞きます、急須が家にないことも当たり前な生活になってゆくのかも知れません。でも淹れ方で味わが変化する茶葉は美味しく、とても楽しいですし、地球にも優しいですね♪
 美味しいお茶を更に美味しくする常滑焼の急須については、コチラ をご覧下さい。
美味しいお茶を更に美味しくする常滑焼の急須については、コチラ をご覧下さい。横浜桜木町シベリアのコテイベーカリーHP









