 NHK大河ドラマ『龍馬伝』では、大浦お慶が大活躍です。激動の幕末に波乱の生涯を送った大浦慶は日本のお茶を外国に輸出し、日本茶輸出貿易の先駆けとなりました。
NHK大河ドラマ『龍馬伝』では、大浦お慶が大活躍です。激動の幕末に波乱の生涯を送った大浦慶は日本のお茶を外国に輸出し、日本茶輸出貿易の先駆けとなりました。お慶は25歳の時、上海行きのジャンク船の椎茸箱に身をひそめて密航し、茶の大量注文を得ます。受注数6トンは九州・嬉野茶だけでは間に合わず、九州全体から集められました。そのお茶は横浜山下町の“お茶場”と呼ばれる再生工場で中国茶に作りかえられ、はるばるイギリスに渡りました。
横浜市中区山下町辺りには当時多くの“お茶場”があり、最盛期には数千人の女性が働いていたました。その大半は、近隣に住む女性たちで、毎朝3時、4時から横浜公園に集まり、日雇いの仕事を得て、過酷なお茶場での長時間労働に就きました。
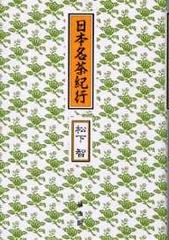
 【茶の再生方法】熱せられた直径約60センチほどの鉄釜に2キロ余のお茶を投入、熱しながら40分ほど攪拌して乾燥、更に紺青・黄土藍青などで着色して仕上げます。この技術は中国式のため監督は中国人の担当していました。
【茶の再生方法】熱せられた直径約60センチほどの鉄釜に2キロ余のお茶を投入、熱しながら40分ほど攪拌して乾燥、更に紺青・黄土藍青などで着色して仕上げます。この技術は中国式のため監督は中国人の担当していました。お茶場の労働は過酷なもので、炉と鉄釜が200~300基も並ぶ熱気の中、監督が棍棒を持って監視しているので一瞬たりとも休むこともきないものでありました。高温の夏場には卒倒する人もいましたが、井戸端で頭から水を浴びせられて再び連れ戻され、作業に従事させられました。
日雇いで、1日10~12時間の労働、賃金が平均天保銭17枚ほどといいますから(約1500文弱)現在の金額にして1万円ほどでしょうか。当時の大工さんの日当と同じですので、過酷ではありましたが当時の女性にとっては割りの良い仕事でもあったのではないでしょうか。先を争うように仕事を求めた様子が次の労働歌からしのばれます。
 野毛山の鐘がゴンと鳴りゃ、
野毛山の鐘がゴンと鳴りゃ、港が白む、
早く行かなきゃ、カマがない
 慈悲じゃ情じゃ 開けておくれよ火番さん
慈悲じゃ情じゃ 開けておくれよ火番さんきょうの天保をもらわなきゃ
なべ釜へっつい みな休む
箸と茶碗がかくれんぼ
飯盛りしゃくしが隠居して
お玉じゃくしが身を投げる

野毛山の鐘 は「野毛山 時の鐘」「伊勢山 時の鐘」とも呼ばれていて現在の成田山横浜別院の辺りにありました。成田山の職員の方のお話によれば鐘は2時間に1回打ち鳴らされ、住民に時を知らせていたそうです。残念ながら現在、時鐘楼の痕跡は何も残っていません。
 大浦お慶の日本茶輸出貿易での華々しい成功、その裏には、横浜の女性達の“女工哀史”がありました。
大浦お慶の日本茶輸出貿易での華々しい成功、その裏には、横浜の女性達の“女工哀史”がありました。 【参考資料】「日本名茶紀行」「日本茶輸出100年史」「横浜と女性たちの150年」「横浜と女性史」「横浜市史稿」
【参考資料】「日本名茶紀行」「日本茶輸出100年史」「横浜と女性たちの150年」「横浜と女性史」「横浜市史稿」









