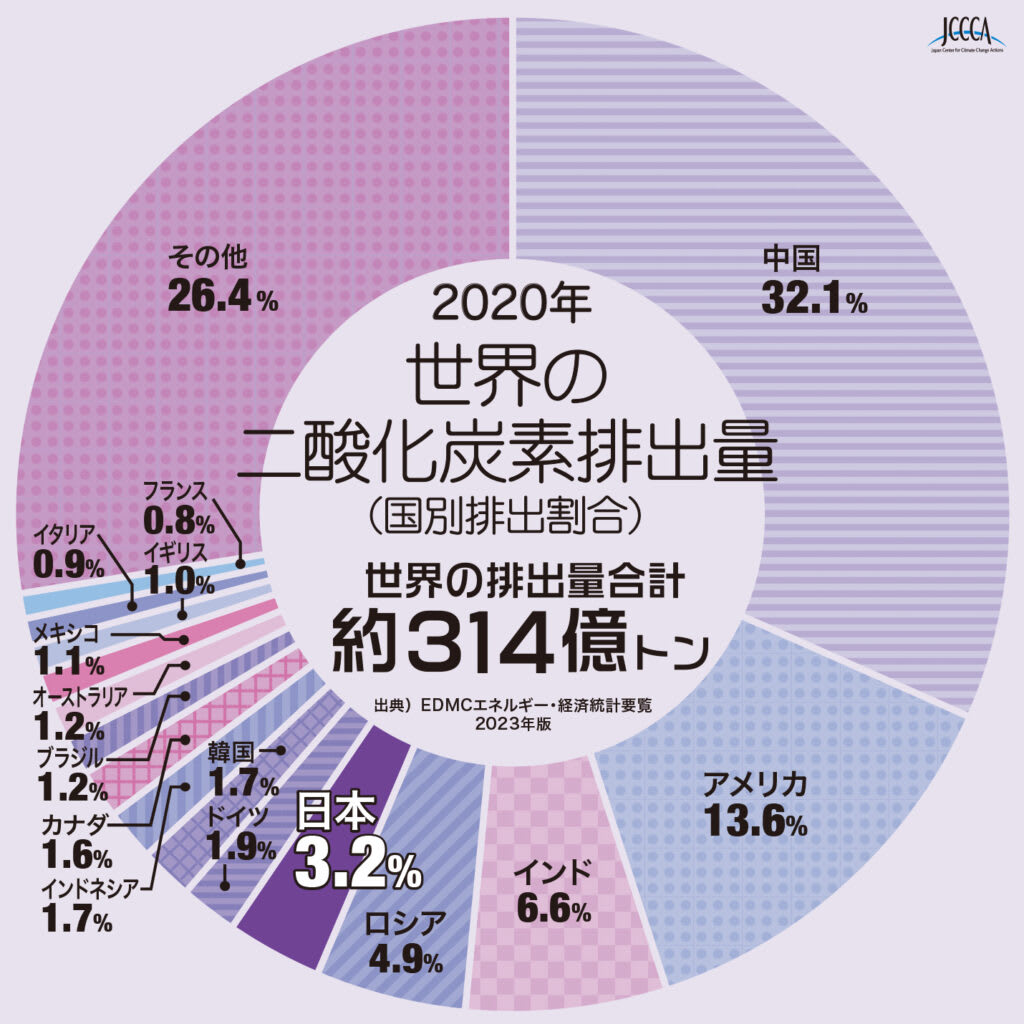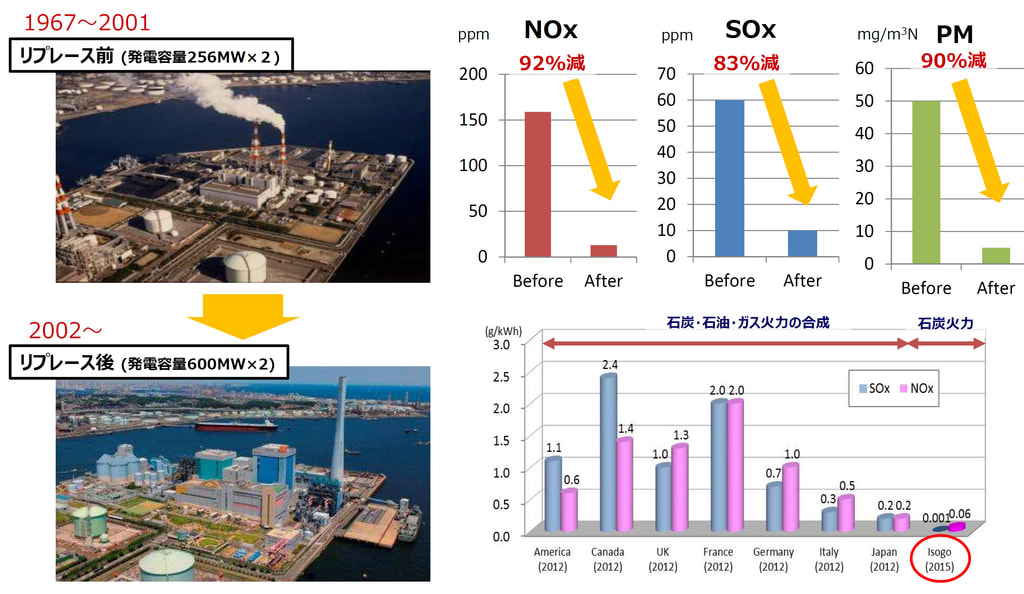最近のプロ選手はパリ~ルーベ等で32Cという幅広タイヤを使用する傾向にあり、タイヤ幅は30Cが標準になるという予測も出ていますが、個人的には懐疑的です。私がロードバイクに乗り始めた頃は23Cタイヤが当たり前でした。それが23C、25C、28Cと徐々に広がって来ているのは確かです。個人的にも23Cのタイヤはもう使用していません。リムブレーキモデルには25Cか28Cを、ディスクブレーキモデルには25C、28C、30Cをホイールによって使い分けています。

使い分けてみた結果、フルクラムのレーシング6DBで使用している30Cはやや重たい印象があります。25Cタイヤは完成車にアセンブルされていた少し重量のあるホイールで使用しています。カーボンディープリムのcannondale Hollowgram R45には28Cを使用していますが、これはホイールがアルミとカーボンという素材の違いがあるので、比較は難しいのですが、25Cと28Cの違いはほとんどないと感じています。チューブはいずれもプチルです。

リムブレーキの時代にはフレームのタイヤクリアランスが広く取れなかったのですが、ロードバイクのディスクブレーキ化が急激に進み、ホイールメーカーもホイールの内径を広いモデルを生産するようになっています。理由は勿論太いタイヤに対応させるためですが、何故、タイヤは太くなり続けるのでしょう。

タイヤメーカーのCONTINENTALが言うには、25Cで空気圧94psi(6.48BAR)のタイヤと23Cで空域圧123psi(8.48BAR)のタイヤは同じ転がり抵抗だそうです。タイヤが太い方がころがり抵抗が少なく、注入する空気量も増えるため乗り心地も良くなることが最大の理由のようです。ただ、太いタイヤはタイヤの重量は増しますから、太ければ良いというものでもないと思っています。

リムブレーキでは15㎜以下だったホイールの内径は今では17㎜以上に広がってきています。今では23Cタイヤが履けるホイールを探す方が難しい状況なのです。ディスクブレーキ用のホイール内径は20㎜を超えるものも増えてきています。ETRTO規格も変更になり、今では内径19㎜が標準になっているのです。

新しいタイヤは新ETRTOに対応して作られていますが、古いタイヤを使用する場合は注意が必要です。ホイールが古く内径が15㎜や17㎜のものを使っている人も同様です。内径17㎜のホイールに新ETRTO規格のタイヤを履かせるとリム幅が2㎜狭くなることで、タイヤ幅も1㎜狭くなるのです。つまり25Cタイヤを履かせたつもりでも、実際は1㎜狭い24Cになる訳です。