
二戸市埋蔵文化財センター。岩手県二戸市福岡八幡下。
2023年6月6日(火)。








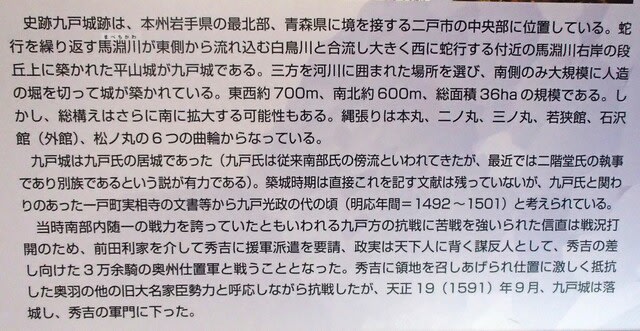
九戸城は、九戸政実(くのへまさざね)の4代前・光政(みつまさ)が明応年間(1492〜1501)に築城したとされる。
九戸城は、馬淵(まぶち)川の右岸に形成された河岸段丘に位置し、南北500メートル、東西750メートルの大きなL字形で、西辺を馬淵川、北辺を白鳥川、東辺を猫淵川に囲まれている。それぞれの川床まで落差は20メートルにも及び、傾斜角45度以上の断崖となっている。南辺は松の丸外側の空堀(幅25~40メートル)と二の丸外側の空堀(幅40メートル、深さ10~12メートル)が切られている。
河岸段丘は2段になっており、三の丸の標高は110メートルほど、本丸や二の丸は130メートル以上ある。浸食地形を最大限に利用した中世的特色の強い、総面積34ヘクタールの広大な平山城である。
本丸と二の丸の間には幅10~18メートル、深さ3~5メートルの空堀があり、石垣が残っている。二の丸には空堀に面して高さ、幅とも1.5~2メートルの土塁が築かれ、本丸とは2つの虎口(こぐち=出入口)でつながれている。
三の丸には旧奥州道中(現在の県道274号二戸一戸線)が横切り、市街地化が進んでいる。 城の南西には松の丸(現在の福岡保育園、呑香稲荷神社、安養寺周辺)があり、南部氏26代・信直が三戸城から移転して盛岡城に移り住む間、7年数カ月の間、南部藩の本城となっていた。









九戸氏の始まりは、南部氏の祖・源光行(南部光行)の六男、九戸行連(ゆきつら)と伝わる。行連が分家して、初め陸奥国九戸郡伊保内(岩手県九戸村)を領し、九戸氏を称したとされる。
しかし、出自には異説もあり、九戸村の九戸神社伝「小笠原系図」によると、結城親朝の配下の総大将小笠原政康の5代の孫小笠原右近将監政実が九戸氏の始祖と伝える。
また九戸氏の確実な史料の初出である「光源院殿 御代当参衆並足軽以下衆覚」永禄6年(1563年)では、南部晴政と並んで「九戸五郎(奥州二階堂)」の名がみえ、二階堂氏との付記がある。古文書に拠ると元弘4年(1334年)に二階堂行朝が九戸を含む久慈郡に代官を派遣したことがみえ、二階堂氏と九戸に関係があったとされる。
鎌倉時代に発祥した奥州南部氏は、南部氏宗家・嫡流とされる三戸南部氏26代南部信直が近世初頭に盛岡藩を確立し幕末には陸奥10カ郡・20万石を領す近世大名となった。
永禄6年(1563年)の室町幕府「諸役人附」の「関東衆」の中に「南部大膳亮」と「九戸五郎」が併記されていることから、南部氏と九戸氏は同格の別族であるという説や、併記は同族並立状態が依然として続いていた北奥羽の様相を反映したものとする説もあり、戦国時代後期の南部地方では三戸南部氏と九戸氏という二大勢力が対立していた。


中世の終焉 九戸政実の乱と豊臣秀吉による鎮圧
天正8年(1580)三戸南部当主の24代晴政(はるまさ)が死去。晴政は晩年まで嫡男がなく、一族の田子信直(たっこのぶなお)を後継者に指名していたが、男子(25代)晴継(はるつぐ)誕生後は信直と不仲となっていた。晴政の死後、南部家は跡目を巡り、信直支持派と晴継擁護の九戸一派とが対立。晴継も13才で暗殺され、混迷の中、信直が南部26代目を継ぐ。
天正18年(1590)、豊臣秀吉は小田原城攻略後、奥州仕置を開始した。小田原不参陣の諸氏を追放するが、仕置軍が去ると残党が蜂起し不穏な状況となる。
この機に乗じ政実は翌天正19年(1591)年3月に挙兵。信直は苦戦を強いられるが、9月には奥州再仕置軍6万騎が馬淵川流域に到着し籠城する約5,000人と対峙する。上方軍は九戸氏菩提寺の和尚を使者に、政実の武勲を称え、婦子女や下級武士の助命を条件に和議を勧告、政実はこれをのんで開門するが、これは謀略で、九戸城はあえなく落城し、政実らは宮城県三迫で処刑された。
秀吉の国内統一は完了し、信直は和賀(わが)・稗貫(ひえぬき)・志和(しわ)の三郡を加封され、九戸城は蒲生氏郷により豊臣流の城に改修される。
信直はこの城を福岡城と改め盛岡に本拠地を移すまでの一時的な居城とし、慶長4年(1599)この地で死去した。その後、元和年間(1615-1623)ごろに信直の子・利直(としなお)が盛岡に本城を移し、福岡(九戸)城は寛永13年(1636)に廃城となった。





埋文センター見学後、北東近くにある国史跡・九戸城跡へ向かった。



















